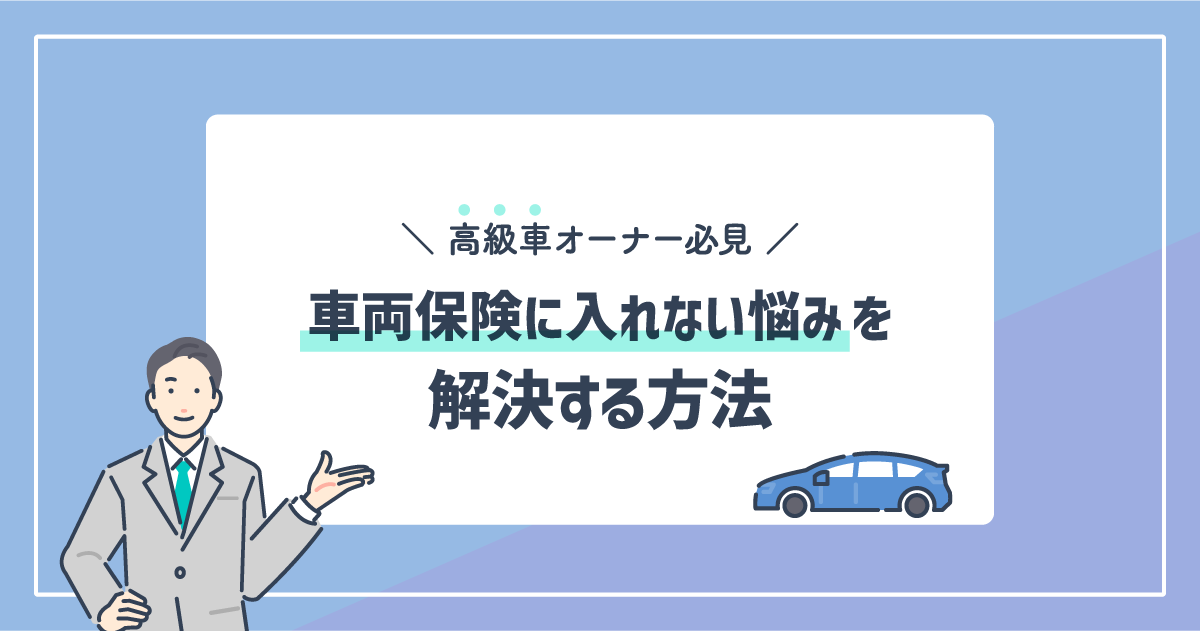脳卒中は、多くの方が聞いたことのあるメジャーな病気でしょう。実際、罹患率も高く、重症化しやすい病気です。
そういった疑問を抱いている方も多いでしょう。
この記事でわかること
- 脳卒中に備えるために必要なお金
- 脳卒中に備えるための「三大疾病保険」
- 脳卒中と診断されてからでも加入しやすい保険
脳卒中とはどのような症状?
脳卒中は、突然発症し、命に関わる重大な疾患です。
とはいえ、どんな病気なのか、どんな備えをすべきかについて、具体的にはわからない方も多いでしょう。まずは脳卒中とはどのような病気か確認しておきましょう。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血をあわせた総称
脳卒中は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つの病気の総称です。
- 脳梗塞:血栓などにより脳の血管が詰まること
- 脳出血:脳内の血管が破れて出血すること
- くも膜下出血:脳を包む膜の下で出血が起こること
発症のメカニズムは異なるものの、いずれも脳血管の異常が引き金となっています。
日本人の死因のうち多くを占める疾患
2020年の統計によると、脳血管疾患は全死亡者数の7.5%を占めています。日本人の死因においても、第4位となっています。

また脳卒中は、片麻痺や言語障害といった後遺症が残りやすい病気です。治療が完了したとしても、日常生活に影響が残るケースも多いでしょう。
脳卒中の治療内容
脳卒中の治療は、長期間にわたるケースが多いです。
早く対処できるほど、治療期間は短く済みます。しかし軽度の脳卒中であっても、入院期間は1週間〜数週間にわたります。
重度の脳卒中の場合、入院期間は数ヶ月から半年以上に及ぶことも。
症状が重い場合は大掛かりな手術も必要になるため、相応の治療費が必要になりそうですね。
脳卒中の治療費用はどれぐらいかかる?

脳卒中になったら、入院や手術が必要です。そこで気になるのは、やはり「医療費」でしょう。
平均的な入院期間が長いため多額の費用が必要
脳卒中の場合、長期間の入院が必要なケースが多いです。そのため、多額の入院費用がかかると考えられます。
厚生労働省が発表した「令和2年(2020)患者調査の概況」によると、脳血管疾患による平均在院期間は「77.4日」です。
また「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》」によると、自己負担費用と逸失収入(働けなることによる収入の減少額)の合計は、1日あたり平均25,800円と報告されています。
そのため、入院だけでも費用はかなり大きくなると考えられます。
さらに症状によっては、手術や多くの検査も必要です。治療費の総額は、非常に高額になると予想できるでしょう。
リハビリが必要になるケースも多いため長期にわたって費用が必要
脳卒中の後遺症によっては、身体機能回復のために長期間のリハビリテーションが必要となります。
脳卒中の後遺症はさまざまな種類があります。そのため症状に応じて、理学療法、作業療法、言語聴覚療法といったさまざまな方法のリハビリが行われます。
利用可能な公的制度
とはいえ、実は治療費の全てが自己負担となるわけではありません。
脳卒中の治療費負担を軽減するために、以下のような公的制度が利用できます。
- 公的医療保険制度
対象となる治療費の自己負担額が3割(年齢によっては1〜2割)
- 高額療養費制度
医療費が高額になった場合、自己負担額が一定の上限額を超えた分が払い戻される
- 傷病手当金
病気やケガで会社を休んだ場合に、健康保険から一定期間、収入の約3分の2が支給される
上記のような制度により、脳卒中の治療費用は大きく軽減されるでしょう。
長期間働けないため収入の減少にも注意
ただし公的制度だけでは、脳卒中の治療費に関する不安がすべて解決できるわけではありません。
脳卒中の治療や療養のためには、長期間仕事を休まなければならない可能性があります。したがって、収入が大きく減少するリスクにも備えなければなりません。
「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》」によると、1日あたりの逸失収入は平均21,000円です。

会社員の場合は、傷病手当金が利用できます。しかし支給期間は最長1年6ヶ月であり、その後は無収入となる可能性があります。金額的にも、傷病手当金だけでは休職前の収入を完全にカバーすることはできません。
さらに、フリーランスや自営業の方は傷病手当金を利用できません。そのため、会社員以上に手厚く備えておく必要があるでしょう。
すでに脳卒中と診断された人は保険に加入できる?

ここまで、脳卒中を発症すると、治療や療養に多額の費用がかかることをお伝えしてきました。
しかし読者の中には、脳卒中と診断されてからこの記事を読んでいる方もいらっしゃるでしょう。
すでに脳卒中と診断されているとしても、保険で治療費に備えることはできるのでしょうか?結論、通常の保険では難しいが、診断後でも加入できるタイプの保険も存在します。
この章では、すでに脳卒中と診断されてからどんな保険を検討すべきかについてご紹介します。「まだ診断されていないけれど、これからのために備えておきたい」という方は、この章を読み飛ばしてください。
脳卒中と診断された人は通常の保険には加入しにくい
結論、脳卒中と診断されたあとに、通常の保険に加入するのは難しいです。
保険会社は加入者の健康状態を審査し、病気になるリスクが高い人の加入を制限しています。そのため、加入時点で何らかの病気にかかっている場合、審査段階で加入を断られることが多いです。
中でも脳卒中は、大掛かりな治療が必要な病気。そのため、脳卒中の診断後に通常の保険に加入するのはかなり難しいでしょう。
審査基準が緩やかな保険なら加入できる可能性がある
引受基準が緩やかなタイプの保険であれば、脳卒中と診断されてからでも加入できる可能性があります。
脳卒中と診断されてからでも加入しやすい保険は以下の2つです。
- 引受基準緩和型保険
- 無選択型保険
引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険は、健康状態の告知項目が少なく済む保険です。そのため、過去に脳卒中になったことがある方でも、通常の保険より審査が通りやすいでしょう。
もし持病があったり入院歴があったとしても、引受基準緩和型の審査は通過できる可能性が比較的高いです。ただし、保障内容や保険金の支払い条件が通常の保険と異なるので、契約内容をきちんと確認しましょう。
無選択型保険
無選択型保険は、健康状態に関係なく、誰でも同じ条件で加入できる保険商品です。そのため、病気が完治していない方や、これから脳卒中の治療をスタートさせる方でも入りやすいでしょう。
しかし、加入してから一定期間は保険金が支払われないタイプが多いです。また一般的に、保険料は通常の保険や引受基準緩和型保険よりも割高に設定されています。
そのため、保障内容や保険料について確認し、脳卒中の治療に間に合うかどうか必ずチェックしましょう。
脳卒中と診断されてから保険に加入する際の注意点
脳卒中の既往歴がある人が保険に加入する際は、以下の点に注意が必要です。
- 告知内容は正直に伝えることが重要
- 保険料と保障内容の確認を怠らないこと
告知内容は正直に伝えることが大切
保険加入時には、病気や体調について正直に告知しなければなりません。
脳卒中であることを隠したり、症状を軽く伝えたりすると、告知義務違反となります。その場合、請求しても給付金が支払われないといったペナルティが課せられます。
「加入時点で嘘をついてもバレないだろう」と思うかもしれません。ですが給付金が請求された段階で、保険会社は詳細な調査を行います。
そのため、嘘の内容を告知したとしても、結局バレてしまう可能性が非常に高いです。
保険料と保障内容をしっかり確認する
また審査基準が緩い保険商品は、通常の保険よりも保険料が高くなる傾向にあります。また、保障内容も通常の保険と異なることが多いです。
そのため、加入前に保険料の金額や保障内容について入念に確認しましょう。
「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」は、通常の保険に比べて保険料が割高に設定されていることが多いです。そのため、無理なく保険料を支払えるか、きちんと確認しておきましょう。
また、加入してから一定期間は保険金が支払われないことも多く、場合によっては脳卒中の治療が始まっても給付金がもらえないことも。
そのような事態を避けるためにも、加入時の確認は入念に行いましょう。
脳卒中に手厚く備えられる「三大疾病保険」とは

突然発症し、治療や療養に多額の費用がかかる脳卒中。また脳卒中だけでなく、がんや心疾患のように、多くの人がかかりやすい大きな病気にもきちんと備えておきたいですよね。
そのような方におすすめなのが「三大疾病保険」です。日本において罹患率が高く、かつ重症化しやすい三大疾病に対し、手厚く備えることができます。
死因の上位を占める「がん」「心疾患」「脳血管疾患」を手厚くカバー
三大疾病保険とは、日本人の死因の上位を占める「がん」「心疾患」「脳血管疾患」という3つの疾患に対応した生命保険です。
一般的な生命保険や医療保険と異なり、三大疾病に特化した保障内容となっているのが特徴です。
がんや心疾患、脳卒中は、入院期間が長くなりやすく、治療費も高額になることが多いです。三大疾病保険に加入すれば、三大疾病に該当する病気にかかった際に給付金を受け取れます。
費用の心配をせずに治療に専念できるため、ストレスや不安も大きく軽減できそうですね。
死亡保険金がもらえるタイプの保険商品もある
三大疾病保険には、死亡保障を兼ねている保険商品もあります。そのため、三大疾病で保険会社所定の状態になった時に一時金が受け取れますが、保険商品によっては死亡保険金を受け取れることもあります。
三大疾病だけでなく、死亡保険として残された人にもお金を用意できるのは心強いですね。
ただし、三大疾病にかかった際の給付回数が複数回ではなく一回のみであったり、死亡保障や高度障害状態のどちらかで給付金を受け取った時点で保険契約が消滅するなど、保険商品によって様々なので、支払いの条件は十分に確認する必要があります。家族に確実にお金を用意したいのであれば、他の生命保険への加入も検討しましょう。
脳卒中になったら保険金はいくらもらえる?

では保険に加入して脳卒中に備える場合、給付金はいくらもらえるのでしょうか?
実際にいくらぐらい受け取れるかを理解すれば「保険に入るべきか」「自力でどれぐらい備えておけばいいか」が分かりますね。
ここからは、脳卒中になった際に受け取れる給付金について解説していきます。
通常の医療保険であれば「入院給付金」や「手術給付金」
まず、一般的な医療保険に加入していれば、入院給付金や手術給付金が受け取れます。
入院給付金は、入院日数に応じて日額で支払われるタイプの保障です。例えば日額1万円の場合、10日間の入院で10万円、30日間の入院なら30万円の給付金を受け取れます。
また大がかりな手術が必要になった場合は、手術給付金が支払われる保険商品が一般的です。手術給付金の算出方法は「倍率タイプ」と「固定額タイプ」となっており、どちらかを選べることもあります。
「倍率タイプ」は、入院給付金に所定の給付倍率をかけた金額がもらえます。たとえば給付倍率が40倍、入院給付金の日額が1万円である場合、手術給付金は40万円です。
一方「固定額タイプ」は、あらかじめ手術給付金の金額が固定で決まっているタイプです。
三大疾病保険であれば追加で保険金が受け取れる
さらに三大疾病保険に加入しておけば、数百万円〜数千万円の給付金が追加でもらえます。
通常の医療保険や生命保険だけでは不安だと感じる方にとっては、とても心強いですよね。
また先述したように、三大疾病保険に加入しておけば死亡保険金も用意できます。脳卒中やがんなどの病気で給付金を受け取らなかった場合、代わりに死亡保険金がもらえることがあります。
脳梗塞は保険金が出ないって本当?
「脳梗塞になったら保険金が出ない」ということを聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
結論、脳梗塞になっても保険金を受け取ることはできます。ただし、そのためには「支払い要件」をクリアしなければなりません。
医療保険であれば、病気を問わず入院や手術が必要になったら保険金が支払われます。注意が必要なのは「三大疾病保険」です。
多くの三大疾病保険では「発病し、初めて医師の診断を受けた日から60日以上継続して、労働の制限が必要だと医師が判断した」ことが支払い要件として定められています。
しかし医療技術の進歩により、脳梗塞の治療方法は格段に向上しています。そのため、保険金の支払要件をクリアする前に治療が完了してしまうケースが増えていると考えられます。
その結果「脳梗塞は保険金が出ない」と言われるようになった、というのが実情でしょう。
まとめ:脳卒中リスクに備える保険選びのポイント
脳卒中に対しては、通常の医療保険や生命保険でも備えられます。ですが脳卒中になる可能性は決して低くなく、治療費も高くなりやすいです。
そのため、三大疾病保険のように「脳卒中に確実に備えられる保険」を選ぶのもひとつの手です。効果的に保険を活用すれば、お金の心配をせず、治療に専念できるでしょう。
また、もし脳卒中と診断されてから加入したいのであれば、加入基準が緩やかなタイプの保険を選びましょう。ただしその場合、保険料や保障内容のチェックを怠らないのが大切です。
保険選びに迷ったらプロを頼ろう
しかし、どのような保険に入るべきかについては、多くの方が悩むでしょう。
保障をどれだけ手厚くすべきか、どの保険会社が最もお得かなど、自力で考えるのが難しいポイントも多いですよね。多くの保険会社の特性を理解しつつ比較検討するのは、なかなか骨が折れる作業です。
だからこそ、保険選びに迷ったら保険のプロに相談するのがおすすめです。みんかぶ保険では、保険の専門知識を豊富に持つプロに無料で相談できます。
「保険会社ごとに一括で見積もりを依頼したい」「他の人がどのような保険に加入しているか知りたい」など、自力では調べるのが難しいこともプロに一任できます。
しつこい営業をかけられることもないため、安心して利用可能です。
保険選びで迷ってしまったら、気軽に活用してみてください。