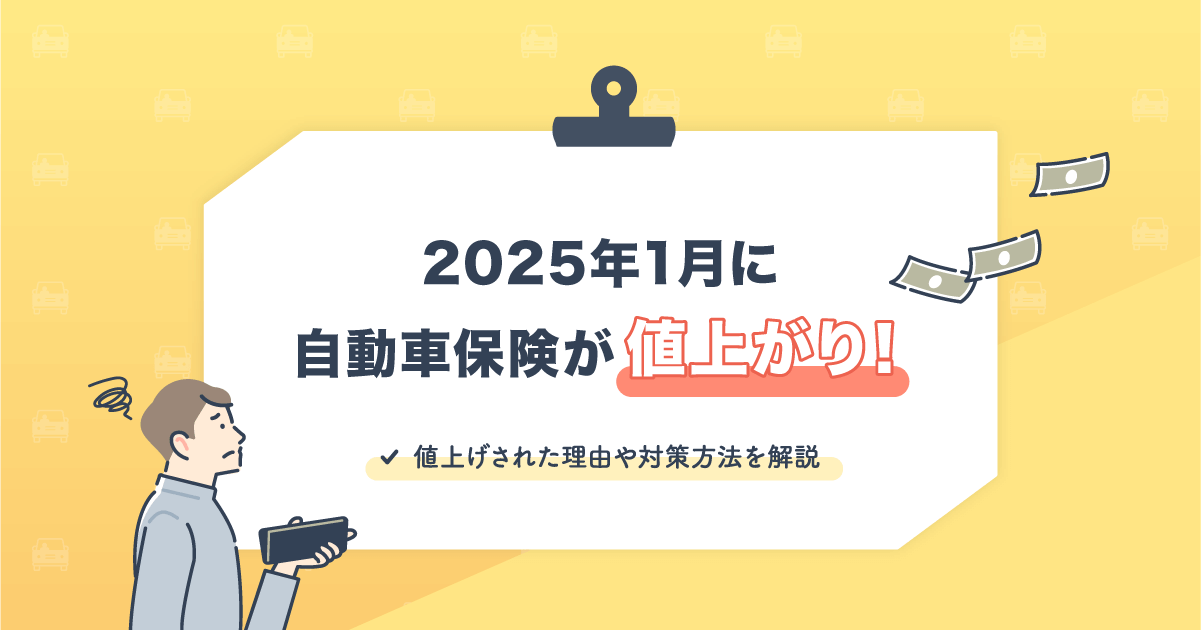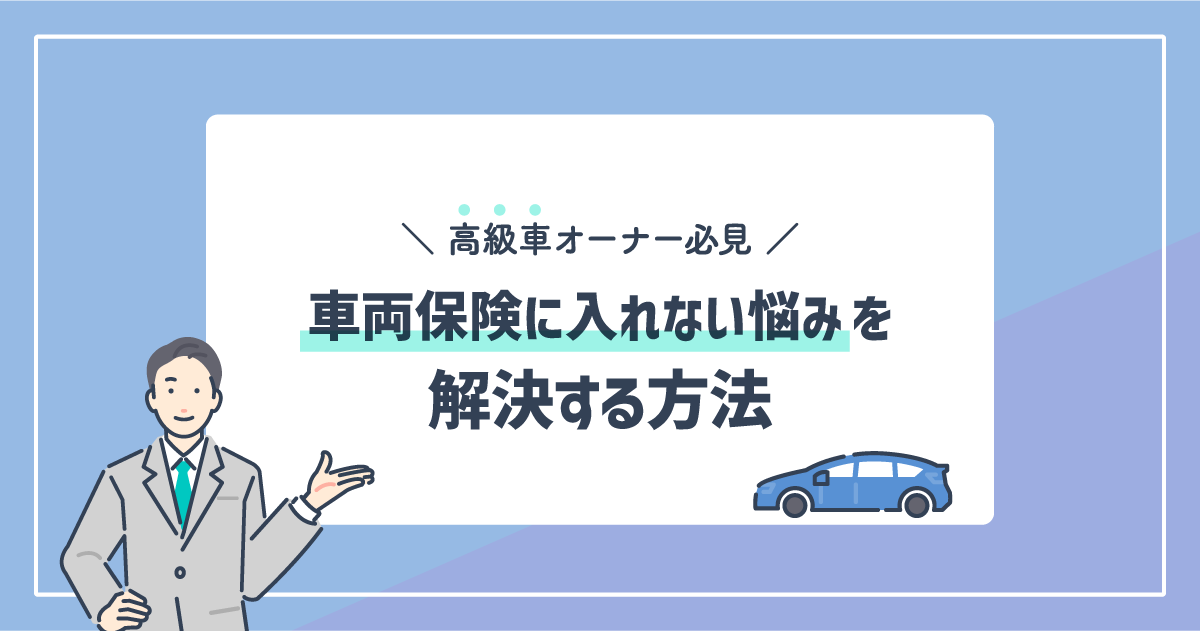初めて自動車保険に入る人の中には、わからないことだらけで困っている方もいらっしゃるでしょう。
そのような人に向けて、この記事では『初めての自動車保険』に関する基礎知識から、保険料を安く抑えるコツまで徹底解説します。
- 自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」に分かれるが、自賠責保険だけでは補償が不足する可能性が高い
- 20代前半は保険料が高めだが、補償内容の選び方や契約方法によっては保険料を抑えられる
- 補償選びで重要なのは保険料とのバランス。先に保険料の上限を決めておくと補償内容を決めやすい
自動車保険とは? 仕組みについて解説
自動車保険とは、交通事故を起こしてしまった場合に発生する「賠償金の支払い」をカバーするための保険です。
また自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があり、それぞれ役割が異なります。
車を買ったらとりあえず自動車保険にも入る、となんとなく思っている人もいるでしょう。しかし任意保険と自賠責保険の違いについてきちんと理解しておかないと、保険選びの際に混乱してしまう原因となってしまいます。
まずは自賠責保険や任意保険がどのようなものかについて、具体的に解説していきます。
自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険とでは、役割も補償範囲も大きく異なります。まずは以下の表で基本的な違いを確認してみましょう。
| 加入義務 | 補償内容 | |
|---|---|---|
自賠責保険 | 加入しなければならないと法律で決められている(自動車検査証の交付を受ける際に必須) | 対人賠償のみ(相手の死傷)。 また補償額には上限あり。 後遺障害:最高4,000万円、死亡:最高3,000万円、傷害:最高120万円 |
任意保険 | 任意(法的義務なし) | 対人・対物賠償に加え、自分や同乗者の補償、車両損害など幅広くカバー。契約内容に応じて高額補償も可能 |
自賠責保険はすべての車両オーナーに課せられた「最低限の社会的義務」です。それに対し、任意保険は自分自身と資産を守るための補償が用意されています。
ここからは、自賠責保険と任意保険がそれぞれどのような特徴を持っているのか、さらに詳しく見ていきましょう。自賠責保険の補償内容や任意保険の必要性について具体的に理解することで、自分に合った保険選びができるようになります。
自賠責保険は加入が義務付けられているが補償は限定的
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、1955年に法律で定められた強制保険です。
交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、すべての自動車所有者に加入を義務付けています。
しかし、自賠責保険の補償範囲は任意保険と比較すると、限定的です。自賠責保険は「交通事故の被害者保護」のための最低限の保険であり、ドライバー自身を守るための保険ではないため正しい認識を持っておく必要があります。
任意保険は自賠責保険と比較して補償が充実
任意保険は、その名の通り加入が法的に義務付けられてはいませんが、自賠責保険では足りない部分を補完する重要な役割を果たします。万が一の際の備えとしてドライバーの中には何らかの任意保険に加入しているのが現状です。
任意保険の最大の特徴は、補償範囲の広さと柔軟性。対人賠償においては自賠責保険だけでは足りない補償額をカバーできます。さらに、自賠責では補償されない対物賠償(相手の車や建物など物的損害)もカバー可能です。
また任意保険なら、自分や同乗者のケガも補償の対象です。車両保険を付ければ自分の車の修理費もカバーされるため、事故によって生じるさまざまなリスクから総合的に身を守れます。
さらに追加の補償や特約を自由に選ぶことも可能です。例えば、以下のような特約を利用できます。
| 特約名 | 補償内容 |
|---|---|
弁護士費用補償特約 | 交通事故で示談交渉や訴訟が必要になった場合に、弁護士費用や訴訟費用を補償。 |
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者およびその家族が125cc以下の原動機付自転車を運転中に起こした事故を補償。 |
車内身の回り品補償特約 (携行品補償特約) | 車内に置いたPC、カバン、ゴルフバッグ、カメラなどの荷物が事故や盗難で損害を受けた場合、その修理費や損害金を補償(※現金や宝石などは対象外)。 |
無保険車傷害特約 | 相手が無保険または補償金額が低い場合に、被保険者自身のケガ、後遺障害、死亡に対する補償を受けられる。 |
他車運転危険補償特約 | 自分の車ではなく、一時的に借りた他人の車を運転中に事故を起こした場合でも、自身の保険で補償が受けられる。 |
対物超過修理費用補償特約 | 事故により相手車両の修理費用が車の時価額を超えた場合、その差額を一定額まで補償(通常の対物賠償保険の補償限度を超える部分をカバー)。 |
ロードサービス特約 | 故障や事故で車が動かなくなった際に、レッカー移動、タイヤ交換、バッテリー上がりなどの緊急対応サービスを提供(契約内容によっては距離やサービス内容に差がある場合もある)。 |
ご自身の生活スタイルや不安度に合わせて、柔軟に補償内容を選べます。
自賠責保険だけでは足りないと言われる理由
と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし現実的には、自賠責保険だけでは到底カバーしきれないケースも数多く存在します。
| 事故内容 | 加害者に命じられた賠償額 |
|---|---|
31歳の主婦が死亡 | 約9,800万円 |
66歳の会社経営者が死亡 | 約7,600万円 |
22歳男性が事故により高次脳機能障害に | 約2億3,500万円 |
相手が重度の後遺障害を負った場合、その補償額は1億円を超えることも決して珍しくありません。自賠責保険の上限である3,000万円(死亡時)や4,000万円(後遺障害時)では到底足りず、差額は全額自己負担となってしまいます。
また、相手の車やガードレール、建物などを破損させた場合でも、自賠責保険では補償されません。
修理費は数万円から数百万円に及ぶこともあり、その全額が自己負担となります。
さらに、自分自身や同乗者のケガ、自分の車の修理費も自賠責保険では補償されません。もし事故を起こして自分がケガをした場合や、大切な車が大きく破損したとしても、その費用はすべて自己負担となるのです。
このような理由から、自賠責保険だけでは「最低限の法的義務を果たす」ことはできても、現実的なリスク対策としては大きく不足していると言えます。
https://ins.minkabu.jp/columns/voluntary-car-insurance-230208
任意保険の補償内容は主に3つ
任意保険はドライバーを守るための重要な役割を果たしてくれますが、まず混乱しやすいのが「補償内容」でしょう。任意保険に加入することで「何を」「どの程度」補償されるのか、きちんと整理しておく必要があります。
ここからは、以下の3つに分けて、任意保険の補償内容について解説していきます。
相手への補償(対人・対物)
自分と同乗者への補償(人身傷害・搭乗者傷害)
自分の車への補償(車両保険)
相手への補償|対人・対物賠償保険
交通事故で最も心配なのは、他人を傷つけたり、他人の財産に損害を与えたりした場合の賠償責任でしょう。そのような事態に備えるための「相手への補償」には「対人賠償保険」と「対物賠償保険」の2種類があります。
対人賠償保険は、事故によって他人を死傷させた場合に、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益など、法律上の損害賠償責任を補償します。自賠責保険でも相手に対する補償はありますが、その上限額を超える部分もカバーするのが対人賠償保険の役割です。
一方で対物賠償保険は、他人の車や建物、電柱、ガードレールなどの物的損害に対する賠償責任を補償します。自賠責保険では物損はまったく補償されないため、任意保険の中でも特に重要な補償です。
高級外車との接触事故で数千万円の修理費が発生したり、重度の後遺障害を相手に負わせてしまい億単位の賠償責任が生じたりするケースが現実に起きています。一度の事故で家計が破綻するリスクがあるため、対人・対物補償が充実しているのは心強いですね。
自分と同乗者への補償|人身傷害・搭乗者傷害
交通事故では、他人だけでなく、自分自身や同乗者もケガをする可能性があります。しかし任意保険に加入していれば「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」といった補償で備えられます。
「人身傷害保険」は、契約者や同乗者が事故でケガをした場合、過失割合に関係なく実際の損害額をカバーする補償です。
例えば、自分に70%の過失がある事故の場合、通常は相手からの賠償は30%分しか受けられません。しかし人身傷害保険があれば、残りの70%分も含めて全額補償を受けられます。
入院費や通院費はもちろん、休業損害や後遺障害が残った場合の逸失利益なども補償対象です。
一方「搭乗者傷害保険」は、ケガの程度や部位によってあらかじめ定められた金額が支払われる補償です。例えば、骨折で○○万円、入院1日につき×千円といった形で補償金が支払われます。
人身傷害保険と比べると補償内容はシンプルですが、必要な手続きが簡単であるという特徴があります。
特に怪我をしやすい子どもや高齢者を乗せる機会が多い場合は、手厚い補償を検討すべきでしょう。
また、搭乗者傷害保険と人身傷害保険とを併用すれば、入院中の出費にも対応できるというメリットが得られます。
ご自身と同乗者を守るために、これらの補償をどのように組み合わせるか、家族構成や利用状況に合わせて検討することが大切です。
https://ins.minkabu.jp/columns/car-insurance-structure-0330
自分の車への補償|車両保険
交通事故や自然災害によって自分の車が損傷した場合に備えるのが「車両保険」です。他の補償と異なり、車両保険は付帯するかしないかを自由に選べることが多く、車の価値や使用状況によって判断が分かれるポイントとなります。
車両保険には主に「一般型」と「エコノミー型」の2種類があります。
一般型は、単独事故や当て逃げ、自然災害など、幅広いケースでの車の損害を補償します。例えば、路肩に接触して車を傷つけた場合や、駐車場で何者かに傷をつけられた場合なども補償の対象です。補償範囲が広い分、保険料も高めに設定されています。
一方、エコノミー型(限定型)は、補償範囲を限定することで保険料を抑えられるタイプです。単独事故や自然災害による損害は補償対象外となりますが、「他車との事故」はカバーされているため、保険料を抑えたい場合に選択されることがあります。
新車や高級車を所有している場合や、ローンが多く残っている場合は、車両保険に加入しておくのがおすすめです。一方、車の時価が低い場合や維持費を抑えたい場合は、車両保険を付けずに他の補償を充実させるという選択肢もあります。
https://ins.minkabu.jp/columns/vehicle-insurance-221210
自動車保険の「等級制度」とは?

自動車保険に加入する際は補償内容だけでなく「保険料」も重要ですよね。
任意保険では保険料が一律に決められているわけではなく、さまざまな要因によって決まります。特に注目すべきなのが「等級制度」です。
自動車保険ならではの制度だからこそ、等級制度がなぜ設けられているのか、保険料がどのように変わっていくのかについてもきちんと理解しておきましょう。
等級制度によって公平性を保つ
自動車保険の等級制度は、保険契約者間の公平性を確保するために導入されています。
自動車保険は、多くの人がお金(保険料)を出し合い、事故に遭った人を皆で支える「相互扶助」という仕組みで成り立っています。しかし、もし頻繁に事故を起こす人と、何十年も無事故の人が同じ保険料を払うとしたら、それは果たして公平といえるでしょうか。
そのような「不公平感」を解消するために設けられたのが「ノンフリート等級制度」です。
等級制度により、事故を起こさず安全運転を続ける人ほど等級が上がり、保険料の割引率が高くなります。実際の割引率は保険会社により異なりますが、20等級(最高等級)に達すると、基本保険料の約70%もの割引が適用されることもあります。
反対に、事故を起こして補償金を請求すると等級が下がり、保険料が割高になっていきます。

初めての自動車保険では6等級からスタート
自動車保険に初めて加入する場合、基本的には「6等級」からスタートすることになります。
6等級からスタートしたあと、1年間無事故で過ごせば翌年の契約更新時に7等級へと上がります。その後も毎年無事故であれば1等級ずつ上昇し、最終的には最高等級の20等級まで到達可能です。
ただし、事故を起こして補償金を請求すると、事故の種類や件数に応じて等級がダウンします。一般的に、3等級ダウン事故と1等級ダウン事故の2種類があります。
3等級ダウン事故:対人・対物事故で損害賠償が発生するケースなど
1等級ダウン事故:単独事故など
気をつけていても交通事故は発生してしまうかもしれませんが、なるべく安全運転を心がけたいところですね。事故のリスクを減らすだけでなく、経済的にも大きなメリットに繋がります。
https://ins.minkabu.jp/columns/car-insurance-grade-221017
初めての自動車保険にかかる保険料は?保険料の年代別相場やシミュレーション
自動車保険に加入する際、最も気になるのは
という点ではないでしょうか。実際のところ、自動車保険の保険料は一律ではなく、さまざまな要素によって大きく変動します。
同じ車種でも、運転する人の年齢や運転歴、等級によって数万円、場合によっては10万円以上も差が出ることもあるのです。
しかし、初めて自動車保険に加入する方にとっては、その変動要因や相場がわからず不安に感じることも多いでしょう。ここからは、自動車保険の保険料がどのような要素で決まるのか、また年代別や車種別の一般的な相場はどの程度なのかを解説していきます。
保険料は年齢・等級・車種で変わる| 保険料の目安
自動車保険の保険料は、主に「運転者の年齢」「等級」「車種」の3つの要素によって大きく変動します。この3つの要素はいずれも、保険会社が「事故を起こす確率」を統計的に判断するための重要な指標です。
等級については、保険会社ごとに独自の割引率が設けられています。また運転者の年齢が高いほど、等級も高くなりやすいです。
そのため、この記事では「運転者の年齢」と「車種」に絞って、保険料の目安をシミュレーションしていきます。
20代前半は事故リスクが高いと判断されるため保険料が高め
20代前半は、初めて自動車保険に加入する人が多い年代です。免許を取得してまだ日が浅く、運転経験が少ないことから、統計的に事故リスクが高いと判断されます。そのため保険料も、全年齢層の中で最も高くなりやすいです。
具体的な相場を見てみましょう。

(当社調べ2011年4月~2022年4月)
20歳〜24歳の初心者ドライバーが新たに保険に加入する場合、基本補償に車両保険を加えると、保険料は年間15万円近くかかることも少なくありません。
20歳〜24歳になると、18歳〜19歳と比べて若干保険料は下がりますが、それでも他の年齢層と比較すると高めです。この年代で初めて保険に加入する場合、保険料は年間10万円〜15万円程度が目安となるでしょう。
ただし、これらはあくまで一般的な相場です。実際の保険料は車種や等級、補償内容によって大きく変動します。
保険料が高いと感じる若年層の人も多いでしょう。しかし無事故のまま等級を上げていけば、徐々に保険料は下がっていきます。
少しでも保険料を抑えたい場合は「21歳以上補償」といった年齢条件を設定することで、保険料を下げられます。21歳未満の方は補償対象外となりますが、保険料は全年齢補償と比べて20%〜40%程度安くなることも。
ただしその場合、21歳未満の友人や家族に車を貸すことができなくなります。生活スタイルに合わせて慎重に選びましょう。
30代・40代は20代よりも保険料の相場が低い
30代・40代になると、運転経験も豊富になり、統計的に事故発生率が下がるため、保険料も20代より安めに設定されます。また、すでに加入してから数年間が経過した人も多く、等級が上がっているケースも多いです。
年齢条件を「26歳以上補償」や「30歳以上補償」に設定すれば、保険料をさらに抑えられます。
また、家族構成によっては「夫婦限定」や「本人・配偶者限定」といった運転者限定特約を付けることで、保険料を下げられます。
軽自動車/普通車の型式別料率クラス
年代の次に、車種による保険料の違いについてもチェックしておきましょう。
多くの保険会社では「型式別料率クラス」というシステムを採用しています。車の型式ごとの、過去の事故率や修理費用、盗難率などの統計データをもとにクラス分けされたものです。

軽自動車の場合、料率クラスは1〜4に区分されています。一般的に軽自動車は普通車と比べて車両価格が安く、修理費用も低く抑えられることから、保険料もリーズナブルに設定されていることが多いです。
例えば、同じ補償内容・条件で比較した場合、軽自動車の保険料は普通車と比べて2〜3割程度安くなることがあります。
一方、普通車の料率クラスは1〜9まであり、クラスが高いほど保険料も高くなります。スポーツカーや高級車、輸入車などは高いクラスに分類されやすく、同じ補償内容でも軽自動車の2倍以上の保険料がかかることも。
注意すべきなのは、同じ車種区分でも型式によってクラスが異なることです。例えば同じ軽自動車でも、人気車種や事故率の高い車種は高めのクラスに設定されやすいです。
また、普通車でも小型・コンパクトタイプは比較的低いクラスに分類され、保険料も抑えられることがあります。
車を購入する際に、燃費や維持費だけでなく、料率クラスも考慮すれば、必要な費用を長期的に予測できます。各保険会社のホームページにて、自分の検討している車種のクラスを事前に確認してみるのも良いでしょう。
初めての自動車保険の選び方|保険料を抑えつつベストな補償内容を決めるコツ

ここからは、いよいよ「初めての自動車保険の選び方」についてご紹介していきます。
自動車保険に初めて加入する際、
と考える人も多いでしょう。保険料と補償内容は一般的にトレードオフの関係にあり、手厚い補償を選べば保険料は高くなりがちです。
しかし、賢い選び方をすれば、必要な補償を確保しながらも無駄な出費を抑えられます。効果的に保険料を抑えるためには、どの条件が保険料に影響するのかを把握しておくことが重要です。
ここからは、以下のようなステップで自動車保険の選び方をご紹介します。
保険会社のタイプを選ぶ
運転者年齢条件と運転者限定を決める
補償内容を選ぶ
車両保険の有無を決める
支払い方法を決める
割引制度がないか確認する
それぞれの項目ごとに、わかりやすく解説していきます。
保険会社のタイプを選ぶ|ネット型か代理店型か
自動車保険を提供している保険会社は「ネット型」と「代理店型」の2種類に分けられます。
近年はネット型の自動車保険がシェアを拡大しています。しかしそれぞれのメリット・デメリットをきちんと理解した上で、自分のニーズに合った選択をするのが大切です。
| 保険のタイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
ネット型 通販型・ダイレクト型 |
|
|
代理店型 |
|
|
どちらが自分に合っているかは、「保険に関する知識や経験があるか」「対面でのサポートを重視するか」「保険料の安さを優先するか」などによって変わってきます。それでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
ネット型のメリット・デメリット
まずはネット型自動車保険のメリット・デメリットをご紹介します。
| 保険のタイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
ネット型 通販型・ダイレクト型 |
|
|
ネット型自動車保険の最大のメリットは、なんといっても保険料の安さです。
代理店や営業員の人件費、店舗の維持費などのコストがかからないため、同等の補償内容でも代理店型より10〜30%程度安くなるのが一般的です。特に若年層や事故歴のあるドライバーなど、保険料が高めに設定されがちな層にとっては嬉しいメリットですね。
また、ネット型保険は24時間365日いつでも申し込みや変更手続きができます。深夜や休日でも、スマホやパソコンからすぐに見積もりを取ったり、契約内容を変更したりすることも可能。忙しい方や店舗へ行くのが難しい人にとって大きなメリットです。
一方、ネット型保険の最大のデメリットは、自分自身で補償内容を選ぶ必要があるという点です。対面でのアドバイスがないため、保険に関する知識が不足していると、必要な補償を見落としたり、逆に過剰な補償内容を設定してしまうリスクがあります。
また、事故発生時の対応も電話やメールが中心です。そのため直接相談できる担当者がいないことに対し、不安を感じる方もいるでしょう。
まとめると、ネット型保険は
自分に必要な補償を自分で判断できる
シンプルな補償内容で十分だと感じる
保険料の安さを最優先したい
という人に向いています。初めて自動車保険に加入する場合でも、事前に補償内容を理解できていれば、ネット型保険で保険料を節約できるでしょう。
代理店型のメリット・デメリット
次に、代理店型自動車保険のメリット・デメリットをチェックしてみましょう。
| 保険のタイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
代理店型 |
|
|
代理店型自動車保険の最大のメリットは、保険の専門家による対面でのアドバイスが受けられる点です。
複雑な保険商品の中から自分に合った補償内容を選ぶ際、経験豊富な担当者からのアドバイスは非常に心強いものです。特に初めて自動車保険に加入する方や、保険の知識に自信がない方にとっては、大きな安心材料となるでしょう。
また代理店型保険のメリットとして「事故対応の手厚さ」も挙げられます。事故発生時には、担当者が直接相談に乗ってくれるため、煩雑な手続きや保険会社とのやり取りをすべて任せられます。
経験豊富な担当者が付くことで、事故時にも適切な対応やアドバイスが受けられ、精神的な負担も軽減されるでしょう。さらに、地域密着型の代理店であれば、地元の整備工場や病院などとのネットワークを活かした迅速な対応が期待できます。
一方、代理店型保険の最大のデメリットは「保険料の高さ」。営業コストや手数料が保険料に上乗せされるため、同じ補償内容でもネット型と比較して保険料が高くなりがちです。
差額は年間で数千円から数万円に及ぶこともあり、長期的に見れば大きな金額になります。また、代理店の営業時間内でないと相談や手続きができないというデメリットもあります。
以下の特徴に当てはまる人は、代理店型保険がおすすめです。
保険の専門知識が少ない
万が一の事故時に手厚いサポートを求める
対面での相談を通じて安心感を得たい
保険料が多少高くなっても、安心感やサービスの質を重視したい人には、代理店型がおすすめです。
運転者年齢条件と運転者限定を決める
「運転者年齢条件」と「運転者限定」を適切に設定できれば、自動車保険料を効果的に抑えられる可能性があります。つまり
何歳以上の人が運転するか
誰が運転するか
を決める、ということです。
保険の対象となる人の範囲や年齢を制限することで、保険料を大きく抑えられます。そのため普段誰が車を運転するかによって、適切に条件を設定しましょう。
運転する人の範囲や年齢に関する条件について、より具体的に解説していきます。
運転する人を家族や本人に限定できる
「運転者限定」とは、自動車を運転する人の範囲を限定することで保険料を抑えられる条件のことです。
主な選択肢には「限定なし」「家族限定」「本人・配偶者限定」「本人限定」などがあります。限定する範囲が狭いほど保険料は安くなりますが、その分だけ補償される運転者の範囲も狭まります。
「家族限定」は、契約者本人とその家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)のみが運転する場合に補償される設定です。友人や知人、別居の既婚子どもなどが運転する場合は補償対象外となります。
家族以外には車を貸さないという人は、補償の対象を家族に限定するのもおすすめです。
さらに範囲を狭めた「本人・配偶者限定」は、契約者本人とその配偶者のみが補償対象となり、同居の親や子どもであっても補償されません。夫婦のみの世帯や、子どもがまだ運転しない家庭に適しています。
最も限定範囲が狭い「本人限定」は、契約者本人のみが運転する場合に限り補償される設定です。最も保険料を抑えられる条件ですが、配偶者も補償対象外となる点に注意が必要です。一人暮らしで、他の人に車を貸さない方向けの選択肢でしょう。
運転者限定を決める際は、
年末年始の帰省時に別居の子どもが運転する可能性はないか
緊急時に友人が運転する場面は想定できないか
など、現実に起こりうる状況をきちんと想定しておくのが大切です。安易に保険料だけを優先させるのではなく、自分のライフスタイルに合った、最適な設定を選びましょう。
年齢による制限は全年齢・21歳以上・26歳以上など
運転者の範囲だけでなく、補償の対象となる運転者の年齢も制限すれば、さらに保険料を抑えられます。主な選択肢は「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」などです。
基本的に、年齢が若い人まで補償対象に含めるほど、保険料は高くなります。
「全年齢補償」は文字通り、年齢を問わず誰が運転しても補償対象となる設定です。10代の若者から高齢者まで幅広くカバーできますが、その分保険料も高くなります。
「21歳以上補償」に設定すれば、21歳未満の方が運転中の事故は補償対象外となります。しかしその分、保険料は「全年齢補償」よりも割安です。さらに「26歳以上補償」に設定すれば、保険料はさらに安くなります。
ただし設定年齢に満たない人が運転して事故を起こした場合、原則として補償金は支払われません。例えば「26歳以上補償」に設定している場合、25歳の家族や友人が運転中に事故を起こしても補償の対象外です。
数百万円、場合によっては数千万円の賠償責任を自己負担することになりかねません。誰が運転する可能性があるかを慎重に考えたうえで、年齢条件を設定しましょう。
補償内容と保険料のバランスに気をつけながら補償内容を選ぶ
ここまでで保険会社や条件についてある程度絞れたら、いよいよメインの補償内容を決めていきます。
自動車保険を選ぶ際に最も重要なのが、保険料と補償内容のバランスです。補償の手厚さと保険料はトレードオフの関係。補償内容が手薄になりすぎてはいけませんし、逆に補償を盛り込みすぎると保険料の支払いが苦しくなってしまいます。
最適なバランスを見つけるコツは「先に保険料の上限額を決めておくこと」です。毎月何円までなら無理なく支払えるか先に計算しておき、その範囲内で補償を充実させていくと、補償の最適な手厚さを見つけやすいでしょう。
また補償内容を決めていく際は「自分の車の使用状況」「家族構成」「運転頻度」などを考慮し、リスクの大きさを客観的に評価することが大切です。
例えば、家族が頻繁に乗る車なら、対人・対物賠償は無制限にしつつ人身傷害保険の金額は状況に応じて調整する、といった補償内容も考えられます。
加えて、保険会社によって基本補償の内容や用意している特約は異なります。ある保険会社では標準で組み込まれている補償が、別の会社では有料の特約になっていることも珍しくありません。
そのため複数の保険会社の見積もりを比較し、それぞれの特徴を理解しておくと、よりベストな選択ができるでしょう。
基本補償・特約だけでなくロードサービスや事故対応の内容も要チェック
自動車保険を選ぶ際、多くの人は補償内容や保険料にばかり目を向けがち。ですが実は「ロードサービス」と「事故対応」の質も重要な判断基準です。
ロードサービスや事故対応は、いざというときの安心感や満足度を大きく左右します。
ロードサービスとは、故障やトラブルが発生したときに提供される支援サービスのことです。バッテリー上がり、タイヤのパンク、ガス欠、キー閉じ込みなどの日常的なトラブルから、事故や故障によるレッカー対応まで、幅広い状況をサポートしてもらえます。
保険会社によって無料レッカーの距離制限(30kmから無制限まで様々)、タイヤ修理の補償範囲、宿泊・帰宅費用のサポート内容などが異なります。保険会社や補償内容を決める際に、ご自身の生活スタイルに合ったサービス内容かどうかを確認しましょう。
一方で、事故対応とは、事故発生時の初期対応から示談交渉、補償金支払いまでの一連のプロセスを指します。24時間365日の連絡体制があるか、担当者の対応速度はどうか、被害者との示談交渉支援はどこまで行ってくれるかなど、会社によって対応品質に差があります。
特に初めての事故では、どれだけ手厚く対応してもらえるかどうかで、その後の負担は大きく変わります。
ロードサービスと事故対応をチェックする際は、公式サイトだけでなく実際のユーザー評価も参考にするのがおすすめです。特に口コミサイトやSNSでの評判は、リアルな体験に基づく貴重な情報源となります。
また担当者に直接質問することで、対応の丁寧さや知識の深さを確認することもできます。保険料の安さだけでなく、いざというときの安心感も大事にしたいですね。
車両保険の有無を決める
ひとつ前のポイントと重なる部分でもありますが、車両保険の有無も保険料を左右する重要な項目です。
事故やいたずら、盗難、自然災害など、様々な原因による車の損害に対して補償を受けられる心強い補償ですが、同時に保険料を大きく左右する補償でもあります。車両保険だけで、総保険料の3〜5割を占めることも珍しくありません。
車両保険の必要性が高い人と低い人の特徴を、それぞれ表にまとめました。
| 車両保険の必要性が高い人 | 車両保険の必要性が低い人 |
|---|---|
|
|
どのような人は車両保険の必要性が高い/低いのか、より具体的に解説していきます。
車両保険の必要性が高い人の特徴
車両保険が特に必要性の高い方の特徴としては、まず「新車や高額車の所有者」が挙げられます。車の価値が高いほど、修理費用も高額になりがちです。
また「自動車ローンが残っている人」も要注意です。事故で車が大破しても、ローンの支払い義務は残るため、修理費や買い替え資金の確保が必要になります。
「運転に不安がある初心者ドライバー」も車両保険の必要性が高いでしょう。運転技術が未熟なため、単独事故やこすり傷などのリスクが相対的に高く、修理の頻度も高い傾向があります。
車両保険の必要性が低い人の特徴
一方、車両保険の必要性が低いと考えられるのは、「車の時価額が低い」場合です。車の価値が保険料を大きく下回ると、費用対効果の面で車両保険の必要性が低くなります。
また「運転頻度が非常に少ない」場合も、事故リスクが相対的に低いため、車両保険の必要性は下がります。
加えて「万が一の出費に耐えられるか」という経済的な観点も重要です。高額な修理費の支払いが突然必要になっても支払う余裕があるのであれば、わざわざ車両保険を追加する必要はありません。
一般型・エコノミー型・車両保険なしのメリット・デメリット比較
車両保険を選ぶ際「追加する or しない」だけでなく、車両保険のタイプについても考えてみるのがおすすめです。
車両保険には「一般型」と「エコノミー型」の2種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットについて、表にまとめました。
| メリット | デメリット | おすすめな人 | |
|---|---|---|---|
一般型 | 補償範囲が広い | 保険料が高め |
|
エコノミー型 | 補償範囲が限定的 | 保険料が割安 |
|
「一般型」は最も手厚い補償を提供する車両保険です。衝突や接触による損害はもちろん、単独事故、いたずらや盗難、自然災害による損害まで幅広くカバーします。
新車購入直後や、車を仕事で使用する方、初心者ドライバーなど事故リスクが高い人にとっては特に心強いですね。ただし保険料は、エコノミー型よりも高額になります。
一方で「エコノミー型」は、補償範囲を絞ることで保険料を抑えられるタイプの車両保険です。主に「他の車との衝突・接触事故」に焦点を当てており、相手が特定できる事故のみをカバーします。
相手不明の当て逃げや、電柱などにぶつけた単独事故は、補償の対象外となるケースが多いです。
保険料は一般型よりも2〜3割程度安く設定される傾向があります。そのため「ある程度の補償は用意したいけど、保険料を抑えたい」という方に向いています。
中でも、運転に慣れてきた人や「相手がいる事故だけはカバーしておきたい」という人にとっては、一般型よりもコストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。
https://ins.minkabu.jp/columns/vehicle-insurance-221210
保険料の支払い方法を決める
自動車保険を契約する際、見落としがちなのが「支払い方法」。一見些細なポイントだと思えるかもしれませんが、実は支払い方法によって年間保険料が変わるんです。
自動車保険の支払い方法には「一括払い」と「分割払い(主に月払い)」の2種類があります。
分割で保険料支払う場合、保険会社は分割手数料を上乗せします。例えば、年間保険料が10万円の場合、分割払いにすると総額で10万5千円から11万円程度になる場合があります。
一括払いならそのような分割手数料が不要です。そのため年間保険料の支払額は、一括払いのほうが少なくなります。
しかし、一括払いをするにはまとまった資金が必要です。特に車を新たに購入した直後は、車両本体の支払いや登録諸費用、車検費用など、出費が重なりがち。そこに加えて自動車保険の一括払いとなると、一時的な家計の負担が大きくなってしまいます。
無理に一括払いを選んで生活資金が圧迫されるようでは本末転倒です。10万円程度の保険料を一気に支払うのが難しい場合は、無理せず分割払いにしましょう。
https://ins.minkabu.jp/columns/monthly-payment-221201
保険会社ごとの割引制度をチェックする
忘れてはいけないのが、各保険会社が用意している独自の割引制度です。上手に活用すれば、効果的に保険料を削減できます。
割引制度は多岐にわたります。代表的なものを以下にまとめました。
インターネット申込割引
早期契約割引
ゴールド免許割引
新車割引
EV・エコカー割引
セカンドカー割引
割引制度はまさに「知っているか知らないか」で保険料に差が生まれるポイントです。
ただし、各保険会社の割引制度を個別に調査し、比較検討するのは非常に骨の折れる作業です。各社のウェブサイトを一つひとつ確認し、適用条件や割引率を調べるだけでも膨大な時間がかかってしまうでしょう。
そのため、複数の保険会社の見積もりを一度に取得できる「一括見積もりサービス」を活用するのがおすすめです。
一括見積もりを活用すればベストなプランをスムーズに選べる

同じ車種、同様の補償内容でも、保険料は保険会社により異なります。そのため、一社だけの見積もりで契約を決めてしまうと「実は他社ならもっと安く、さらに充実した補償が受けられた」というケースに直面してしまうことも。
自動車保険を賢く選ぶためには、複数社の見積もり比較が必須です。
とはいえ、たくさんの保険会社の補償内容をチェックして、それぞれ見積もりを依頼し……と進めていては、膨大な時間がかかってしまいます。すべての保険会社の補償内容や保険料を頭に入れるのは、非常に難しいですよね。
みんかぶ保険の一括見積もりサービスを利用すれば、一度入力するだけで複数社の見積もりを同時に取得できます。保険料の違いだけでなく、事故対応の質や特約の種類、割引制度の充実度などを総合的に比較することも可能です。
さらにみんかぶ保険なら、専門スタッフによる無料相談サービスもご利用いただけます。
保険料の比較はもちろん重要ですが、初めて自動車保険に加入する方にとっては「どのような補償内容を選べばよいのか」という悩みも大きいはず。
「この補償は必要?」「この特約は外しても大丈夫?」といった質問に対しても、保険のプロがわかりやすく回答します。無料相談は、何度でも利用可能です。保険料だけでなく補償内容についても、納得感のある選択ができるでしょう。
初めての自動車保険は納車日までに加入しておこう

自動車保険はいつまでに加入すべきなのでしょうか?結論から言えば、車を公道で走らせる予定の日(通常は納車日)までに必ず加入を完了させておく必要があります。
法的には、強制保険である自賠責保険のみでも加入しておけば、車を運転できます。
ただし自賠責保険だけでは補償範囲が極めて限定的です。万が一の事故で相手に大きな損害を与えてしまった場合、数千万円〜数億円単位の賠償金を自己負担することになるリスクもあります。
そのため、任意保険の加入手続きは早めに済ませておきましょう。具体的には、納車日の2〜3週間前から手続きを始めるのが理想的です。
多くの保険会社では「早期契約割引」を設けており、保険始期日(補償開始日)より一定期間前に契約すると保険料が割引されることもあります。余裕を持って準備しておけば、そのような割引制度も活用できそうですね。
自動車保険の加入方法
代理店型の場合は、保険代理店やディーラー、保険会社の営業所などで、担当者と対面しながら契約手続きを進めます。保険の知識が乏しい初心者でも、プロの担当者がサポートしてくれるため安心感がありますね。
一方、ネット型なら保険会社の公式サイトや比較サイトを通じて、インターネットや電話で直接契約できます。24時間いつでも申し込みができ、自分のペースで手続きできる点が魅力です。
オンラインでの手続きなら「インターネット申込割引」などの特典が適用されることも多いです。
代理店型でもネット型でも、手続きの大まかなステップは同じです。
保険会社に申し込む
必要書類を揃えて提出
保険会社による審査を受ける
保険期間スタート
手続きをスタートしたら、提出書類について保険会社から案内されます。細かな必要書類については保険会社ごとに異なりますが、以下の書類をあらかじめ用意しておくとスムーズです。
車検証
運転免許証
(既に他社の自動車保険に加入している場合は)現在の保険証券
新車購入時は、車検証が納車直前にならないと発行されないケースもあります。その場合はディーラーから必要な情報を事前に入手できることが多いです。
保険の補償開始日(保険始期日)を設定する際は、必ず納車日に合わせましょう。また書類に不備があると手続き完了が遅れてしまいます。ミスしないよう、手続きは丁寧に進めましょう。
【Q&A】初めての自動車保険でよくある質問
Q1. 18歳の保険料はどれくらい?
18歳の若年ドライバーが自動車保険に加入する場合、保険料は他の年齢層よりも高額になる傾向があります。まだ免許を取得したばかりの若年層は、事故リスクが高いと判断されるからです。
18〜20歳で月払いを選択した人の相場は以下のとおりです。

18歳の場合、年間15万円程度かかることも珍しくありません。中型車や大型車になるとさらに高額になり、20万円を超えることもあります。
具体的な保険料は車種、居住地域、走行距離などによっても変動しますが、いずれにしても若年ドライバーの保険料負担は決して軽くはないのが現状です。
高額な保険料を少しでも抑える方法として、親の自動車保険を活用する方法があります。もし親が既に自動車保険に加入しており、ある程度高い等級(例えば10等級以上)を持っているなら、新車を購入する際に7等級からスタートできる可能性があります。
また、親の車を共同で使用するのであれば、親の契約に「家族限定」「年齢条件18歳以上補償」などの設定をすることで、若年ドライバー単独で加入するよりも保険料を抑えられることがあります。
いずれにしても、18歳の保険料は高額になりがち。複数の保険会社から見積もりを取り、最も条件の良い会社を選ぶのがおすすめです。また、免許取得後は安全運転を心がけ、無事故無違反で等級を上げていくことが、保険料を下げる最も確実な方法です。
Q2. 6等級の時点で事故を起こしてしまったら等級はどうなる?
自動車保険に初めて加入すると、通常は6等級からスタートします。この時点で事故を起こしてしまうと、翌年の等級は下がってしまうのが一般的です。
等級がどの程度下がるかは、事故の内容によります。
3等級ダウン事故:対人・対物事故で損害賠償が発生するケースなど
1等級ダウン事故:単独事故など
3等級ダウン事故を起こした場合、翌年の等級は3になります。保険料も大きく増加するでしょう。
ただし事故を起こしても、自動車保険を使わなければ等級に影響はありません。自動車保険を使わずに済むほど軽微な事故であれば、補償金を受け取らないのもひとつの手です。
Q3. 子どもが免許を取って親の車に乗る場合の自動車保険はどうしたらいい?
子どもが新たに運転免許を取得し、親の車に乗るようになった場合、現在の自動車保険契約を見直す必要があります。
特に注目すべきは「運転者限定特約」と「運転者年齢条件」の2つです。
保険料を抑えるために「本人・配偶者限定」や「35歳以上限定」などの条件を付けている人も多いです。しかしその場合、新たに免許を取得した子どもは補償の対象外となってしまいます。
もし子どもが補償対象外の状態で事故を起こした場合、補償金は一切支払われません。
親の車を子どもがたまに運転する場合は「運転者限定特約」を「家族限定」または「限定なし」に変更し「運転者年齢条件」も子どもの年齢をカバーするように設定し直しておきましょう。
一方、親から子どもに車を譲り渡したり、実質的に子どもが主に使用する車になったりするケースもあるでしょう。その場合は、以下2つの選択肢があります。
親が契約者のままで記名被保険者(主に運転する人)を子どもに変更する
子どもが新たに契約者となって自動車保険に加入する
親の契約を引き継ぐ場合、親が積み上げてきた等級を子どもに引き継ぐことができる場合があります。保険会社によって条件が異なりますが、一般的に親と子が同居している場合に適用できるケースが多いです。
一方、子どもが新規で契約する場合は原則として6等級からのスタートになりますが、条件を満たせば「複数所有新規契約特則(セカンドカー割引)」を適用して7等級からスタートできる可能性もあります。
まとめ
初めて自動車保険に加入する場合、おそらく「何から考えればいいのか」がわからない人も多いはず。まずは任意保険の役割を明確にしておくと、補償内容も選びやすくなるはずです。
また同様の補償内容でも、いくつかの条件や契約方法を変えるだけで保険料も変わってしまいます。この記事でご紹介したポイントをしっかり抑えて、ベストな自動車保険を選びましょう。
「どの保険会社を選べばいいかわからない」と感じる場合は、ランキングから選んでみるのもひとつの手です。みんかぶ保険ではさまざまな自動車保険をご紹介しているため、ぜひチェックしてみてください。