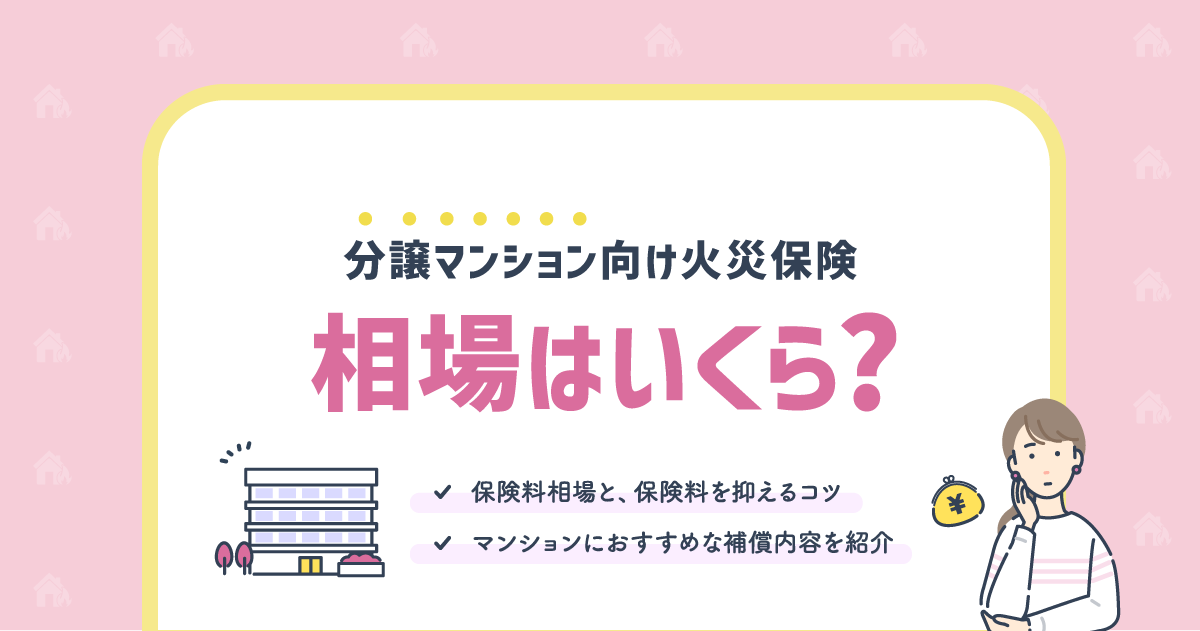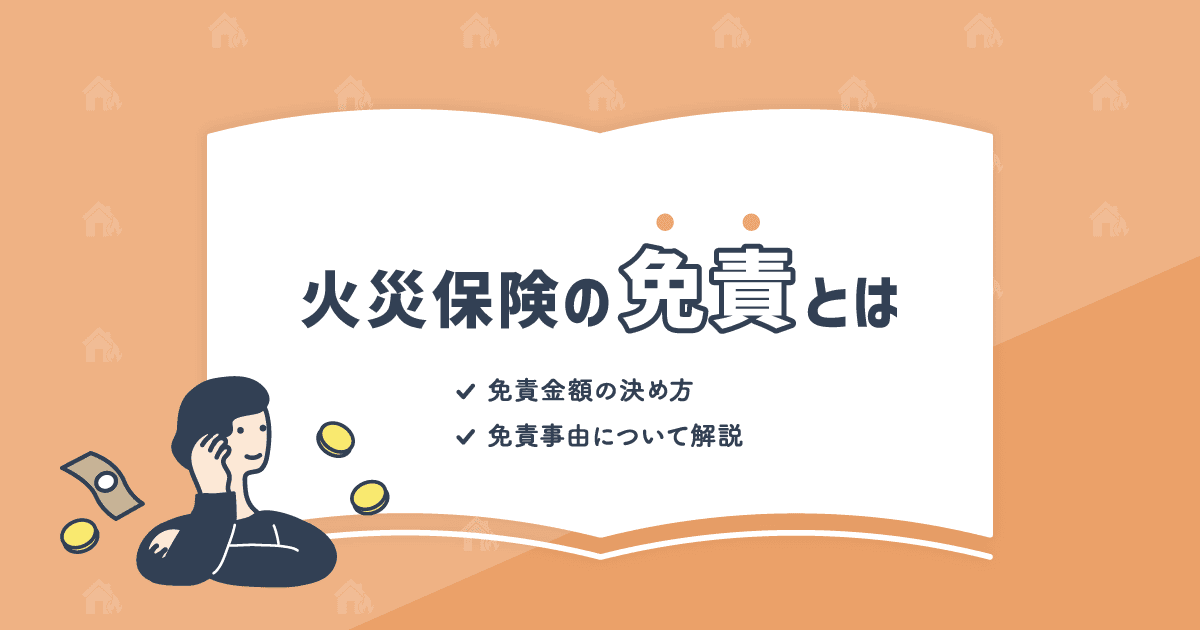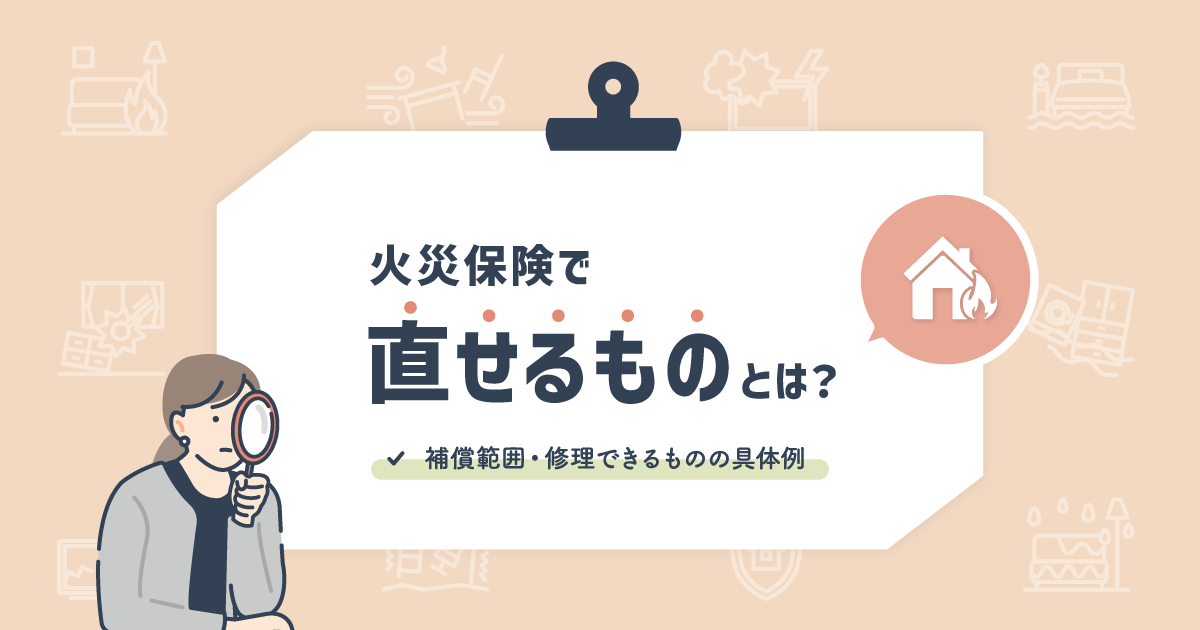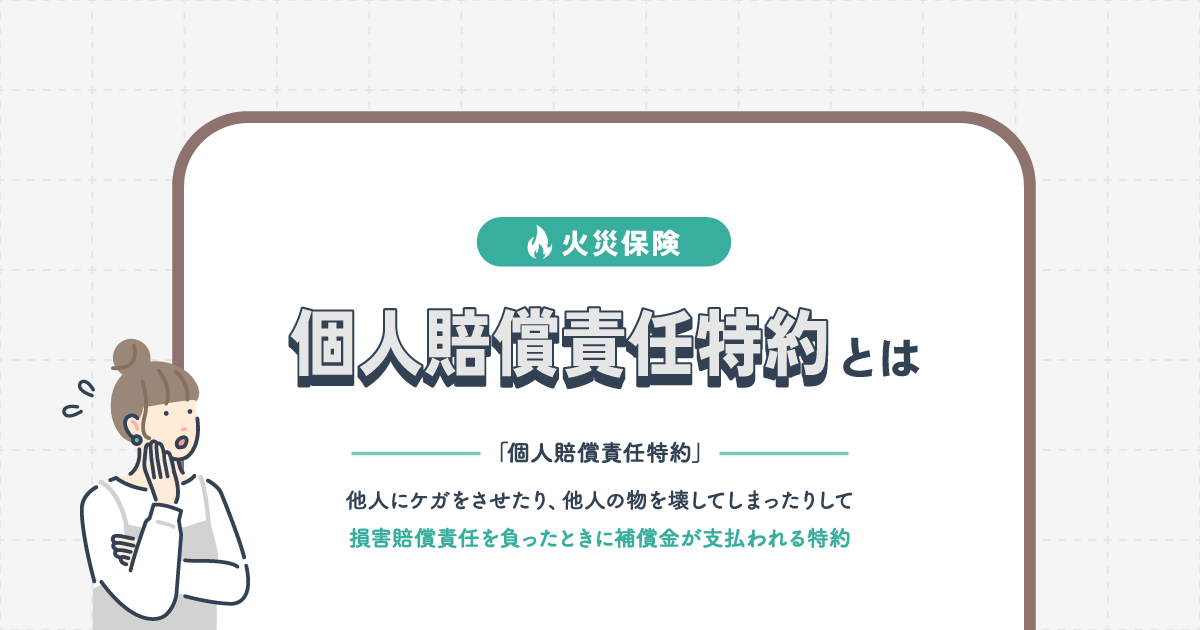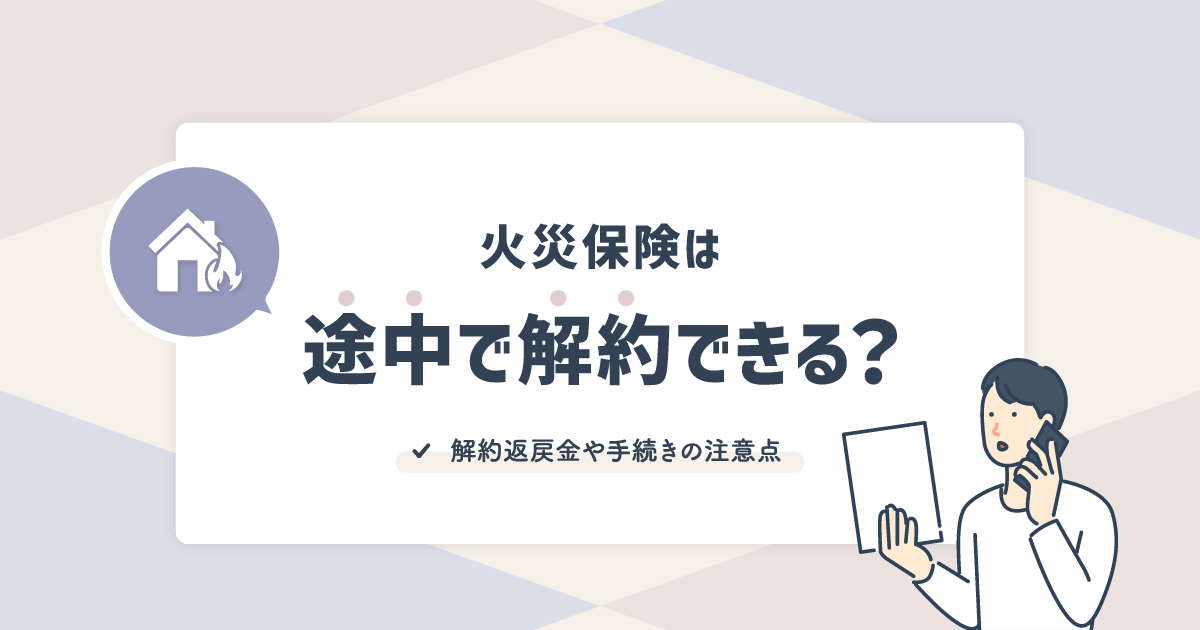こうした疑問を解決するため、この記事では分譲マンションの火災保険の相場はいくらくらいなのか、どんな点に気をつけて保険選びをすればよいのか解説します。
- 分譲マンションの保険料相場は、1万5千円〜4万円程度(延床面積・構造により変動)
- 火災保険選びの際は「共有部と専有部」がどう分かれているか確認することが重要
- マンションの場合は「個人賠償責任保険」「水漏れ・水災補償」をつけるのがおすすめ
- 保険会社によっては長期契約・一括払い等により保険料を抑えられる場合も
という方は以下の無料相談から始めるのがおすすめです。
分譲マンション向け火災保険の相場はいくらくらい?
まずは、具体的な保険料がイメージしやすいように、分譲マンションの保険料例を3つ紹介します。
広さの異なる3つのパターンでシミュレーションした結果、保険料相場※は1.5万円〜4万円/年程度ということがわかりました。
※地震保険を付けた場合
※保険料相場については下記見積条件にてみんかぶで取り扱いのある火災保険4社の保険料例をもとに掲載しております。
見積もり条件① 専有面積:50㎡
<条件>
THE すまいの保険(個人用火災総合保険)
・建物所在地:東京都
・建築年月:2025/01
・補償開始日:2025/9/1
・建物:共同住宅
・構造:M構造
・専有面積:50㎡
・建物保険金額:1,000万円(地震保険金額:500万円)
・家財保険金額:0円
・水災等地:1
<基本補償>
・火災、落雷、破裂、爆発
・風災、雹災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)
・自己負担額 0円(一部の補償は自己負担額が5万円となる場合があります。)
・臨時費用保険金 なし
<特約>
・住宅修理トラブル弁護士費用特約:300万円
・地震火災費用保険金
・凍結水道管修理費用保険金
<その他特約・割増引>
・建てかえ費用特約
・建築年数割引
※地震保険加入
| 保険期間 | 保険料/一括払い |
|---|---|
1年 | 17,090円 |
5年 | 80,860円 |
見積もり条件② 専有面積:70㎡
<条件>
THE すまいの保険(個人用火災総合保険)
・建物所在地:東京都
・建築年月:2025/01
・補償開始日:2025/9/1
・建物:共同住宅
・構造:M構造
・専有面積:70㎡
・建物保険金額:1,500万円(地震保険金額:750万円)
・家財保険金額:0円
・水災等地:1
<基本補償>
・火災、落雷、破裂、爆発
・風災、雹災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)
・自己負担額 0円(一部の補償は自己負担額が5万円となる場合があります。)
・臨時費用保険金 なし
<特約>
・住宅修理トラブル弁護士費用特約:300万円
・地震火災費用保険金
・凍結水道管修理費用保険金
<その他特約・割増引>
・建てかえ費用特約
・建築年数割引
※地震保険加入
| 保険期間 | 保険料/一括払い |
|---|---|
1年 | 25,580円 |
5年 | 121,020円 |
見積もり条件③ 専有面積:100㎡
<条件>
THE すまいの保険(個人用火災総合保険)
・建物所在地:東京都
・建築年月:2025/01
・補償開始日:2025/9/1
・建物:共同住宅
・構造:M構造
・専有面積:100㎡
・建物保険金額:2,000万円(地震保険金額:1,000万円)
・家財保険金額:0円
・水災等地:1
<基本補償>
・火災、落雷、破裂、爆発
・風災、雹災、雪災
・水災
・建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難
・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)
・自己負担額 0円(一部の補償は自己負担額が5万円となる場合があります。)
・臨時費用保険金 なし
<特約>
・住宅修理トラブル弁護士費用特約:300万円
・地震火災費用保険金
・凍結水道管修理費用保険金
<その他特約・割増引>
・建てかえ費用特約
・建築年数割引
※地震保険加入
| 保険期間 | 保険料/一括払い |
|---|---|
1年 | 34,080円 |
5年 | 161,170円 |
分譲マンションの火災保険料の見積もり方法
保険料の相場が分かったら、実際に自分が購入したマンションの場合いくらになるのか気になりますよね。
そういうときは、無料見積もりをとることをおすすめします。見積もりをとることでより詳細な保険料がわかるだけでなく、それぞれの保険の特徴や補償を比較することができます。
そんな場合には、保険のプロからのアドバイスを受けることもできるので積極的に活用したいですね。
みんかぶ保険の見積もりの流れ
建物の構造・延床面積がわかるものを用意する(確認済書や登記簿謄本など)
必要フォームを記入する
メールまたはお電話で担当者から連絡を受け、届いた見積もり結果(保険料シミュレーション結果)を確認する
保険選びに納得がいくまで相談しながら担当者のサポートを受ける
分譲マンションに火災保険は必要?いらない?

結論、分譲マンションに火災保険は必要です。
加入義務はありませんが、火災保険に入っておかないと火災や自然災害で大きな損害を受けた場合、経済的に大打撃を受けてしまう可能性があります。
最悪の場合、再建費用や修繕費用が支払えず、住まいを失ってしまう可能性も0ではありません。
持ち家の火災保険加入率は約8割※
では、分譲マンションを含む「持ち家」がある世帯の火災保険加入率はどれくらいなのでしょうか。
内閣府の調査によると、火災保険(共済等を含む)の加入率は82%と報告されています。
| 火災補償あり | 水災補償あり | 地震補償あり |
|---|---|---|
2,880万件(82%) | 2,307万件(66%) | 1,732万件(49%) |
また、水災補償をつけている世帯も6割強となっており、台風や豪雨災害への備えをしている世帯が多いことが伺えますね。
※損害保険料率算出機構資料(2015年度末における全保険会社の建物(住宅)を対象とした火災保険保有契約を集計)及び日本共済協会資料(2015年度末におけるJA共済連、JF共水連、全労済、全国生協連の建物(住宅)を対象とした共済保有契約を集計。住宅のみのデータ抽出が困難なものを除く)をもとに、内閣府が試算したデータです。
分譲マンションで火災保険に入らないデメリットとは
もし、分譲マンションで火災保険に入らない場合、どんなデメリット・リスクが考えられるでしょうか?
主な3つのデメリット
高額な修理費用が発生する可能性がある
火災による建物の焼損だけでなく、水漏れによる内装の損傷など、修理費用は数百万…場合によっては数千万円単位になることもあります。
生活再建が困難になる可能性がある
住まいを失うと、仮住まいの費用や新しい住まいの購入費用など、多額の費用がかかります。
また、家財道具の買い替えも必要となり、生活再建が困難になる可能性があります。
ローン返済が滞る可能性がある
住宅ローンを組んでいる場合は、火災などで住宅が損傷すると、担保価値が下がり、ローン返済が滞る可能性があります。
また、住宅ローンを組む場合には、火災保険への加入を必須条件とされているケースがほとんどです。一括払いで購入するのはあまり現実的ではないため、ローンを組むという観点では、火災保険への加入は「必須」であるといえます。
ただし、火災保険への加入が必須だからといって、いい加減に保険選びをするのはNGです。自分のマンションを守るために「必要十分な」補償を揃えた保険に加入することが大切です。
次は、分譲マンションで火災保険に入る際、注意すべきポイントを一緒に確認していきましょう。
分譲マンションの場合は火災保険の補償範囲に注意しよう

分譲マンションで火災保険に入る場合には「補償範囲」に注意しなければいけません。
具体的には、自分が購入した分譲マンションの「専有部分」と「共有部分」はどう分かれているのか把握しておく必要があります。
専有部分と共有部分
マンションは個人が所有する「専有部分」とオーナー・管理組合が所有する「共有部分」に分かれています。

これは、しっかり区分所有法に記載がされています。
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
また、家財や明記物件(30万円以上の高価な貴金属・貴重品で保険加入時に記載したもの)は個人の管轄です。
ここで気をつけておきたいのが、どこまでが個人で管理しなければいけない「専有部分なのか」です。
専有部分の範囲はマンションの管理規約で定められており、上塗基準と壁芯基準のどちらか確認する必要があります。

上塗基準のほうが専有部分の面積が小さく、保険料も安くなります。
玄関ドア・窓ガラス・窓枠・バルコニーなどの扱いも要チェック
また、専有部分かどうかの判断が難しい以下の箇所のチェックも漏れなくしておきましょう。
玄関ドア
窓ガラス
窓枠
バルコニー
専有部分がどこまでなのかを明確にしておかないと、いざ火災や災害の被害を受けた際に、トラブルの原因になってしまいます。
火災保険に加入するタイミングでしっかりと「専有部分はどこまでなのか」を確認しておきましょう。
【分譲マンション向け】火災保険の選び方・保険金額の決め方

こうした要望に応えるため、ここからは「分譲マンション向けの保険の選び方」を紹介します。
もし、自分で補償をチェックしたり、保険を比較するのが面倒という場合には、一括見積もり+保険のプロに相談する方法がおすすめ。
選び方を知らなくても、保険のプロがあなたの性格・物件・家計を加味して最適なプランを提案してくれますよ。
また、みんかぶ保険の見積もりでは、保険会社から直接セールスが来ることもなく「保険のプロ」とじっくり保険選びができるのでご安心ください。
火災保険選びの6つのポイント
火災保険は、いざという時のために必ず加入しておきたい保険の一つです。
しかし、保険会社やプランがたくさんあり、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、火災保険を選ぶ際に、ぜひ知っておきたい6つのポイントを分かりやすく解説します。
1. 保険の対象を決める
まず、火災保険で何を補償したいのか、保険の対象を明確にしましょう。一般的に、火災保険の対象は「建物」と「家財」の2つに分けられます。
建物: 家の本体、門、塀、物置など、建物に固定されているものを指します。
家財: 家具、家電製品、衣類など、建物の中に置かれている動産を指します。
補足:賃貸住宅の場合は、建物は大家さんが契約していることが多く、入居者は家財のみを補償対象とするケースが一般的です。
2. 構造級別を確認する
建物の構造によって、火災保険の保険料が変わります。木造、軽量鉄骨造、RC造など、建物の構造によって構造級別が定められており、構造級別によって保険料が算出されます。
3. 補償範囲を決める
火災保険の補償範囲は、火災だけでなく、風災、水災、盗難など、様々なリスクに対応できます。どの程度の範囲まで補償したいのか、ご自身の状況に合わせて選びましょう。
火災: 火災による建物や家財の損害を補償します。
風災: 台風などの強風による損害を補償します。
水災: 洪水、高潮などによる水害を補償します。
盗難: 泥棒による家財の盗難を補償します。
破損: 不意の事故による家財の破損を補償します。
4. 保険金額を決める
保険金額は、万が一の際に受け取れる保険金の最大額です。建物や家財の再取得に必要となる金額を考え、適正な保険金額を設定しましょう。
建物: 建物を再建するために必要な費用を目安にしましょう。
家財: 家財の購入価格を合計した金額を目安にしましょう。
5. 保険期間を決める
火災保険の契約期間は、通常1年単位です。契約期間が長くなると、保険料が割安になる場合があります。
6. 地震保険への加入を検討する
地震による損害は、火災保険では補償されません。地震保険は、火災保険とは別に加入する必要があります。地震の多い地域に住んでいる場合は、地震保険への加入も検討しましょう。
より詳しい、火災保険の選び方は以下の記事で解説していますので、あわせてチェックしてみましょう。
https://ins.minkabu.jp/columns/apartment-need-fire-insurance-220908
マンションだからこそ知っておきたい補償・特約は?
マンションの場合、一戸建てと違い以下の補償・特約も検討しておきたいところ。建物の構造や立地に応じて付帯するかどうかを決めましょう。
個人賠償責任保険は、自動車保険に加入している場合には、すでに付帯されているケースもあるので、事前に確認をしておきましょう。
もし、確認をして入っていないようでしたら加入しておくことをおすすめします。
理由は、1年あたりの保険料は数千円しか変わらないのにもかかわらず、1000万円〜1億円までの補償を受けられるからです。(保険会社によって保険料・保険金額は変わります)
| 補償内容 | 補償範囲 | 具体例 |
|---|---|---|
水災 | 自然災害による水害 | 台風による洪水、高潮、土砂崩れなどにより、建物や家財が水に浸かった場合 |
水漏れ | 配管の破裂、給排水設備の故障などによる水漏れ | キッチンや浴室の配管が破裂し、部屋が水浸しになった場合 |
個人賠償責任保険 | あなたの過失により第三者にケガをさせたり、物を壊したりした場合の賠償責任 | 子供が他人の家を壊してしまった場合、ペットが人に噛みついてケガをさせてしまった場合など |
類焼損害補償特約 | あなたの建物から火災が発生し、隣家などに延焼した場合の損害 | 自宅から火が出火し、隣家の建物や家財が焼損した場合 |
https://ins.minkabu.jp/columns/water-leak-221018
分譲マンションの保険金額の決め方
マンションを購入された方の中には、
と思っている方もいるのではないでしょうか?
実は、それは少し違います。
マンションの購入価格には、建物本体の価値だけでなく、土地の値段や共用部分の費用などが含まれています。火災保険で補償するのは「あなたの住んでいる部分(専有部分)」です。そのため、購入価格をそのまま保険金額にすることは適切ではありません。
どうやって保険金額を決めるの?
一般的には、「新築費単価法」という方法を用いて算出されます。これは、あなたのマンションと同じようなタイプの建物を、今新たに建てるとしたらどれくらいの費用がかかるのかを計算する方法です。
新築費単価法では、建物の構造や築年数、そして同じ地域での建物の新築費用などを参考に、あなたのマンションの再調達価額(新たに購入し直す場合にかかる金額)を算出します。この再調達価額が、火災保険の保険金額の目安となります。
火災保険には、建物だけでなく、家具や家電製品などの家財を補償する「家財保険」も含まれます。家財保険の金額は、ご自身が所有する家財の合計金額を目安に設定します。
保険金額を決める際の注意点
- 過不足のない金額に設定する
保険金額が少なすぎると、万が一の際に十分な補償を受けられません。逆に、多すぎると保険料が無駄になる可能性があります。
- 定期的に保険金額を見直す
家財の購入やリフォームなど、住まいの状況が変わるたびに、保険金額を見直すことが大切です。
分譲マンション向けの火災保険はどこがいい?
覚えておきたい!火災保険料を抑える方法

火災保険料を抑えるためのコツは3つあります。
それぞれ「どうすれば保険料を抑えられるのか」確認しましょう。
必要な補償・不要な補償をしっかり考える
長期契約・一括払いなら総支払保険料を抑えられる
定期的な保険の見直しも保険料を抑えるのに重要!
必要な補償・不要な補償をしっかり考える
火災保険には、火災だけでなく、風災、水災、盗難など、様々な補償が用意されています。しかし、全ての補償が必要とは限りません。
ご自身のライフスタイルや住んでいる地域の災害リスクなどを考慮し、本当に必要な補償だけを選びましょう。
例えば、河川近くに住んでいる場合は水災の補償を充実させ、雪深い地域に住んでいる場合は雪害の補償を付けるなど、地域特性に合わせた補償内容にすることで、無駄な保険料の支払いを防ぐことができます。
長期契約・一括払いなら総支払保険料を抑えられる
火災保険は、通常1年単位で契約を更新しますが、最長5年などの長期契約を結ぶと、保険料が割安になることがあります。
これは、保険会社にとって、長期的な契約の方が安定収入が見込めるため、割引という形で還元しているケースが多いからです。
また、保険料の支払い方法も、保険料を安く抑える重要なポイントになります。保険料の支払い方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
月払い
月々分割で支払う方法です。無理なく支払いができますが、他の支払い方法に比べて総支払額が多くなる傾向があります。
年払い
1年分の保険料を一括で支払う方法です。月払いに比べて総支払額を抑えられますが、まとまった金額を用意する必要があります。
一括払い
2年分、3年分、さらには5年分といった複数年分の保険料を一括で支払う方法です。一括払いにするほど、総支払額を抑えられますが、よりまとまった金額が必要となります。
年払いは、月払いと比較して事務手数料がかからないため、総支払額を抑えられます。また、保険料の支払いを忘れるリスクも減ります。
長期契約かつ一括払いにすることで、保険料を最もお得にできるケースが多いですが、一度に支払う金額が大きくなるため、ご自身の経済状況に合わせて選ぶことが大切です。
定期的な保険の見直しも保険料を抑えるのに重要!
火災保険は、ご自身のライフスタイルや財産状況の変化に合わせて、定期的に見直すことが大切です。
例えば、高価な家電製品を買い替えた場合や、リフォームをして住宅の構造が変わった場合など、見直すタイミングは様々。
保険の見直しをすることで、不要な補償を削ったり、より自分に合った保険プランに変更したりすることで、保険料を安く抑えることができますよ。
保険の見直しをするのにおすすめのタイミング
引っ越しをした時
家族構成が変わった時
高価な物を購入した時
住宅のリフォームをした時
住んでいる地域の災害リスクが変化した時(例えば、河川の整備状況が変わったなど)
まとめ
今回は、分譲マンション向けの保険料相場を紹介しました。火災保険は、大事な住まいを守るために必要な保険です。
自分が納得できる保険を見つけ、安心できる暮らしをゲットしましょう!
※記事内の保険料相場については下記見積条件にてみんかぶで取り扱いのある火災保険4社の保険料例をもとに掲載しております。
見積条件
<条件>
建物所在地:東京都、建築年月:2025/01、補償開始日:2025/1/1、建物:共同住宅、構造:M構造、専有面積:50㎡~100㎡、建物保険金額:1,000~2,000万円(地震保険金額:500~1,000万円)、家財保険金額:0円、水災等地:1
<基本補償>
火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災、水災、建物外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難、不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)、自己負担額0円(一部の補償は自己負担額が5万円となる場合があります。)、臨時費用保険金なし
<特約>
住宅修理トラブル弁護士費用特約:300万円、地震火災費用保険金、凍結水道管修理費用保険金
<その他特約・割増引>
建てかえ費用特約、建築年数割引
※地震保険加入
※この記事は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【引受保険会社】損害保険損保ジャパン株式会社
承認番号:SJ25-05755 承認日:2025/08/13