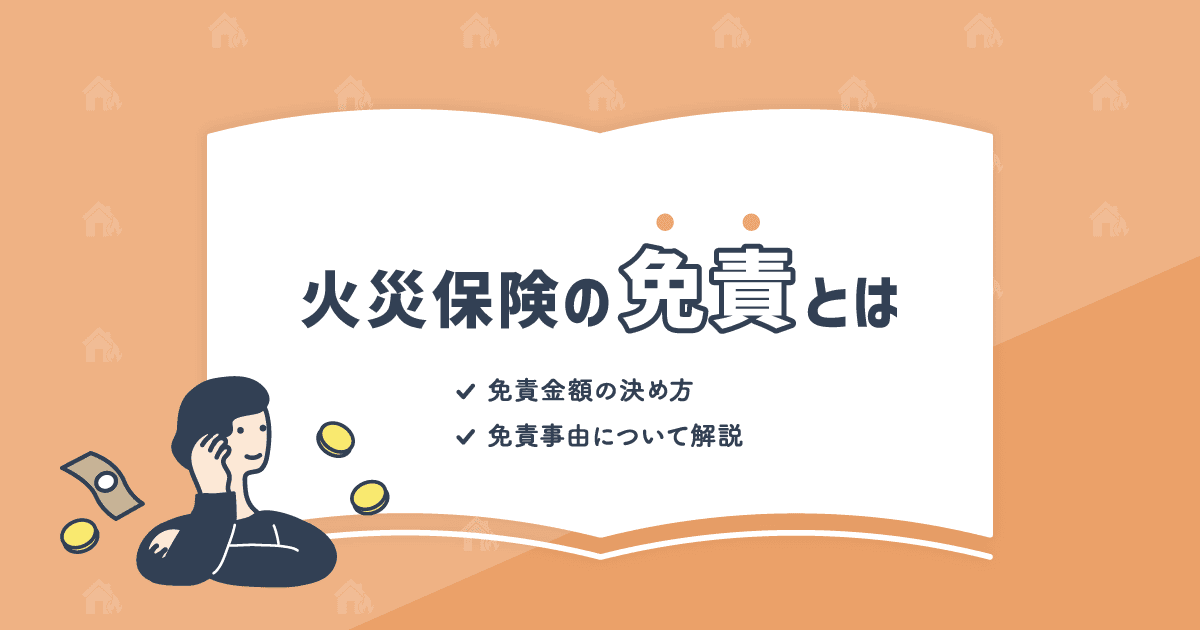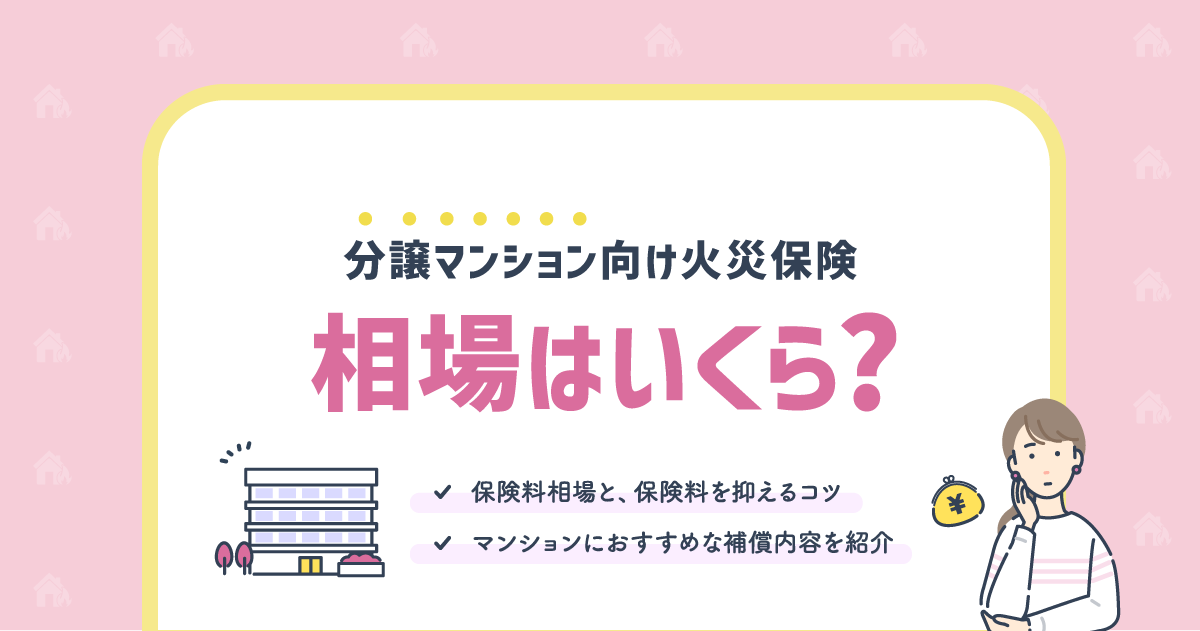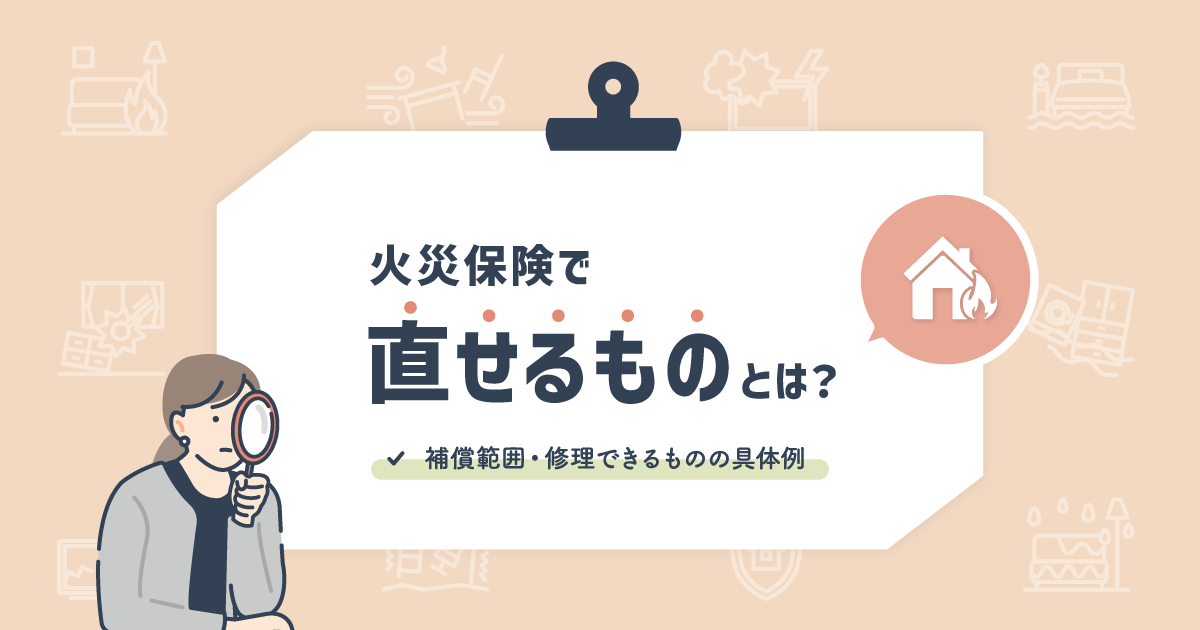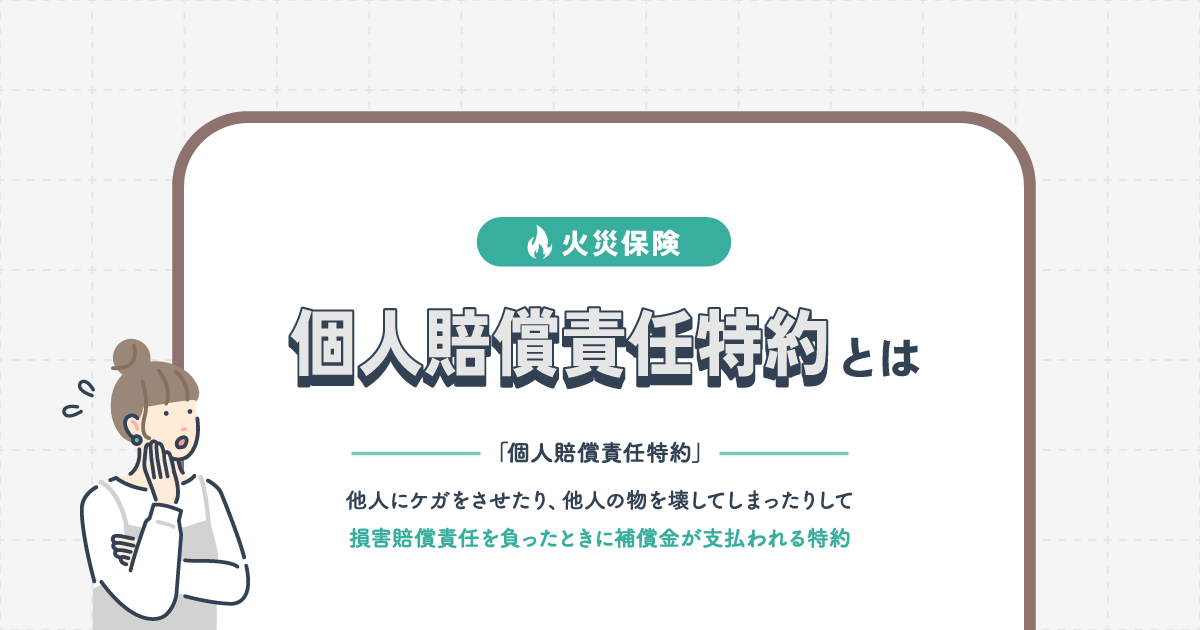生活の安心を保つために必要な「火災保険」。
住まいは「衣食住」のうちの一つで、生活に欠かせないものですからね。
とはいえ、補償を手厚くしすぎると毎月の火災保険が高くなりすぎますし、逆に補償が十分でないと、自然災害に巻き込まれてしまった時に「大損失」になる恐れがあります。
では、必要十分な補償内容で「自分に合った火災保険」はどのように選べばよいのでしょうか。この記事では「火災保険の上手な選び方」をわかりやすく解説します。
火災保険を選ぶための事前知識
火災保険の選び方について解説する前に、まずは事前に把握しておくべき項目についてご紹介していきます。
あらかじめ「火災保険に関する基礎知識」を理解しておくことで、火災保険をよりスムーズに選べるようになります。
補償対象は「建物」と「家財」
火災保険の補償対象は、「建物」と「家財」の2種類に分類できます。
「建物」は住居として利用する建築物や、住居に備え付けられているもののことです。
一方で「家財」は、住居内に収容されており、契約者やその家族が所有するものを指します。

※保険会社によって補償対象が異なるので確認が必要です
補償のタイプとしては、「建物のみ」「家財のみ」「建物・家財」の3種類から選べます。
補償対象の範囲によって、保険料の高さも変わります。最も保険料が高くなるのは、補償範囲が広い「建物・家財」です。
建物の造りによって保険料が変わる
建物がどのように作られているかによっても、保険料は変動します。

火災リスクが高い建物ほど保険料も高くなるため、火災保険に加入する際は、建物の構造を事前に確認しておきましょう。
補償内容は「基本補償」と「オプション補償(特約)」
火災保険の補償内容は「基本補償」と「オプション補償(特約)」のふたつに分けられます。
基本補償
| 基本補償 | 内容 |
|---|---|
| 火災、落雷、破裂、爆発 | 貰い火、放火、落雷、ガス漏れによる爆発等の損害を補償 |
| 風災、雹(ひょう)災、雪災 | 台風や豪雪等による損害を補償 |
| 水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水等の損害を補償 (津波によるものは含まない) |
| 落下、飛来、衝突 | 外部からの飛来物等による損害を補償 |
騒擾(じょう)、 集団行動等に伴う暴力行為 | 騒擾(じょう)や暴力行為等による損害を補償 |
| 水漏れ | 給水管等の破裂等による損害を補償 |
| 盗難 | 空き巣や盗難等による損害を補償 |
| 破損、汚損 | 偶発的に発生した損害を補償 |
オプション補償(特約)
| オプション補償(特約)等 | 内容 |
|---|---|
| 臨時費用保険金 | 火災保険金の支払いが認められた時に、保険金が上乗せで受け取れる補償 |
| 地震火災費用保険金 | 地震などによる火災で損害が一定割合になった場合、保険金が受け取れる補償 |
| 個人賠償責任特約 | 偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償 |
| 類焼損害特約 | 近隣の住宅や家財に延焼してしまった際の補償 |
| 残存物片付け費用保険金 | 損害を受けた保険の対象の残存物の片付け費用を補償 |
| 失火見舞費用保険金 | 保険の対象となる建物から火災・爆発・破裂が発生し、第三者の所有物に損害が発生した場合に、第三者に支払う損害金 |
※補償の種類や定義については、保険会社によって異なります
火災保険の補償を選ぶ際は、「基本補償」に「オプション補償(特約)」を追加していきます。
補償内容を充実させるほど、保険料は高くなっていきます。火災保険を選ぶ際は補償内容と保険料のバランスが重要です。
火災保険の選び方

火災保険を選ぶ手順【6ステップ】
- 補償対象を決める(建物・家財)
- 構造級別(建物の造り)を確認する
- 補償範囲を決める
- 【重要】建物の保険金額を決める
- 【重要】家財の保険金額を決める
- 保険の契約期間を決める
各手順で抑えておくべきポイントを、例を出しながら分かりやすく説明します。
補償対象を決める(建物・家財)
火災保険の補償対象は、建物と家財の2つが基本となります。
加入する際に補償の対象をどれにするのかを「3パターン」から選択しましょう。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財
構造や保険金額等が同条件の場合は、「3.建物と家財」の保険料が一番高くなります。補償の対象が広いほど保険料が高くなるので注意が必要です。

- 家財のうち、どうしても無くなったら困るものはあるか
- もしもの時、建物や家財を再度購入できる経済的余裕があるか
上記を考慮して決めましょう。
また、保険料の負担が大きくなりすぎないよう、事前に支払い可能な保険料を決めておくのもおすすめです。
構造級別(建物の造り)を確認する
火災保険は、建物の造り(柱等)によって「構造級別」という区分を用いて分類されます。
火災が起きた時に、燃えにくい造りの場合は保険料が安くなり、燃えやすい造りの場合は保険料が高くなります。
構造級別を判断する際は、以下の書類を確認してみましょう。
- 建物の種類…納税関係、もしくは不動産取引に関する書類
- 建物の性能…建築確認申請書やハウスメーカー、施工業者による証明書類
補償範囲を決める

補償内容には「基本補償」と「オプション補償(特約)」の2つあります。
手順としては、「基本補償」でカバーできる範囲を確認した上で「オプション補償(特約)」を選択する流れがベストとなります。
基本補償で対応できる災害・トラブルの例
- 火災
- 落雷
- 洪水
- 強風
- 水漏れ
- 盗難
- 暴力行為
オプション補償で対応できる災害・トラブルの例
- 保険金の不足
- 地震による火災
- 偶然の事故による損害賠償責任
- 近隣への延焼
- 火災による残存物の片付け費用
補償範囲を決めるコツとして「マンションなのか戸建てなのか」「河川の近くか、山の近くか、雪害が多い地域か」など、住む建物や地域のリスク度合いを把握しておくと良いでしょう。
リスクが高い地域に住んでいるのなら、自然災害の補償に手厚く加入しておくと安心です。
【重要】建物の保険金額(限度額)を決める

保険金額とは、損害が発生した際に補償される限度額のことです。
適切な評価額を設定しないと、補償が足りなかったり、保険料を多く支払うことにも繋がるので重要なポイントです。
建物の保険金額を決める際には、「新価(再調達価額)」と「時価(現在の評価額)」のうち、どちらかを基準にして保険金額を決定します。
新価
同じの建物を取得する際に必要な金額
時価
新価から、経過年数による消耗分を差し引いた金額
保険金額の基準は、現在では保険会社が予め新価で設定しているのが一般的ですが、希望すれば時価を選択することも可能です。ただし、保険金額によって支払う保険料も変化するため、保険料が高くなりすぎないよう注意しましょう。
※保険会社によっては「新価」のみで保険金額を決定する場合もあります。
どちらにすべきか迷っている方は、全損など「万が一のこと」があっても自己資金を使わずに同じ建物を取得できる「新価」を基準にするのがおすすめです。
保険金額は多すぎるのも少なすぎるのも避けたほうがお得なので、新価ちょうどに設定すると良いでしょう。
新価と時価の計算方法
以下にそれぞれの計算方法例を紹介します。
新価に基づいた保険金額の例
計算式としては「購入建物の消費税 ÷ 当時の消費税率」となります。
消費税は建物代金にかかり、土地代にはかかりません。
例
- 購入した建物の消費税が250万円
- 当時の消費税率が10%
※マンションの場合はこの金額から専有部分のみの金額を算出します。
時価に基づいた保険金額の例
計算式としては「新価で算出した保険金額 ー 経過年数分の消耗」となります。
例
- 新価で算出した保険金額は2,500万円
- 築5年
- 5年で10%(250万円分)が消耗した
保険金額を算出する際の目安として、不動産価格を確認することをおすすめします。不動産価格とは、建物や土地を売りに出す際につけられる価格のことです。
不動産価格を調べるには、固定資産税の納税通知書にある「課税明細書」を確認してください。「価格(評価額)」の欄に記載されている金額が不動産価格になるので参考になります。
火災保険 保険料の相場・見積もりをシミュレーションして比較する
【重要】家財の保険金額を決める

補償の対象に家財を含める場合には、家財の保険金額を設定しなくてはなりません。
※家財とは、家具や家電製品などの生活用の動産の事を言います。
火災保険というと建物の補償をイメージしやすいですが、合計額が意外と高くなりがちな家財の補償も大切です。
家財の合計金額例
家族構成:3名(大人2人子供1人 世帯主は30後半)
- 家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、PC、掃除機、空気清浄機 等) :210万円
- 家具(ベッド、寝具、ソファー、絨毯、タンス、テーブル、机、椅子 等):200万円
- 衣類(スーツ、コート、制服、普段着、婦人和服 等):160万円
- 身の周り品(靴、バッグ、腕時計、アクセサリー 等):220万円
- 趣味、娯楽(レジャー用品、スポーツ用品、楽器、ゲーム機、DVD 等):150万円
計 940万円
※あくまで目安となります
家財を1つを買い替えるだけではそこまで大きな金額はかかりませんが、火災などが起こり、今ある家財を全て買い替えるとなると合計金額は高くなってしまいます。
思っている以上に家財の金額は高額になってしまうということを理解しておきましょう。
家財評価表を目安にすると便利
保険会社によってはホームページ上に家財の目安一覧が載っていたり、シミュレーションができたりします。
家財の保険金額を決定する際の目安となるのでオススメです。

※保険会社によって異なります
価額が30万円以上のものは保険証券に明記しよう
家財補償を付ける際に、あらかじめ申込書に明記しておかなければ補償の対象外になるものを「明記物件」と言います。
明記物件は、1個または1組の金額が30万円以上の貴金属、宝石、書画等の事を指しますが、保険会社によって定義が異なるので、明記物件と思われるものは申込時に保険会社へ確認が必要です。
保険の契約期間を決める
保険の契約期間は、1年〜最長5年になります。契約期間が長いほど保険料は安くなり、一括払いの方がさらに安くなります。
長期契約と短期契約それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 長期契約 | ・トータルの保険料が安くなる・更新の手間が省ける ・保険料が据え置かれ、値上がりの影響が少なくなる | ・補償内容の見直し頻度が少なくなる ・物価の変動によっては保険金が足りなくなることも |
| 短期契約 | ・保障内容のチェックや見直しがしやすい ・契約内容を忘れにくい | ・長期契約よりも保険料の総額が高くなる ・毎年更新の手間がある |
※2022年10月に、保険期間の最長が10年から5年に短縮されました。
火災保険の平均相場はいくらくらい?
火災保険の相場は地域、構造、保険金額等によって異なるため、明確な平均相場というのはありません。
火災保険 保険料の相場・見積もりをシミュレーションして比較する
1年契約の保険料の目安として、以下表を参考にしてください。

※当社調べによる
火災保険選びのコツ・注意点

納得のいく火災保険選びをするには、3つのコツがあります。
- 起きやすい災害・起きづらい災害を確認する
- 契約期間が終了する / 引越しするタイミングで保険内容を見直す
- 不要な補償をつけないよう注意する
それぞれ注意点があるので合わせて記載します。
起きやすい災害・起きづらい災害を確認する
住所の名称に「川」という漢字が入っていると、水害のリスクが高いという話を一度は聞いたことがあるかもしれません。
お住まいの地域や建物によって自然災害のリスクが増減するため、地域の特性を加味して補償内容を選ぶ方法をおすすめします。
- 高層マンションであれば水害などのリスクが少なくなる
- 持ち家であれば自然災害に対しても手厚くしておいた方が安心
といった考え方は必須です。
また、お住まいの地域の水害、地盤沈下、地震のリスク度合いについてはハザードマップを確認すると把握できるので確認が必要です。
契約期間が終了する / 引越しするタイミングで保険内容を見直す
昨今、スマート家電やスマートロック(鍵)等の設備が増えていると思いますが、サイバー攻撃に備えた補償が付けられる商品もあります。
火災保険も時代のニーズにあった新商品が出てくるので、入っている保険の期間が終わった、また引っ越すタイミングでは保険の見直しを推奨します。
昔の保険のままだと、カバーされていると思っていたが補償されなかったというケースもあります。
時代に合わせた保険に加入して、万一の時でも安心して補償を受けられる状態にしておくことをおすすめします。
不要な補償をつけないよう注意する
補償は、手厚ければ手厚い方が良いというわけではありません。リスクの少ない補償を多く付けても、保険料が必要以上に大きくなってしまいます。
補償内容の取捨選択をすることで、自分にぴったりの保険に加入することができます。
また、個人賠償責任補償等の特約は、自動車保険や傷害保険で既に持っているというケースもあるので、加入する際は自身の持っている保険で加入しているかどうかの確認も必要となります。
火災保険の選び方は戸建てとマンションで異なる
ここまで火災保険の選び方について解説してきました。
ですが、戸建てとマンションとでは火災保険を選ぶステップが異なります。
| 戸建て | マンション | |
|---|---|---|
| 補償の対象を決める | ◯ 必要 | ✕ 不要 |
| 建物の造りを確認する | ◯ 必要 | ◯ 必要 |
| 補償範囲を決める | ◯ 必要 | ◯ 必要 |
| 建物の保険金額を決める | ◯ 必要 | ✕ 不要 |
| 家財の保険金額を決める | ◯ 必要 | ◯ 必要 |
| 保険期間を決める | ◯ 必要 | ◯ 必要 |
戸建てとマンションでは想定されるリスクも異なる
戸建てとマンションとでは、備えるべき災害やトラブルも異なります。
戸建てにおけるリスク
- 火災による全焼
- 洪水による浸水
- 防犯リスク
マンションにおけるリスク
- 上階からの漏水
- 停電・断水
- 洪水時のトイレづまり
戸建て・マンションそれぞれに特有なリスクを把握した上で、必要な補償を選びましょう。
地震保険には入らなくてもいい?
火災保険を検討する際は、地震保険にも加入すべきかも考える必要があります。
地震保険は単体で契約することは原則不可能であり、火災保険とセットで加入する必要があります。
また、火災保険と地震保険は「災害に対する備えについて考える」という点では共通しているため、同時に検討したほうがスムーズですね。

地震保険にも加入しておくのがおすすめ
日本に住む以上、地震保険にも加入しておくのがおすすめです。日本は地震大国でもあり、日本全土で2021年の震度1以上の地震の回数は、2,424回も発生しています。(1日当り約6.6回)
地震が多い日本に住んでいるのであれば、万が一の事態が起こった際にも金銭面と精神面での安心を得る為に、地震保険の加入をしておくのが良いでしょう。
保険料控除の対象にもなる
地震保険は「保険料控除」の対象になるので、節税効果があります。
保険料控除の対象とはならない火災保険と比べて、経済的負担が少なく済むのは嬉しいですよね。
控除額は最大で50,000円と上限が決まっております。保険料が50,000円未満の場合はの全額が控除額になります。(平成19年以降に加入した地震保険の場合)
- 年間支払い保険料が40,000円の場合 → 控除額 = 40,000円
- 年間支払い保険料が60,000円の場合 → 控除額 = 50,000円
※平成18年以前に加入した火災保険がある場合は異なります
保険料控除を受ける際の申請方法については、年末調整と確定申告によって手順が異なります。詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。
確定申告は「e-Tax」というWEBで行える方法も存在しております。分かりやすい説明付きなので、不備の心配がある方におすすめです。
火災保険選びは「一括見積もり」が便利
今回は、火災保険の上手な選び方について解説してきました。
記載したポイントを抑え、お住まいの自然災害のリスクを把握し、必要な補償を選択すると、自分のニーズにあった火災保険に加入できるでしょう。
火災保険の商品は保険会社によって特色が異なります。ニーズにあった保険を探す際には各社の見積もりを比較する必要があります。
みんかぶ保険では、火災保険の一括見積もり機能を用意しているため、面倒な手間を抑えて、適切な火災保険を効率的に見つけることができます。
住まいの安心を確保するために必要な火災保険は、自分にピッタリの保険を選びましょう。