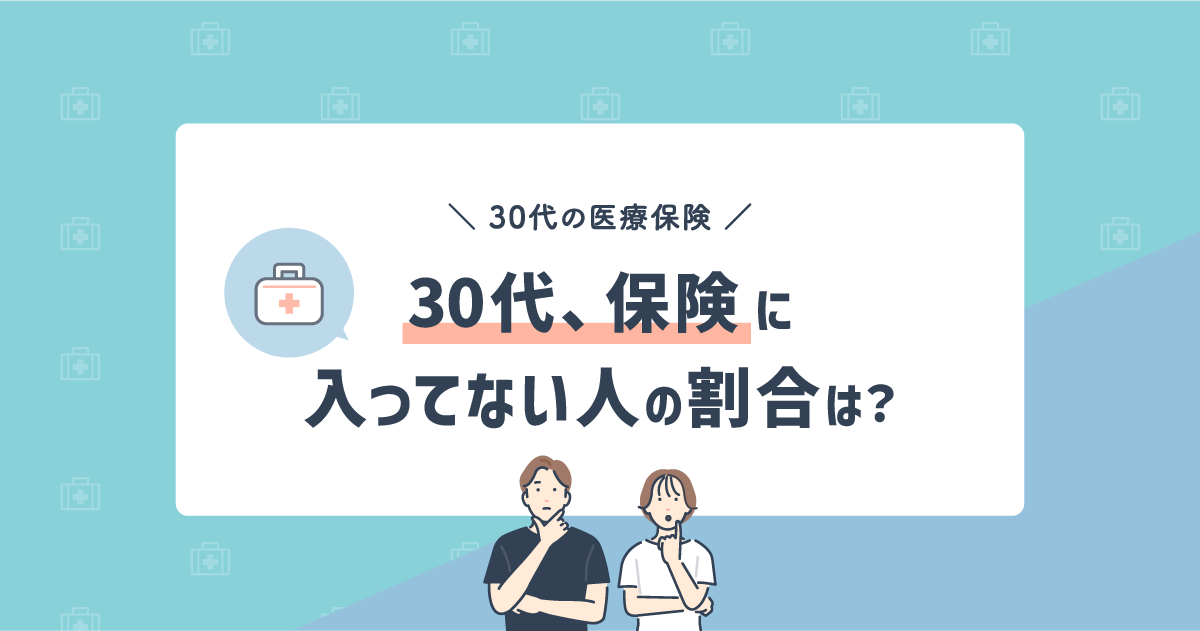こうした疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。特に定年退職をして年金暮らしになったとしたら、保険料による経済負担も無視できなくなりますからね。
この記事では、高齢者(70歳・80歳以上)に医療保険は必要なのか、それとも公的医療保険で十分なのか、その判断基準を解説します。
高齢者に医療保険が必要か判断するポイント

高齢者が医療保険に加入すべきか否かを判断するポイントは以下の2点です。
- 現在の資産・貯蓄で医療費を賄えそうかどうか
- 自身の持病や遺伝的な病気のリスク(がん家系など)があるか
もし、十分な貯蓄があり、病気にかかったとしても自分でカバーできそうであれば無理に民間の医療保険に加入する必要はありません。なぜなら後述する「公的医療保険」である程度の医療費はカバーができるからです。
ただし、自身の健康状態に不安がある、貯蓄だけだと先進医療や入院(個室希望やベッド差額)に対応できないという場合には、医療保険へ加入したままにしておいたほうが賢明といえるでしょう。
ちなみに、高齢になってから保険に加入しようとするのはおすすめしません。保険料も高くなってしまいますし、健康状態によっては加入を断られてしまうこともあります。
ですから、保険は必要になってからではなく「必要になる前」に備えておく意識を持ちましょう。
民間の医療保険に加入することでカバーできる医療費
では、医療保険に加入しておくとどんな医療費をカバーできるのでしょうか。医療保険などの保障内容は、一般的に以下のようなものがあります。これらに関する医療費はカバーできると思っていいでしょう。
【医療保険などで保障される費用の例】
- 入院給付金:入院日数に応じて給付金を受け取ることができます。
- 手術給付金:手術の種類に応じて給付金を受け取ることができます。
- 通院給付金:主に入院後の通院治療を受けた場合の医療費の一部を保障します。
- 入院一時金:入院した際に一時金を受け取ることができます。
- 就業不能給付金:病気やケガで一定期間働けなくなった際に、給付金を受け取ることができます。
- 先進医療費用:先進医療が保障内容に入っていれば治療にかかった費用を受け取ることができます。
このほかにも、保険商品によって保障される費用・されない費用が異なりますので、加入する際は必ず商品説明をしっかり読み込むようにしましょう。
高齢者が病気(がんや脳血管疾患)に罹患してしまう割合
ところで、高齢者=病気リスクが高いというイメージがあると思いますが、実際にどれくらいの割合で「重大な病気」に罹患するおそれがあるのでしょうか。
多くの人がかかりやすく、入院や手術といった大がかりな治療が必要になる「がん」と「脳血管疾患」を例に、高齢者の病気リスクについて確認しておきましょう。
まずは「がん」についてです。2019年に厚生労働省が公表した「全国がん登録 罹患数・率 報告」によると、10万人あたりにおけるがん罹患者数の年代別推移は以下のとおりです。

| 年代 | 10万人あたりの人数 | 患者数に占める年代ごとの割合 |
|---|---|---|
| 40代 | 183.15 | 1.30% |
| 50代 | 591.4 | 4.19% |
| 60代 | 1769.75 | 12.55% |
| 70代 | 3332.75 | 23.64% |
| 80代 | 4139.4 | 29.36% |
| 90代以降 | 4082.05 | 28.95% |

| 年代 | 罹患数 | 全体数に対する年代ごとの割合 |
|---|---|---|
| 総数 | 945,055 | |
| 40〜44歳 | 17,860 | 1.89% |
| 45〜49歳 | 31,042 | 3.28% |
| 50〜54歳 | 38,086 | 4.03% |
| 55〜59歳 | 49,965 | 5.29% |
| 60〜64歳 | 70,370 | 7.45% |
| 65〜69歳 | 113,267 | 11.99% |
| 70〜74歳 | 167,206 | 17.69% |
| 75〜79歳 | 15,878 | 16.80% |
| 80〜84歳 | 128,758 | 13.62% |
| 85〜89歳 | 91,831 | 9.72% |
| 90〜94歳 | 43,283 | 4.58% |
60代になってから、一気にがんの患者数が増えているのがわかりますね。
次に「脳血管疾患」についても確認してみましょう。脳梗塞や脳出血など、脳の血管が詰まったり破れたりする病気をまとめて脳血管疾患として扱います。
厚生労働省が公開している「患者調査」の数値をもとに、年代ごとの患者数をグラフ化しました。

| 年代 | 年代ごとの推計患者数割合 |
|---|---|
| 35~44歳 | 1.05% |
| 45~54歳 | 4.06% |
| 55~64歳 | 7.87% |
| 65~74歳 | 19.06% |
| 75~84歳 | 31.87% |
| 85歳以上 | 35.52% |
脳血管疾患においても、60代を境に患者数が大きく増加していますね。
また年齢だけでなく、遺伝や体質、持病の有無など「病気のなりやすさ」は人によって異なるでしょう。そのため、個々人の体質に関してもしっかり考慮すべきです。
ご自身の病気リスクが高いと感じる場合、医療保険に加入しておいたほうが良さそうですね。
高齢者が利用できる公的医療保険制度は何がある?

前章でご紹介したように、高齢者になると病気リスクも大きくなることがわかります。そのため、医療費が一気に増えてしまうのでは?と心配する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのような病気リスクに合わせて、高齢者に対しては若年層よりも充実した公的医療保険制度が用意されています。慌てて医療保険を探す前に、公的医療保険で医療費はどれだけカバーできるのかをしっかり理解することが重要です。
「高齢者が利用可能な公的医療保険制度」の具体例として、次の3つが挙げられます。
- 公的医療保険制度による自己負担額の減少
- 後期高齢者医療制度
- 高額療養費制度
公的医療保険制度による自己負担額の減少
公的医療保険制度によって対象となる医療費の自己負担額は大きく抑えられますが、年代によって自己負担割合が異なります。
| 70歳~74歳 | 2割 |
| 課税所得145万円以上:3割 | |
| 70歳未満 | 3割 |
| 6歳までの未就学児は2割 |
70歳以上になると医療費の自己負担割合は2割となり、窓口で支払う金額が若年層よりも安く済むようになります。
後期高齢者医療制度
75歳以上になると、それまでの公的医療保険のかわりとして「後期高齢者医療制度」が利用できます。
後期高齢者医療制度では、所得が低い人は医療費の自己負担額がさらに低めに設定されています。そのため医療費による経済的負担がより一層軽くなりますね。
| 75歳以上 | 年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円未満):1割 |
| 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円以上520万円未満):2割 | |
| 現役並み所得者(年金収入+その他の合計所得金額が383万円以上、世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は520万円以上):3割 |
自己負担割合が小さくなるため、同じ治療を受けたとしても、若年層と比較して半分程度の医療費で済むケースも多いです。
高額療養費制度
また高齢者は「高額療養費制度」においても、70歳以上のひとは若年層よりも自己負担上限額が低めに設定されています。
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が設定された上限額を超えた場合、差額が支給される制度です。上限額以上の医療費が発生しても差額分をもらえるため、多額の医療費が必要な方でも経済的負担を抑えられます。
70歳以上の場合、上限額は以下のとおりです。

高齢者の医療費における自己負担費用は?

高齢者は手厚い公的医療保険制度が利用できるため、若い世代の人々よりも医療費の負担が小さくなることをお伝えしてきました。
「これだけ手厚い公的医療保険制度があるなら医療保険は必要ないのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし充実した公的医療保険制度があるからといって、医療保険はいらないと考えるのはまだ早いです。公的医療保険制度はすべての医療費に対して使えるわけではなく、対象外の費用は全額自己負担となります。
では、高齢者が実際に支払う医療費の金額はいくらぐらいなのでしょうか?自己負担額について、さらに詳しく確認してみましょう。
公的医療保険制度の対象外となる費用
公的医療保険制度の対象外となる費用の具体例として、以下の4つがあげられます。
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる技術料
- 入院中の自己負担費用
- 公的医療保険の対象ではない医療行為
それぞれの費用について、詳しく解説していきます。上記の費用については公的医療保険制度の対象外ではあるものの、民間の医療保険であればカバー可能です。
差額ベッド代
差額ベッド代とは、通常の大部屋での入院ではなく、少人数もしくはひとりで過ごせる個室での入院を希望する際に必要になる費用のことです。
通常、入院する際は6〜8人部屋に入ります。しかし「プライバシーを確保したい」「もっと自由に過ごしたい」という思いから、個室での入院を希望する方も多いでしょう。
差額ベッド代の料金は病院ごとに異なりますが、厚生労働省が発表した「主な選定療養に係る報告状況」によると、1日あたりの平均額は6,613円です。
差額ベッド代は公的医療保険制度の対象外であるため、全額自己負担となります。
先進医療にかかる技術料
先進医療とは、厚生労働省から認可を得ている比較的新しい治療法・技術のことです。
ある治療法が公的医療保険制度の対象となるには、効果や安全性に関する厳しい基準をクリアする必要があります。新しい治療法が出ても、公的医療保険制度の対象となるまではある程度の時間がかかってしまいます。
しかし、一定の効果が認められ、安全性もある程度の実績が得られている新しい治療法については、厚生労働省が先進医療として公開しています。
大がかりな治療も多いため、先進医療にかかる技術料は高額になるケースが多いです。先進医療の技術料も自己負担となりますが、医療保険の「先進医療特約」で備えることができます。
| 先進医療技術 | 技術料(1件当たり平均額) | 平均入院期間 | 年間実施件数 |
|---|---|---|---|
| 高周波切除器を用いた 子宮腺筋症核出術 | 301,951円 | 9.7日 | 82件 |
| 陽子線治療 | 2,692,988円 | 14.9日 | 1,293件 |
| 重粒子線治療 | 3,162,781円 | 5.3日 | 562件 |
公益財団法人 生命保険文化センター「先進医療とは?どれくらい費用がかかる?」
入院中の自己負担費用
入院中は、差額ベッド代以外にも自己負担費用が生じます。
- 日用品や衣類にかかる費用
- 新聞や雑誌といった娯楽費
- 入院中働けなくなることによる収入の減少(逸失収入)
特に、仕事を休んで入院する人は「逸失費用」に注意する必要があります。「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》」によると、1日あたりの逸失費用の平均は21,000円であり、大きな損失となる方も多いでしょう。

会社員の方であれば、入院中も一定の収入が得られる「傷病手当金」が利用できます。しかしフリーランスや自営業の方はそのような制度が使えないため、特に注意が必要です。
公的医療保険の対象ではない医療行為
ほかにも、公的医療保険の対象外となる医療行為については、治療費を自分で全額支払わなければなりません。
具体例としては、以下のようなものがあります。
- 予防注射
- 日常生活による疲労を解消するための整体治療や鍼治療
- 健康診断・人間ドック
- 美容整形
支払う金額が大きくなる可能性があるため、上記のような医療行為を受ける際は必要な費用を事前に確認しておくのがおすすめです。
年代別の平均的な医療費
では、実際に支払うことになる医療費の目安はいくらぐらいなのでしょうか?もちろん病気の種類や通院回数など、さまざまな要因によって必要な医療費は大きく異なりますが、この記事では概算結果をお伝えします。
厚生労働省が公開している「令和3(2021)年度 国民医療費の概況」をもとに、各年代の医療費総額に自己負担割合をかけ算して、各年代ごとの医療費を大まかに計算しました。

| 年代 | 自己負担割合が2割の場合の 自己負担額 | 自己負担割合が1割の場合の 自己負担額 |
| 45 ~ 64歳(※1) | ¥87,210 | ¥87,210 |
| 70 ~ 74歳(※2) | ¥126,680 | ¥126,680 |
| 75 ~ 79歳 | ¥156,920 | ¥78,460 |
| 80 ~ 84歳 | ¥183,60 | ¥91,800 |
| 85 ~ 89歳 | ¥206,900 | ¥103,450 |
| 90歳以上 | ¥226,800 | ¥113,400 |
※1 自己負担割合は3割で計算
※2 自己負担割合は2割で計算
高齢になると病気リスクが高まりますが、公的医療保険制度が手厚くなるおかげで、年間の自己負担額の変動はある程度抑えられます。
それでも、自己負担割合によっては支払額が3倍近くに増える可能性もあるため、一定の備えが必要でしょう。
高齢者は医療費による経済的負担が大きい
注意すべきなのは実際の金額だけでなく「収入に占める医療費の割合」です。
高齢者の多くは年金が主な収入になります。そのため現役世代よりも収入額が減少し、お金のやりくりが大変になる方も多いでしょう。
さらに高齢者は入院や手術が増えると考えられますが、個室入院や先進医療を希望すれば医療費も一気に膨らみます。
そのため、収入に対して医療費が占める割合が大きくなり、経済的な負担は予想よりも大きくなる可能性が高いです。お金の不安が強い方は、医療保険に加入して備えておく必要があるでしょう。
実際に医療保険に加入している高齢者はどれぐらい?
では、実際に医療保険に加入している高齢者はどれぐらいいるのでしょうか?医療保険に加入すべきか迷ってしまう方にとっては、医療保険の加入率も重要な判断材料になるでしょう。
生命保険文化センターによる「2022(令和4)年度『生活保障に関する調査』」によると、年代ごとの医療保険加入率は以下のとおりです。
| 40歳代 | 71.6 |
| 50歳代 | 75.3 |
| 60歳代 | 71.6 |
| 70歳代 | 61.5 |
生命保険文化センター「2022(令和4)年度「生活保障に関する調査」(2023年3月発行)」
定年退職後でも、多くの方が医療保険に加入していることがわかりますね。しかし細かく数値を確認してみると、50代をピークに医療保険の加入率が下がっています。
子供の独立やローンの完済など支出が減るタイミングで、医療保険を解約する人も一定数いると考えられます。やはり個々人の収入や貯蓄状況によって医療保険の必要性は変わりそうですね。
高齢者の平均的な保険料はいくら?
とはいえ、医療保険への加入を考える際に大きなハードルとなるのが「保険料」。医療保険に加入した場合、保険料の支払いが毎月必要になります。
もし保険料による負担が大きい場合、医療保険に加入するのは避けたほうが無難でしょう。では実際に、高齢者の保険料は何円くらいでしょうか?
具体的な保険料は保険会社やプランによって異なるため、具体的な金額はお伝えすることが難しいです。ただし基本的に、加入時の年齢が高いほど毎月の保険料も高くなります。
保険料による負担と保障内容を天秤にかけて、医療保険に加入すべきか考えてみましょう。
医療保険に加入すべき高齢者の特徴

これまで医療保険の加入に関するさまざまな判断材料をご紹介してきました。その内容をもとに、医療保険に加入すべき高齢者の特徴を3つご紹介します。
まだ医療保険に加入しようか悩んでいる方は、次の3点に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
- 収入額や貯蓄額に不安を感じる人
- 治療の環境や選択肢を充実させたい人
- 無理なく保険料を支払える人
収入額や貯蓄額に不安を感じる人
ご自身の収入額や貯蓄額では医療費をまかないきれないのではないかと不安に感じる方は、医療保険に加入しておきましょう。
ここまでご紹介してきたように、高齢者は医療費による経済的な負担が大きいです。そのため「自力で準備できるお金では足りないのではないか」「医療費で生活が圧迫されてしまうのではないか」と感じる方は、医療保険に入れば不安を解消できるでしょう。
治療の環境や選択肢を充実させたい人
「個室入院がしたい」「公的医療保険の対象外となる治療法も活用したい」といったように、治療環境や選択肢を充実させたい人は医療保険を活用するのがおすすめです。
快適な入院生活や新しい治療法には、多額の費用が必要になります。しかし医療保険に加入しておけば、そのようなお金もしっかり準備できるでしょう。
お金を理由に治療に制限をかけたくないと考える人は、医療保険で備えておきましょう。
無理なく保険料を支払える人
無理なく保険料が支払えるのであれば、医療保険には加入しておくのが無難でしょう。
いつどのような病気になるか、どれだけの治療が必要になるかは誰にもわかりません。「そんなに大した医療費は必要ないだろう」と思っていても、突然の病気で多額の支払いが発生する可能性も決して低くはないでしょう。
何が起こるかわからないからこそ、医療保険に加入しておけば安心ですね。ただし高齢者の保険料は高額になりやすいため、事前の確認が必須です。
また預貯金や収入に余裕があり、自力で病気に備えられる人も、無理に加入する必要はないでしょう。
医療保険には何歳まで加入できる?
医療保険には、誰でも加入できるわけではありません。加入できる年齢には一定の制限がかけられているため、早めに手続きを開始する必要があります。
一般的には「85歳」まで
加入できる年齢については各保険会社ごとに定められていますが、基本的には「85歳まで」とされていることが多いです。そのため、85歳になるまでに加入手続きを済ませておきましょう。
また加入する年齢が高いほど、保険料も高くなってしまいます。医療保険に加入しようと考えている方は、なるべく早く加入手続きを済ませておきましょう。
高齢者でも加入しやすい医療保険の種類
年齢は加入時の審査項目のひとつです。加入時の年齢が高くなるほど、加入できる可能性は下がってしまいます。
しかし医療保険のタイプによっては、加入しやすい保険商品も存在します。通常の医療保険に加入できなかった場合は、これからご紹介する2つのタイプの医療保険についても検討しましょう。
引受基準緩和型(限定告知型保険)
引受基準緩和型の医療保険とは、通常の医療保険に比べて加入基準が緩和されている保険商品のことです。審査項目が少ないため、高齢者や持病がある方でも加入しやすいのがメリットです。
その代わり、保険料は通常よりも高め。加入前に保険料の見積もりを依頼し、無理なく支払えるかを確認しておきましょう。
無選択型保険(無告知型保険)
告知内容がほぼ無く、加入基準が引受基準緩和型よりもさらに低いタイプの医療保険を「無選択型保険」といいます。引受基準緩和型よりも加入しやすいため、病気の治療が完了していない方や高齢の方でも加入できる可能性が高いでしょう。
保険料は引受基準緩和型と比較しても高額であり、持病に関して保障を受けられない期間が設定されていることがあるため、保険料や免責期間のチェックは必要不可欠ですね。
高齢者が加入する医療保険の選び方
では「医療保険に加入しよう!」と判断した場合、医療保険はどのように選ぶべきでしょうか?数多くの保険会社がさまざまなプランを用意している中、ベストな医療保険を探すのはどうも難しそうですよね。
しかし、次の2点に注目することで、自分に合った医療保険を選びやすくなります。
- 保障内容と保険料のバランスが取れている
- 保険期間が長めに設定されている
保障内容と保険料のバランスが取れている
保障内容と保険料のバランスは、医療保険を選ぶ上で最も重要な観点です。
保障内容が手厚すぎても、保険料がその分高くなるため経済的な負担が大きくなってしまいます。かといって保険料の安さばかり重視してしまうと、本来欲しかった保障が得られず後悔してしまう原因にもなります。
- 自分が欲しい保障内容はなにか
- 何円までなら無理なく保険料を支払えるか
上記2点を考えた上で、バランスの取れた医療保険を探してみましょう。
保険期間が長めに設定されている
とくに高齢者において重要なのが「保障を受けられる期間=保険期間の長さ」です。
医療保険の中には、保険期間が短めに設定されているタイプの「定期型の医療保険」があります。保険期間が終わるごとに更新することで継続して利用できますが、一定の年齢を超えると更新ができず、保障が受けられなくなってしまいます。
せっかく医療保険で老後に備えようと思っていたのに、医療保険が使えなくなってしまうのは避けたいところ。高齢者が医療保険に加入する場合は、保障が一生涯受けられる「終身型の医療保険」がおすすめです。
高齢者が医療保険に加入する際の注意点

最後に、医療保険に加入する際に気をつけておくべき点についてもご紹介します。思わぬ損失を受けてしまわないよう、事前に注意点を把握しておくのが大切ですね。
高齢者が医療保険に加入する場合は、次の3点について理解しておきましょう。
- 医療保険に加入できない可能性がある
- 年齢が高いほど保険料も高くなる
- 既往歴があっても申し込んでみる
医療保険に加入できない可能性がある
高齢者は若い世代の人と比べて、医療保険に加入できない可能性が高いです。
医療保険には、誰でも加入できるわけではありません。保険会社の審査をクリアできない場合、加入を断られてしまいます。
審査項目は保険会社ごとに異なりますが、高齢者が審査段階で断られてしまう主な要因は次の2つです。
- 年齢が高すぎる
- 過去になんらかの病気にかかっている、もしくは何らかの病気の治療中である
年齢や病気リスクが高い人は「保険金を受け取る可能性が高い」と判断されます。その場合、公平性の観点から、加入を断られてしまう事が多いです。
医療保険に入りたい場合は、健康なうちに早めに加入しておくのが重要です。
年齢が高いほど保険料も高くなる
またもし加入できたとしても、高齢者は保険料が高めに設定されます。
1人あたりに必要な保険料総額はある程度決まっているため、加入年齢が早いほど分割回数が増え、毎月の保険料は安く済みます。ただし高齢になってから加入すると、分割回数が減るため保険料が割高になりやすいです。
さらに高齢者は若い人よりも給付金を受け取る可能性が高いため、その分保険料も上乗せされてしまうケースもあります。
そのため、高齢になってから医療保険に加入する際は、無理なく保険料が支払えるかをしっかり考えましょう。
既往歴があっても申し込んでみる
先程ご紹介したように、既往歴がある人や年齢が高い人は加入できないおそれがあります。とはいえ、既往歴が年齢を理由に手続きもせずに諦めてしまうのはもったいないです。
審査基準や審査の厳しさは保険会社ごとに異なりますし、病気が完治してから一定期間が経てば医療保険にも加入しやすくなります。
また先程ご紹介したように、通常の医療保険よりも加入しやすい医療保険も存在します。「断られてしまうかもしれない」と感じる方も、まずは手続きをしてみるのがおすすめです。
まとめ
高齢になっても医療保険が必要かどうかについては、次の点をもとに考えてみましょう。
- 公的医療保険制度や自分の収入・預貯金で安心できるか
- 病気リスクが高いと感じるか
いつどのような病気になるかは誰にもわかりません。医療費に対する不安が強い方は、医療保険への加入を検討しましょう。
もし医療保険が必要かどうか判断が難しい場合は、信頼できる第三者に相談するのも手です。みんかぶ保険では、保険の専門知識を持つプロに無料で相談できます。
回数に制限はなく、しつこい営業もありません。医療保険の必要性から保険商品の選び方など、納得のいくまで質問できます。
医療保険についてお悩みの方は、ぜひお気軽に活用してみてください。