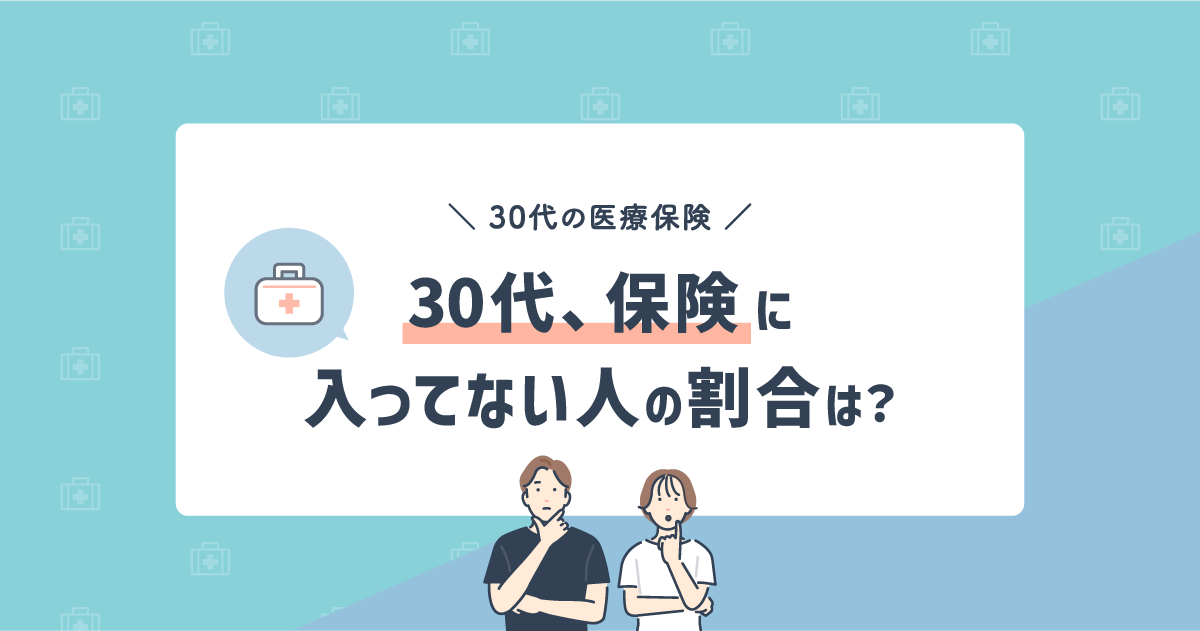手の指や足の指の関節が痛い、なんだかすぐ疲れてしまう……。「関節リウマチ」は、関節の痛みや全身の倦怠感といった症状が特徴的な病気です。
関節リウマチの治療は時間がかかるケースも多いです。そのため、
といった疑問を抱える方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、関節リウマチになった人でも保険に入れるかについてわかりやすく解説します。関節リウマチの治療費を抑える方法についても解説していくので、出費を少しでも減らしたい方はそちらもチェックしてみてください。
関節リウマチでも保険に入れる?

結論から申し上げると、関節リウマチになってから保険に加入するのは難しいです。
とはいえ、そもそも関節リウマチの症状や治療費について、まだ良くわからない方も多いでしょう。もし公的医療保険が適用されるのであれば、治療費の自己負担額も大きく軽減できそうですね。
まずは関節リウマチがどのような病気なのか、なぜ発症してから保険に加入しづらいのかについて解説していきます。
関節リウマチとは?保険適用はされる?
関節リウマチは公的医療保険の対象です。そのため自己負担額が抑えられるだけでなく、高額療養費制度が利用できます。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一種で、30代から50代の女性に多く見られる病気です。症状の例としては以下のようなものがあります。
手のこわばり
関節の腫れ・痛み
微熱
倦怠感
関節リウマチを放置すると、関節の破壊が進行し、日常生活に支障をきたす可能性があります。さらに重症化すると心臓疾患や胃潰瘍、骨粗しょう症など様々な合併症のリスクも高まるため、なるべく早めに治療すべき病気です。
ただし治療の目標は完治ではなく、症状を軽減・消失させて安定した状態(寛解状態)を保つことです。薬物療法やリハビリテーション、手術などによる治療が一般的です。
さらに内蔵や血管にまで症状が広がる「悪性関節リウマチ」は国の指定難病と認定されています。そのため通常の公的制度に加え、追加の助成制度が利用可能です。
関節リウマチは治療が長期化しやすく通常の医療保険には入りづらい
関節リウマチは長期的な治療が必要であり、かつ完治が難しい自己免疫疾患です。そのため、発症してから一般的な医療保険に入るのは難しいでしょう。
関節リウマチ患者は入院や手術のリスクが高いため、健康な人を対象とした保険に入るのは難しいのが現状です。
もし入院や手術の可能性が高い人がたくさん加入してしまうと、保険会社が保険金を支払いきれなくなってしまいます。その場合、健康な人の保険料まで値上げしなければならず、不公平が生じてしまいます。
そのため、関節リウマチを発症してから一般的な医療保険に加入するのは厳しいでしょう。しかし関節リウマチになってからでも、加入できる保険はあります。次の章で詳しく確認していきましょう。
関節リウマチで保険加入を断られてしまった場合に考えたい4つの対処法

保険に加入する前に関節リウマチになってからでも、対処法はいくつか残されています。もし一般的な保険に加入できない場合、次の4つの方法を実践してみましょう。
引受基準緩和型保険に加入申込をする
無選択型保険に加入申込をする
高額療養費制度を活用して自己負担額を減らす
医療費控除を活用する
関節リウマチになってからでも、加入できる保険や利用できる公的制度は残されています。詳しくチェックしてみましょう。
引受基準緩和型保険に加入申込をする
もし一般的な保険に入れない場合、引受基準緩和型保険を選ぶのがおすすめです。
引受基準緩和型保険は、持病や既往症がある人でも加入しやすい保険です。告知項目が簡素化されているため、通常の医療保険よりも加入のハードルが低めに設定されています。
審査自体がなくなるわけではありませんが、関節リウマチの症状や治療状況によっては加入できる可能性があります。
引受基準緩和型保険を選ぶ際の注意点
引受基準緩和型保険を選ぶ際は、いくつかの注意点があります。
まず、保険料が通常の医療保険よりも高めに設定されていることに注意が必要です。無理なく保険料を支払えるか、加入前に必ず確認しましょう。
また加入してから一定期間は、保険金が支払われない「削減期間」が設けられています。加えて、保障の対象となる病気や保険金額に制限がかかるケースも。
具体的な削減期間や保障内容は保険商品によって異なるため、加入時に忘れずにチェックしましょう。
無選択型保険に加入申込をする
引受基準緩和型保険にも加入できなかった場合、無選択型保険なら加入できる可能性が残されています。
無選択型保険とは、加入前に健康状態を告知する必要がないタイプの保険です。持病や既往歴に関係なく、誰でも加入できます。
そのため、関節リウマチを発症し治療が落ち着いていない段階でも、無選択型保険なら加入できるでしょう。
無選択型保険を選ぶ際の注意点
無選択型保険は誰でも加入できる分、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高です。また保障内容も引受基準緩和型保険や一般的な保険と比べて限定的なケースが多いでしょう。
加入してから一定期間は、保険金が支払われない「免責期間」が設けられています。事前に免責期間について必ず確認しましょう。また問題なく保険料を支払う経済的余裕があるか、きちんとチェックするのも大切です。
もし関節リウマチと診断されても、まずは通常の医療保険や生命保険で加入手続きをしてみるのがおすすめです。加入が難しい場合は、次のステップとして引受基準緩和型保険を検討してみましょう。
もしそれでも加入できない場合は無選択型保険を選びましょう。その際も、保障内容や保険料などを十分に吟味することが大切です。
高額療養費制度を活用して自己負担額を減らす
関節リウマチは公的医療保険の対象となるため、高額療養費制度が利用できます。
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費自己負担額が「年齢や所得に応じた上限額」を超えた場合、オーバーした金額を支給する制度です。具体的な自己負担額の例は以下のとおりです。

70歳未満 |
70歳以上 |
ひとつの医療機関で支払う医療費が21,000円を超えたものが計算対象 |
すべての医療費が計算対象 |
たとえば、69歳の年収500万円の人が1か月に10万円の医療費を支払った場合、自己負担額は
80,100+(100,000円-267,000円)×1%=81,770円
となり、もらえるお金は差額の18,230円です。
ただし高額療養費制度によって受け取れるお金は、実際にもらえるまで3ヶ月程度かかります。それまで待てないという方は、無利息の「高額医療費貸付制度」の活用を検討してみましょう。高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で受け取れます。
https://ins.minkabu.jp/columns/expensive-treatment-guide-230718
医療費控除を活用する
さらに、関節リウマチの治療費は医療費控除の対象です。
医療費控除は、1年間で支払った医療費が一定の基準を超えた場合、確定申告により税金の還付を受けられる制度です。本人と生計を共にする家族の医療費を合算でき、控除額は実際に支払った医療費から「保険金などで補填される金額」と「一定の金額」を差し引いて計算します。
対象となる医療費は、診療費、入院費、薬剤費、施術費など幅広いです。しかし治療ではなく予防目的の薬剤やマッサージは対象外です。
確定申告は2月中旬~3月中旬に税務署で行い、過去5年分まで遡って申告できます。領収書やレシートの提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。
医療費控除により還付される金額は、医療費の額や所得税率などによって異なります。もし高額になりやすい関節リウマチの治療費を申請すれば、ある程度の還付が受けられるでしょう。
https://ins.minkabu.jp/columns/medical-expenses-deductible-231020
難病指定の関節リウマチの場合は難病医療費助成制度等が利用できる可能性も

関節リウマチの中でも「悪性関節リウマチ」は指定難病に認定されています。そのため「指定難病医療費助成制度」による医療費の助成を受けられます。
この制度は、難病患者の医療費負担を軽減するものです。自己負担額が上限額を超えた場合に、超過分が都道府県から支給されます。
難病医療費助成制度とは?
難病医療費助成制度は、難病患者の医療費負担を軽減するための制度です。指定難病と診断され、病状の程度が一定以上であると認められた場合、医療費の助成を受けられます。「悪性関節リウマチ」も対象疾患の一つです。
助成を受けるには、都道府県・指定都市への申請と「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付が必要です。自己負担額には上限があり、超過分は都道府県から支給されます。
自己負担額は以下のとおりです。

難病情報センター 「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
難病医療費助成制度を利用するためには、保健所にて申請が必要です。必要書類の一例を以下に示しますが、病気の種類や自治体によって必要書類が変わる可能性があります。
特定医療費の支給認定申請書
診断書(臨床調査個人票)
住民票(申請者及び申請者の世帯の構成員のうち、申請者と同一の医療保険に加入している者が確認できるものに限る。)
世帯の所得を確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書等)
保険証の写し(被保険者証・被扶養者証・組合員証などの医療保険の加入関係を示すもの)
人工呼吸器装着者であることを証明する書類
世帯内に申請者以外に特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費の支給者がいることを証明する書類
医療費について確認できる書類
同意書(医療保険の所属区分確認に必要)
関節リウマチでも入れる保険をお探しならみんかぶ保険へご相談を【無料】

関節リウマチになってからでも保険に入れるか、どのような対処法があるかについて解説してきました。
関節リウマチになってからでは、一般的な保険に加入するのは難しいです。発症する前に加入するのがベストではありますが、発症した方は引受基準緩和型保険や無選択型保険を検討してみましょう。
また関節リウマチは公的医療保険の対象です。高額療養費制度も利用できるため、治療費が気になる方は毎月の自己負担上限額をチェックしてみましょう。
とはいえ、どの保険会社を選べばいいのか、どんな基準で選ぶべきかなど、まだまだわからない点も多いでしょう。せっかく保険に入ろうと思っても、やっぱり保険選びが億劫に感じてしまいますよね。
だからこそ、難しい保険選びはプロに相談してみましょう。みんかぶ保険では、保険に関する知識を豊富に持つ専門スタッフに無料で相談できます。
回数に制限はなく、納得のいくまで何度でもご利用いただけます。「どんな保障が必要なのか」「どの保険会社が保険料は安いのか」など、自力ではわかりづらいポイントも納得のいくまで質問できます。
保険選びに悩んだら、ぜひお気軽にご利用ください。
関節リウマチと保険に関するよくある質問

生命保険に加入していますが、関節リウマチと診断されてしまいました。もし入院した場合には給付金はおりますか?
すでに保険に加入しているのであれば、関節リウマチによって給付金を受け取ることは可能です。
関節リウマチの治療費が保障の対象となるのは医療保険です。ただし一般的に、医療保険で給付金がもらえるのは入院や手術をした場合に限られます。そのため、入院や手術を伴わない治療の場合は給付金がもらえない可能性が高いでしょう。
関節リウマチの治療費が払えない場合はどうすればよいですか?
もし関節リウマチの治療費を支払う余裕がないのであれば、高額医療費貸付制度を活用しましょう。
高額療養費制度を利用する場合でも、申請から支給まで3ヶ月程度かかるケースも多いです。そのため、医療費の支払いが難しいのであれば、高額医療費貸付制度を利用するのが良いでしょう。
高額医療費貸付制度を利用すれば、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で借りられます。利用する際は、必要書類を添えて全国健康保険協会各支部や税務署にて申し込みが必要です。
貸付金の返済用のお金は高額療養費の給付金から自動的に差し引かれ、残りの金額が指定の金融機関に振り込まれる仕組みです。
申請時には以下のような書類を用意しましょう。
高額医療費貸付金貸付申込書
医療機関が発行した保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書
被保険者証又は受給資格者票(原本提示・郵送の場合は写しでよい)
高額医療費貸付金借用書
高額療養費支給申請書
保険証に加え、いくつか記入して提出しなければならない書類があります。詳しくは全国健康保険協会や住んでいる自治体の窓口に問い合わせてみましょう。