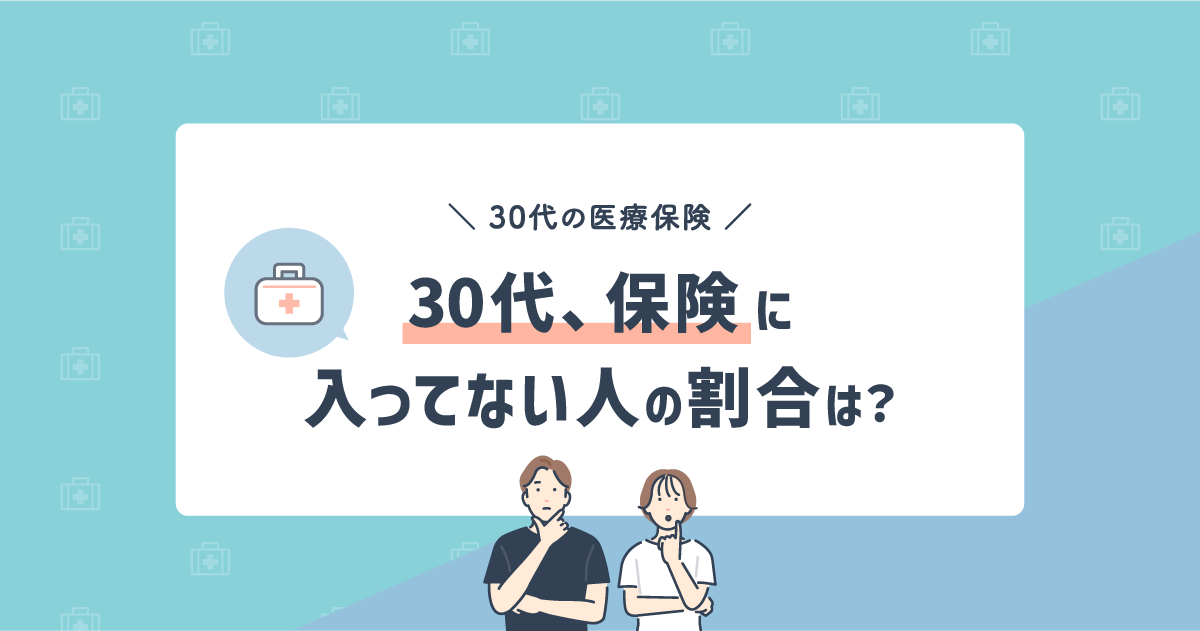引受基準緩和型保険への加入を迷っている人の中には、上記のような悩みを抱えている方もいると思います。
この記事では、引受基準緩和型保険のデメリットについて詳しく解説していきます。また引受基準緩和型保険に入らないほうが良い人の特徴についても説明します。
- 引受基準緩和型保険のデメリットは「保険料の高さ」と「支払削減期間」の2つ
- 加入する前に、保険料を無理なく支払えるかチェック
- 加入できるのであれば、無選択型保険より引受基準緩和型保険を選ぶのがおすすめ
引受基準緩和型保険のデメリットとは?

引受基準緩和型保険のデメリットは以下のとおりです。
一般的な保険よりも保険料が高い
加入してから一定期間はもらえる給付金が少ない
一般的な医療保険と異なり、保険料は高く、また保障内容も一部制限がかけられています。加入前にきちんとデメリットを把握しておかないと、思わぬ落とし穴に直面してしまうことも。
特に、保険料と家計のバランス、給付金の仕組みを理解しておかないと、せっかく保険に加入しているのに十分な保障を受けられないリスクがあります。
「加入後に後悔してしまった」というケースを避けるためにも、それぞれのデメリットについて詳しく理解していきましょう。
引受基準緩和型保険は一般的な保険よりも保険料が高い
引受基準緩和型保険の最大のデメリットは、保険料の高さです。同じ保障内容でも、通常の医療保険と比較して保険料が割高に設定されています。
そのため「保険料はなるべく抑えたい」と考えている人は注意が必要です。
保険料が割高に設定されている理由は、保険加入者の公平性を保つためです。
引受基準緩和型保険は、持病があったり病歴があったりと「健康的な人よりも病気になるリスクが高い人」も加入できます。言い換えれば「より多くの給付金を受け取る可能性が高い人」です。
医療保険に入るともらえる給付金は、加入者が負担する保険料から支払われます。そのため「たくさんの給付金を受け取る可能性が高い人」が加入する分、保険料も多めに集めなければなりません。
しかし加入者全員の保険料を高くしてしまうと、健康的な人は「他の人のためにより多くの保険料を支払う」ことになります。つまり、健康な人とそうでない人の間で不公平が生じてしまいますね。
そのため持病や病歴がある人は、健康的な人よりも保険料が高めに設定されています。
引受基準緩和型保険は加入してから一定期間はもらえる給付金が少ない
一般的な引受基準緩和型保険には「支払削減期間」が設定されています。その期間中に給付金を請求しても、50%程度のお金しかもらえません。

具体的な削減率や支払削減期間は、保険商品によって異なります。
支払削減期間が設けられている理由は、保険料と同様で「公平性を保つため」です。「給付金を受け取る可能性が高い人」も加入できる分、保障内容に制限をかけることで一部の人が給付金をもらいすぎないよう調整しています。
つまり健康的な人もそうでない人も同じぐらいの給付金がもらえるよう、支払削減期間が設けられています。
引受基準緩和型保険のメリットとデメリット比較

もちろん、引受基準緩和型保険にはメリットも存在します。
比較しやすくするために、メリットとデメリットを以下の表にまとめました。
引受基準緩和型保険のメリット | 引受基準緩和型保険のデメリット |
|
|
一般的な保険に入れない人でも入院や手術に備えられるのが最大のメリットです。また持病がある人にとっては、加入前から続いている持病も保障してもらえるのは嬉しいポイントですね。
ただし、保険料の高さはやはりネックになるでしょう。また加入してから一定期間はもらえる給付金が少なくなるため、注意が必要です。
引受基準緩和型保険に入らないほうが良い人の特徴は?

ここまでご紹介してきたメリットやデメリットを踏まえ「引受基準緩和型保険に入らないほうが良い人」の特徴についてご紹介します
一般的な医療保険に入れる可能性がある人
割高な保険料を支払う余裕がない人
引受基準緩和型保険の審査をクリアできない人
上記の特徴に当てはまる人は、引受基準緩和型保険には入らないほうが良いかもしれません。なぜそのように考えられるのか、具体的に説明していきます。
一般的な医療保険に入れる可能性がある人
もし一般的な医療保険にも入れるのであれば、わざわざ引受基準緩和型保険を選ぶ必要はないでしょう。一般的な医療保険のほうが保険料が安く、保障内容も充実しています。
持病や病歴に不安がある人でも、一般的な医療保険に加入できるかもしれません。そのためいきなり引受基準緩和型保険を選ぶのではなく、まずは一般的な医療保険で加入手続きをしてみるのがおすすめです。
割高な保険料を支払う余裕がない人
引受基準緩和型保険は保険料が割高です。そのため余裕を持って保険料を支払えないのであれば、引受基準緩和型保険に入らない方が良いしょう。
いつ病気になるかわからないからこそ、医療保険で備えておきたいと考える人も多いかもしれません。しかし、保険料のために生活費を切り詰めてしまうのは本末転倒です。生活の余裕を確保したうえで、保険に加入するのがおすすめです。
加入手続きをする前に保険会社へ見積もりを依頼し、毎月の支出額をシミュレーションしてみましょう。みんかぶ保険なら、さまざまな保険会社の見積もりを一括で依頼できます。
引受基準緩和型保険に入るのがおすすめな人は?

引受基準緩和型保険に入るのがおすすめな人の特徴は以下のとおりです。
持病や大きな病気になった経験がある人
一般的な保険の審査をクリアできなかった人
引受基準緩和型保険の保険料を支払う余裕がある人
上記に当てはまるのであれば、引受基準緩和型保険への加入を前向きに検討してみましょう。それぞれの特徴について、さらに詳しく解説していきます。
持病や大きな病気になった経験がある人
引受基準緩和型保険は「持病がある人」や「過去に大きな病気にかかったことがある人」におすすめです。
上記のような人は、一般的な医療保険では加入できない可能性が高いです。しかし引受基準緩和型保険なら、そのような人でも病気やケガに備えられるでしょう。
また引受基準緩和型保険なら、もし持病が悪化したとしても保障の対象となります。いつ悪化するかわからない持病を抱えている人にとっては心強いですね。
しかし持病や病歴があっても、一般的な保険に入れる可能性があります。まずは一般的な保険の審査を受けてみて、落ちてしまったら引受基準緩和型保険を検討しましょう。
一般的な保険の審査をクリアできなかった人
また持病や病歴以外の理由で一般的な保険の審査に落ちてしまった人も、引受基準緩和型保険で加入手続きをしてみるのがおすすめです。
一般的な保険の場合「健康診断の結果」や「職業」も審査の対象となります。しかし多くの引受基準緩和型保険では、そのような情報を告知する必要はありません。
「一般的な医療保険には入れなかったけど、やはり保険を活用して医療費に備えておきたい」と感じる人は、引受基準緩和型保険を選ぶのがおすすめです。
引受基準緩和型保険の保険料を支払う余裕がある人
引受基準緩和型保険の保険料は一般的な保険よりも割高。それでも問題なく支払える余裕があるのであれば、加入しておくのがおすすめです。
具体的な保険料は保険商品により異なります。そのため事前に見積もりを依頼することが大切です。
特に医療保険は、長期にわたって支払いが必要な商品です。「少し頑張れば大丈夫だろう」と感じる金額であっても、数ヶ月〜数十年にわたって支払いが続けば想像以上の負担になるでしょう。
生活費を削って保険料を捻出するのではなく、余剰資金で保険料を支払えるのがベストですね。
引受基準緩和型保険と無選択型保険はどちらを選ぶべき?

一般的な保険よりも加入しやすい保険として、引受基準緩和型保険のほかにも「無選択型保険」があります。
無選択型保険と引受基準緩和型保険の違いについて、混同してイメージしてしまう方も多いでしょう。しっかりと区別したうえで、どちらがベストかを判断するポイントをご紹介します。
無選択型保険とは誰でも入れる保険のこと
無選択型保険は、健康状態の告知や医師の診査が一切不要で、誰でも加入できる保険です。そのため、例えば現在入院中の人や末期がんと診断された人でも加入できます。引受基準緩和型保険よりもさらに加入しやすいですね。
しかしその分、無選択型保険の保険料は引受基準緩和型保険よりも高額です。そのため、加入する際は保険料を支払えるか、より注意深く検討する必要があるでしょう
また、保障内容が限定的であるというデメリットもあります。具体的には以下のような制限があります。
入院給付金の日額が低い(例:1日3,000円程度)
保険期間が短い(例:5年や10年など)
死亡保障がない、または少額
特約の選択肢が少ない
契約後一定期間は保険金が支払われない「免責期間」がある
このように、無選択型保険は加入のハードルは低いものの、保障内容や条件面において制限が多いです。
引受基準緩和型保険を選ぶのがおすすめな人
基本的に、加入できるのであれば引受基準緩和型保険を選ぶのがおすすめです。
引受基準緩和型保険は無選択型保険よりも保険料が低く、保障内容の制限も少ないです。引受基準緩和型保険に加入できるのであれば、わざわざ無選択型保険を選ぶメリットはほぼゼロでしょう。
引受基準緩和型保険の審査を通過できるか不安に感じる人でも、まずは加入手続きだけでもしてみるのがおすすめです。保険会社によっては引受基準緩和型保険に入れるかもしれません。
無選択型保険を選ぶのがおすすめな人
無選択型保険は「最後の選択肢」です。重い持病がある人や、現在治療中の深刻な病気がある人など、引受基準緩和型保険への加入が難しい場合は無選択型保険を選びましょう。
健康状態が非常に悪く、他の保険では断られてしまう場合でも、無選択型保険なら加入できるでしょう。
ただし、保険料が非常に高くなる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。また、保障内容も限られています。どのような保障が受けられるのか、加入時に細かくチェックしましょう。
後悔しないための引受基準緩和型保険の選び方

次のステップに沿って考えていけば、なるべく損をしない保険選びができます。
保険料の上限を決める
欲しい保障をリストアップする
保険料とのバランスを考えつつ保障内容を厳選する
保険選びにおいて最も重要なのは、保険料と保障内容のバランスです。保障内容を充実させれば安心ですが、保険料が高くなりすぎないよう注意しましょう。
保険料の上限を決める
何円までなら余裕を持って支払えるのか、あらかじめ明確にしておくのがおすすめです。
保険料の予算をぼんやりと決めるだけでは、実際に契約してから「支払が大変……」と感じてしまう可能性があります。また逆に、保障内容を絞りすぎて「支払える金額には余裕があるのに充分な保障が得られない」事態も避けたいところ。
先に保険料の上限を明確に決めておけば、保障内容と保険料の最適なバランスを見つけやすくなります。
欲しい保障をリストアップする
どんな保障があれば安心か、入院給付金は何円が理想かなど、希望する保障内容をリストアップしてみましょう。
この時点では、まだ保険料のことは厳密に考えなくても大丈夫です。自分の希望する保障内容を挙げてみましょう。
入院給付金や手術給付金の金額だけでなく、付帯したい特約もチェックしてみましょう。保険会社ごとに保障内容も異なるため、各社がアピールしている保障について確認してみるのもおすすめです。
保険料とのバランスを考えつつ保障内容を厳選する
欲しい保障内容に目星がついたら、保険料とのバランスを整えていきましょう。
希望する保障内容では保険料が高すぎる場合は、保障内容や保障額を削っていきます。優先順位が低いものから保障をカットしていき、保険料が予算内に収まるよう調整しましょう。
ただし同じような保障内容でも、保険会社によって保険料は異なります。みんかぶ保険では各保険会社の見積もりを一括で依頼できます。保険選びの手間を一気に減らせるでしょう。
まとめ
引受基準緩和型保険には、次のようなデメリットがあります。
一般的な保険よりも保険料が高い
加入してから一定期間はもらえる給付金が少ない
特に保険料に関しては、支払う余裕があるか慎重に判断しましょう。また一般的な保険の方がコスパにも優れているため、まずは一般的な保険の加入手続きをしておくのがおすすめです。
しかし引受基準緩和型保険なら、持病や病歴があっても加入できます。一般的な保険の審査を通過できなかった方でも保障を受けられるのは安心ですね。
保険選びに迷ったらプロに相談しよう

引受基準緩和型保険を選ぶ際は、保険のプロに相談するのがおすすめです。
みんかぶ保険では、保険の専門知識を豊富に持つプロに無料で相談できます。具体的には、以下のような要望や疑問にも対応可能です。
複数の保険会社の見積もりを一気に確認したい
自分にベストな保障内容を知りたい
どの保険に加入すべきかアドバイスがほしい
保険選びにおいて悩みやすいポイントについて、何回でも無料で相談できます。しつこい営業もありません。
保険選びで少しでも迷ったら、気軽にご利用ください。