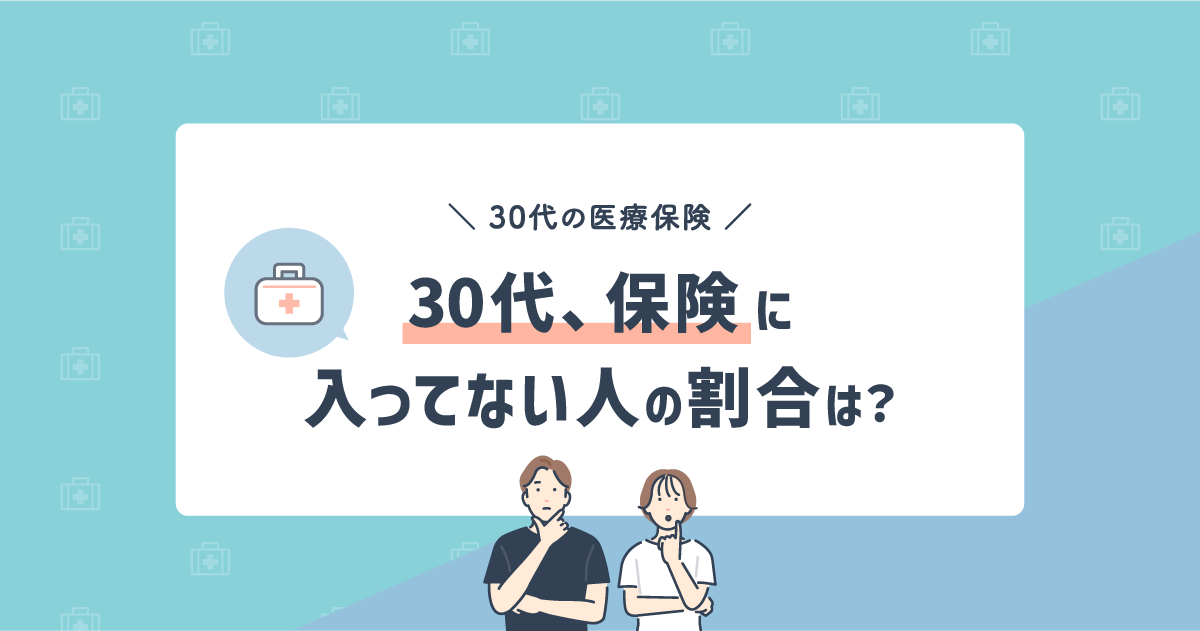病院ではなく、家で医療行為を受けることができる「訪問看護」。患者本人はもちろん、家族にとっても心強いサポートですよね。
訪問看護は、基本的には公的医療保険の対象となります。ただし、公的医療保険の対象になるためには「一定の条件や制限」があります。そのため条件を満たしていないと必要な費用がすべて自己負担となってしまうことも。
また、訪問看護は公的介護保険でも利用できます。医療保険と介護保険では対象となる人や条件が異なるため、両者の違いについても知っておく必要があるでしょう。
今回は、医療保険で訪問看護を使う条件や制限、民間の医療保険で保障されるのかどうか、わかりやすく解説していきます。
訪問看護とは?

訪問看護とは、看護師が患者さんの自宅や施設を訪問して、必要な看護を行うサービスです。主治医の指示に基づいて、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問看護で受けられるサービス内容の例
- 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
- 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
- 医師の指示による医療処置
- 医療機器の管理:在宅酸素、人工呼吸器などの管理
訪問看護を利用すれば、患者さんが住み慣れた環境で療養を続けることができ、一緒に住む家族の負担も軽減できます。
訪問介護との違い
訪問看護と訪問介護は、どちらも自宅や施設で療養を必要としている人を対象としたサービスですが、主な違いは「医療行為の有無」です。
訪問介護は、介護福祉士やヘルパーが、日常生活の支援を行うサービスです。具体的には、以下のようなものが含まれます。
訪問介護
- 食事や排泄などの介助
- 入浴や洗濯などの家事援助
- 生活リズムの調整や見守り
つまり、治療のための医療行為を行うのが訪問看護であり、日常生活をサポートするのが訪問介護となります。
訪問看護で利用できる公的保険

訪問看護は、公的医療保険と公的介護保険の対象となります。
このあと詳しく解説しますが、一定の条件を満たしていればどちらかの保険を利用することができるため、自己負担額を大きく抑えられます。
ただし、公的医療保険においては訪問看護の利用に制限が設けられており、それをオーバーする分は全額自己負担となります。
公的医療保険で訪問看護を利用する際の費用
それでは、公的医療保険で訪問看護を利用する際の費用について確認してみましょう。
まずは、訪問看護にの基本的な料金や状況に応じて加算される費用についてご紹介します。
| 費用項目 | 内容 | 費用(10割) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1日の訪問看護基本療養費(週3日目まで) | 5,550円 |
| 同一建物に居住している3人以上が同じ日に利用する場合 | 2,780円 | |
| 特定の疾病・治療に該当する人 | 8,500円 | |
| 加算料金 | 緊急訪問看護(1日) | 2,650円 |
| 長時間訪問看護 | 5,200円 | |
| 6歳未満の乳幼児に対する訪問看護(1日) | 1,500円 |
厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」
医療保険で訪問看護を利用する場合、年齢や状態に応じて自己負担割合が決められています。そのため、上記の金額から区分に応じた割引を受けられます。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 月額の2割(自己負担なしの場合も) |
| 義務教育就学後~70歳 | 月額の3割 |
| 75歳以上 | 月額の1割(現役並み所得者は3割) |
| 難病・重度心身障がい者などの公費負担 | 医療受給者証により自己負担の有無が異なる |
公的医療保険で訪問看護を利用する条件は?
簡単に訪問看護について解説してきたところで、本題の「公的医療保険で訪問看護を利用する条件」について解説していきます。
公的介護保険でも訪問看護を利用できますが、条件に違いがあります。両者を比較しながら、どんな人が利用できるか確認してみましょう。
| 公的医療保険 | 公的介護保険 | |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 医師の承認を得た方 | 利用不可 |
| 40歳以上 65歳未満 | 医師が訪問看護の必要性を承認、かつ16特定疾病の対象ではない方16特定疾病の対象であっても、要支援・要介護に該当しない方 | 16特定疾病の対象者で、要支援・要介護の認定を受けた方 |
| 65歳以上 | 医師が訪問看護の必要性を承認、かつ要支援・要介護に該当しない方 | 介護保険の要支援・要介護認定を受けた方 |
基本的には、要支援・要介護状態である方や特定の疾病にかかっている人は介護保険、そうでない人は医療保険を利用することになります。
また、表に書かれている「16特定疾病」とは以下の通りになります。
16特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
公的医療保険と公的介護保険の優先順位は?
医療保険と介護保険どちらも対象者となる場合、原則として介護保険が優先されます。そのため、要支援・要介護の認定を受けている方は、基本的に介護保険の訪問看護を利用する必要があります。
公的医療保険と公的介護保険は併用できる?
また公的医療保険と公的介護保険の両方で対象となっていても、どちらか一方の保険しか利用できません。
訪問看護を利用する際は、どちらの保険が適用されるのかを事前に確認しておきましょう。
公的医療保険で訪問看護を利用する際の制限
公的医療保険で訪問看護を利用する場合、いくつかの制限があります。
- 訪問は基本的に週3回まで
- 訪問回数は1日に1回まで(90分程度)
- 1カ所の訪問看護ステーションから看護師1人が訪問
もしこれらの制限を超えて訪問看護を利用したい場合、費用は全て自己負担となってしまいます。ですがいくつかの条件を満たせば、上記の制限が緩和されます。
制限が緩和されるケース
制限が緩和されるケースとしては、次の2つが挙げられます。
- 「特別訪問看護指示書」が出されている
- 特定の疾病や状態に該当している
それぞれについて詳しく解説していきます。
「特別訪問看護指示書」が出されている
特別訪問看護指示書を受け取っている場合、退院後14日間にわたり基本的な制限に縛られることなく訪問看護を利用することができます。
特別訪問看護指示書は、患者の状況に応じて、週4日以上の訪問看護が必要と医師が判断した場合に発行されます。
特定の疾病や状態に該当している
「別表第7」や「別表第8」の症状・状態に該当する人は、週4日以上かつ1日2~3回の難病等複数回訪問看護での利用が可能になります。


公的医療保険で訪問看護を利用する手続き
公的医療保険で訪問看護を利用するには、3つのステップが必要になります。
- 主治医に相談し訪問看護指示書を受け取る
- 訪問看護ステーションを選ぶ
- 訪問看護ステーションに連絡する
それぞれのステップについて、わかりやすく解説していきます。
主治医に相談し訪問看護指示書を受け取る
訪問看護が必要かどうかは、主治医が判断します。具体的には、以下のような状態に当てはまっている場合、訪問看護が必要だと判断されます。
- 医療保険の適用対象となる疾患や障害を有している
- 自宅にて自力で療養することが困難
- 家族や介護者が療養を継続することが困難
そのため、患者や家族の状態だけでなく、治療に関する希望についても主治医に伝えるようにしましょう。
主治医が訪問看護が必要と判断した場合、訪問看護指示書を発行します。訪問看護指示書には、以下の情報が記載されています。
- 患者の氏名・年齢・住所
- 患者の状態や治療内容
- 訪問看護の必要性
- 訪問看護の具体的な内容
訪問看護指示書は、訪問看護の利用に必要な書類です。訪問看護ステーションに申し込む際に提出しましょう。
訪問看護ステーションを選ぶ
訪問看護指示書を受け取ったら、全国に約13,000カ所ある中から利用したい訪問看護ステーションを選びましょう。
訪問看護ステーションには、大きく分けて以下の2種類があります。
- 病院や診療所が運営する訪問看護ステーション
- 単独型の訪問看護ステーション
病院や診療所が運営する訪問看護ステーションは、医療機関と連携した看護や療養を受けることが可能。単独型の訪問看護ステーションは、医療機関と連携していないケースもありますが、患者のニーズに合わせた柔軟な対応が可能な場合があります。
訪問看護ステーションを選ぶ際には、以下の点を比較しましょう。
- 職員の人数
- 訪問看護ステーションと自宅の距離
- 緊急時の対応
- 職員の言葉づかいや印象、姿勢
- 主治医との連携
訪問看護ステーションに連絡
利用したい事業所が決定したら、訪問看護ステーションに連絡し申し込みをします。
申し込みの際に必要な書類の例は、以下のようになります。
- 訪問看護指示書
- 健康保険証
- 訪問看護の申込書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 重要事項説明書
- 利用契約書
上記はあくまで例となります。必要書類は事業所によって異なりますが、「訪問看護指示書」と「健康保険証」は必ず準備しましょう。それ以外の書類については、事業所が独自のフォーマットで用意していることが多いです。
書類を用意して提出した後、訪問看護の開始日を決めます。訪問看護ステーションの都合や療養者の状態によっては、希望通りの開始日にならない場合もあります。
訪問看護は自費でも利用できる
ここまで公的医療保険で訪問看護を利用する条件や手順について解説してきましたが、訪問看護は自費で利用することもできます。
「条件にあてはまらないけど、訪問看護を利用したい」
「週に3日という制限よりも多く訪問看護を受けたい」
といったように、公的医療保険の条件を満たしていなくても訪問看護を利用したいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合でも、訪問看護自体は申し込めば利用できます。ただし、公的保険による割引は適用されないため、必要な費用のすべてを自分で負担しなければなりません。
訪問看護の費用をカバーできる公的制度

訪問看護は公的保険の対象となるとはいえ、その他の医療費も重なると支払いが高額になってしまうこともありますよね。そのような経済的負担に対し、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような方のために、訪問看護の費用をカバーできる公的制度についてご紹介します。
高額療養費制度
訪問看護にかかる費用は、高額療養費制度の対象となります。
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。訪問看護にかかる費用は医療行為としてカウントされるため、高額療養費制度の対象となります。
ただし、高額療養費制度の対象となるのは「公的医療保険の自己負担分」です。そのため、交通費やおむつ代、生活用品の購入費用などは高額療養費制度の対象外となります。
医療費控除
訪問看護に必要な費用は、医療費控除の対象にもなります。医療費控除とは、一定の医療費を支払った場合に、その費用の一部を所得税から控除できる制度です。
こちらも高額療養費制度と同じく、対象となるのは公的保険の自己負担費用です。
民間の医療保険や介護保険は使える?
訪問看護については、公的保険だけでなく民間の保険は使えるのでしょうか?もし民間の保険も使えるなら、さらに経済的な負担が軽減できそうですね。
民間の医療保険と介護保険、それぞれの対象範囲や注意点についてご紹介していきます。
医療保険の通院給付金は対象外であることが多い
民間の医療保険においては、訪問看護に対応した保険商品は少ないのが実情です。
医療保険においては、入院する際に受け取れる「入院給付金」や、通院する際の費用をカバーできる「通院給付金」が用意されているのが一般的。ただし、訪問看護は保障の対象に含まれていないことが多いです。
介護保険では要介護状態になると給付金がもらえる
一方で民間の介護保険では、要介護(要支援)認定を受けると給付金がもらえるのが一般的です。そのため、受け取った給付金を訪問看護の費用に充てることもできます。
ただし、給付金がもらえる「要介護認定のレベル」は契約内容により異なります。要介護1の認定から給付金が受け取れるものや、要介護3の認定から受け取れるものなど、保険商品により保障の対象範囲はさまざま。
すでに加入している方は、ご自身の給付条件について確認しておきましょう。
民間の医療保険や介護保険の選び方
訪問看護に備えて民間の医療保険や介護保険に加入する場合は、それぞれ考慮すべきポイントがあります。
- 医療保険:訪問看護もカバーできる保障・特約がついているか
- 介護保険:給付金をもらえる条件をどれだけ厳しくするか
医療保険と介護保険どちらにおいても、保障を充実させると支払う保険料は高くなってしまいます。そのため、経済的に無理のない範囲で保障内容を決めましょう。
迷ったら保険のプロに相談
とはいえ、保障内容を決めるのはやはり難しいです。さまざまな保険会社が用意している保険商品をチェックしながら、これからの収入や支出、病気にかかるリスクなどさまざまなことを考慮しなければなりません。
そのため、加入する保険を決めるのはなかなか骨の折れる作業となります。
だからこそ、専門知識を持つプロに相談してみるのがおすすめ。みんかぶ保険では、無料で保険のプロと一緒に保険を選ぶことができます。利用回数に制限はないため、納得のいくまでプロに質問が可能です。
保険選びはなるべく後悔のないよう進めたい。そう考えている方は、お気軽にご利用ください。