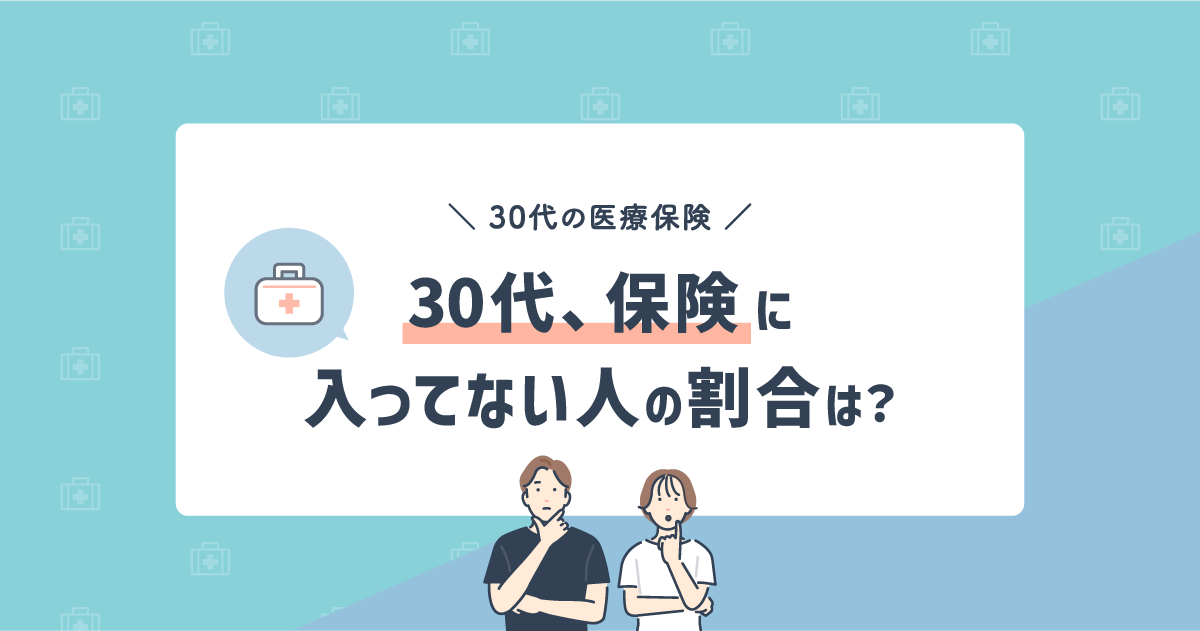骨折やひびは、多くの方が経験するかもしれないケガのひとつです。しかも、突発的に起きてしまうため、備えがなく家計にとっても痛手になってしまうことも。
そのような予期せぬ事態に備えるために、医療保険を活用したいと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、骨折やひびの場合、医療保険に入っていても必ず給付金が支払われるとは限りません。
では、骨折や骨にひびが入ってしまった場合に備えるためには、医療保険をどのように準備しておくべきなのでしょうか。
この記事では、骨折やひびに対する保険の適用範囲や、給付金がもらえる保険、注意点などについて解説します。
骨折しても医療保険の給付金が下りる可能性は低い
結論、骨折に対し医療保険の給付金がおりる可能性はあまり高くありません。
ただし、中には医療保険の給付金がもらえるケースもあります。具体的には、以下の3つが該当します。
特定損傷特約を付帯すれば骨折も保障対象に
入院や手術をすれば給付金を受け取れることも
ギブス装着時のみなし通院で給付金がもらえることも
入院や手術をすれば給付金を受け取れる
骨折の種類や程度によっては、入院や手術が必要です。例えば、以下のような骨折の場合は長期の入院や大掛かりな治療が必要になるでしょう。
大腿骨骨折
重度の肋骨骨折(3カ所以上の骨折がある場合や、臓器損傷を伴う場合など)
事故などによる複数箇所の骨折
骨折の程度が重く、入院や手術が必要になった場合は、医療保険の給付金を受け取ることができます。
【医療保険で請求できる給付金例】
入院給付金: 入院した場合に入院日数分の日額を受け取れる
手術給付金: 手術が必要になった場合、種類に応じて一定の金額が受け取れる
入院給付金や手術給付金は、保険会社や契約内容によって支払われる金額は異なります。また、支払われる日数や回数にも上限があるので、給付金の請求前や加入前に確認しておきましょう。
特定損傷特約を付帯すれば骨折も保障対象に
以下のように、骨折の部位や程度によっては、入院や手術が必要ないケースも多いでしょう。
1~2本の肋骨骨折
疲労骨折
軽度の剥離骨折
もし入院が必要でない軽度な骨折・ひびの場合でも、特定損傷特約のような、治療を受けたときに一時金を受け取れるような特約を医療保険に付帯することで保障の対象に含めることができます。
しかしどのような骨折が対象になるかについては、保険会社や契約内容により異なる可能性もあります。
また、特定損傷特約は病気ではなく特定のケガを保障するもので、医療保険の基本保障には含まれていないことが多いです。
そのため、骨折した場合に入院や手術をしなくても給付金を受け取りたい場合は特定損傷特約を付ける必要があります。
その場合、保険料が割高になる可能性があるため「保険料と骨折リスク」のバランスを十分に考えたうえで付帯するかを決めましょう。
骨折したら医療保険の給付金はいくらもらえる?

上記で紹介したとおり、保障内容や骨折の程度によって給付金が受け取れるケースがあります。
ここで気になるのは「いくらもらえるのか」ですよね。給付金を受け取りたい方にとっては、具体的な金額も知っておきたいところ。
実際にどれぐらいの金額がもらえるかに関しては、該当する保障やケガの程度によって異なります。
| 入院や手術を受けた場合 | 特定障害特約 |
みなし通院保障 |
|
|---|---|---|---|
| 金額 | 契約内容による 『入院給付金』 1日あたり数千円〜数万円 入院給付金日額の5倍〜40倍 |
契約内容による 5万円、10万円など |
契約内容による 1日あたり数千円〜1万円程度 |
上記はあくまで例です。実際の給付金額は保険会社や契約内容により異なります。
ただし、先述したようにすべての骨折が対象になるとは限りません。
実際に給付金が受け取れるのか、いくらもらえるのかについて具体的に知りたい方は、保険会社に確認を取りましょう。
骨折もカバー可能な傷害保険と共済
医療保険においては、骨折した場合に給付金を受け取れるケースが限定的であることをお伝えしました。
では、骨折にきちんと備えるためには医療保険以外にどのようなものが利用できるでしょうか?ここからは、次の2つについて解説していきます。
傷害保険
共済
傷害保険とはケガの補償に特化した保険
傷害保険は、交通事故や災害によるケガの補償に特化した保険です。骨折やひびも補償対象となるため、お金の心配をせず安心して治療に専念できそうですね。
傷害保険では入院がなかった場合でも通院日数に応じて給付金が支払われます。
例えば、骨折やひびの治療でギブスを装着した場合、実際に通院しなくても、みなし通院として給付金が支払われることがあります。
みなし通院とは、ギブス装着期間を通院日数とみなして通院給付金を支払う補償のことです。
みなし通院として認められる例
足の骨を骨折してギブスを装着し、1ヶ月間自宅で安静にしていたとします。その間の通院日数は0日でも、みなし通院の補償があれば30日分の通院給付金が支払われます。
ただし、すべての医療保険でみなし通院保障が付帯できるわけではありません。
また、またギブス装着期間が短い場合や装着部位によっては対象にならないこともあるので、加入している/加入を検討している医療保険の契約内容をきちんと確認しましょう。
共済は医療保険と似ている保障制度
共済は、同じような目的を持つ人々が互いに助け合うために作られた制度です。
保険と似ていますが、非営利の事業であり加入する場合は組合員になる必要がある、という点が保険とは異なります。
共済の中には医療費の補助を目的とした医療共済や、ケガの保障を目的とした傷害共済などがあります。保障内容も保険と似ており、通院給付金や入院給付金を受け取れるものが一般的です。
共済は保険と同じような仕組みですが、営利目的ではないため保険料が割安になる傾向があります。ただし給付金額や保障内容が年齢によって変わるタイプもあるため、契約時には保障内容をしっかり確認しましょう。
医療保険、傷害保険、共済の違いや選び方
医療保険や傷害保険、共済は、保険料や給付金の額、保障内容がそれぞれ異なります。
| 医療保険 | 傷害保険 |
共済 |
|
|---|---|---|---|
| 保障内容 | 入院や手術 通院保障も付帯できる場合も |
ケガの補償 | 入院や手術 ケガだけの保障もあり |
保険料 |
年齢や性別、既往歴、職業などさまざまな要素によって決まる |
年齢によって決まる |
掛け金(保険料と同義)は医療保険や傷害保険より手軽なことも |
自分に合った保障を選ぶには、それぞれの特徴を理解し、保障内容や保険料、給付金の額などを比較検討するのが大切。また家族構成や生活スタイル、予算に合わせて選ぶことも重要です。
例えば、子供がスポーツをしている家庭なら傷害保険に加入しておくと安心ですし、病気の保障を重視するなら医療保険を選ぶのが良いでしょう。
保険料を抑えたい方は、共済も検討するのもおすすめです。
さらに言えば、「一番重視するポイント」で加入する保険の種類を選び、そのうえで不安な部分は特約や別の保険で備えられると尚良しです。
自分ではイマイチ選びきれない場合は、保険のプロに相談するのも一つの手です。
骨折してから医療保険に加入し給付金を受け取ることはできる?

骨折は予期せぬタイミングで急に起こってしまいます。いざというときのためにお金を用意しておくのが理想ではありますが、急な治療費に困ってしまう方も多いでしょう。
では、骨折してから給付金を受け取るために医療保険に加入することはできるのでしょうか?また加入できたとしても、給付金は受け取れるのでしょうか?
骨折してから加入しても給付金を受け取るのは難しい
結論、骨折してから医療保険に加入したとしても、給付金は基本的に受け取れません。
医療保険においては、加入後に発生した病気やケガに対しては保障の対象となります。
ただし、加入前もしくは保障開始前に発生したものに関しては、保障の対象外となってしまいます。
そのため、いざというときのために「事前に」備えておくのがベストです。
骨折してから医療保険に加入する方法
とはいえ、骨折してから「やはり備えは必要」と考えて医療保険に加入したい方も多いでしょう。
また、追加でケガをしてしまったり何らかの大きな病気にかかってしまった場合、より大きなお金が必要になってしまいますよね。
そのため、今後に備えて何か準備をしておくと安心でしょう。
治療中に加入するのは基本的に難しい
骨折の治療中に医療保険に加入することは、基本的に難しいと言えます。保険会社が加入時に健康状態を審査し、リスクの高い人に対しては加入を制限するからです。
骨折の治療中は健康上のリスクが高いと判断され、加入を断られる可能性が高くなります。
保険会社にとって、骨折の治療中の人はすでに医療費がかかることが確実であり、給付金の支払いリスクが高いと考えられます。そのため、多くの保険会社は治療がまだ終わっていない人の加入を避ける傾向があります。
また、仮に加入できたとしても、骨折に関連する治療は保障の対象外とされることが多いです。
制限付きで加入できることもある
骨折の治療中でも、制限付きで医療保険に加入できる場合があります。軽度な骨折であるほど、医療保険に加入できる可能性が高いです。
しかし、給付金が請求できる期間や金額、保障対象が一部制限されるケースが多いです。それでも加入すべきかどうか、きちんと考えましょう。
医療保険に加入できても、保険料は通常よりも高額になる可能性が高いです。病気やケガに関して一定のリスクがあるとみなされるため、その分多くの保険料を請求されてしまう可能性が高いのです。
また、告知義務違反に該当しないよう、骨折していることは正直に伝えるのが大切。告知義務違反があった場合、給付金が支払われないことがあります。
加入条件が緩やかな医療保険を選ぶ
医療保険の中でも加入しやすいタイプの保険を選ぶこともひとつの方法です。
医療保険においては、加入基準が緩やかで、持病があっても加入できるものもあります。
引受基準緩和型
加入時の告知項目が少ない医療保険
無選択型
健康状態に関する告知が必要ない医療保険
上記2つの保険に関しては、骨折やヒビの治療中でも加入しやすいのが特徴です。ただし、保障内容が限定的だったり、保険料が高かったりする傾向があるので、加入する際は十分に検討しましょう。
持病がある方でも入りやすい引受基準緩和型保険の選び方・人気おすすめランキング
骨折してから利用できる制度やもらえるお金は?

医療保険だけでなく、利用できる公的制度についてもしっかり理解しておくのが大切です。慌てて医療保険に加入しなくても、公的制度を使えばきちんと費用をカバーできるかもしれません。
ここからは、以下の公的制度についてご紹介していきます。
傷病手当金
障害年金
障がい者手帳
高額療養費制度
医療費控除
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだ場合に、健康保険から支給される手当金です。一定の条件を満たせば、骨折で休職した場合も傷病手当金を受け取ることができます。
支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額で、支給期間は通算1年6ヶ月です。
傷病手当金は、会社を休んでいる期間の生活を支えるための重要な制度です。骨折で長期間仕事を休まなければならない場合は、傷病手当金の申請を検討しましょう。
障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたした場合に、年金として一定金額が支給される制度です。骨折が原因で障害が残った場合、障害等級に応じて障害年金を受け取ることができます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障がい者手帳
骨折が原因で障害が残り、障がい者手帳を取得した場合、様々な支援サービスを利用することができます。
障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、重度の骨折により身体に障害が残った場合は、身体障害者手帳の対象です。
身体障害者手帳は障害の部位や程度に応じて、1級から6級までの等級に分けられ、等級によって利用できる支援サービスの内容が異なります。
重度障害者であれば、医療費の助成や交通機関の割引、税制上の優遇措置などを受けられます。
ただし、一定の障害認定基準に該当していなければ手帳は取得できません。そのため申請の際は、医師の診断書や意見書が必要になります。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担の上限額を超えた分が払い戻される制度です。骨折の治療で高額な医療費がかかったとしても、自己負担額は一定の金額で抑えられます。差額ベッド代、食事代などが一部含まれないものがあります。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。そのため、ご自身は最大でいくら支払わなければならないのかチェックしてみましょう
高額療養費制度は、高額な医療費の負担を軽減するための重要な制度です。骨折の治療で高額な医療費がかかる場合は、積極的に利用しましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から控除する制度です。骨折の治療で多額の医療費を支払った場合、医療費控除により所得税を軽減することができます。
ただし、給付金や高額療養費制度による還付金は、控除の対象外となります。また、控除を受けるためには5年間の医療費の領収書を保管し、確定申告時に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
計算や手続きがややこしく感じてしまいますが、医療費控除は多額の医療費負担を減らすための重要な制度。そのため、骨折の治療で多額の医療費を支払った場合は、確定申告で医療費控除をきちんと受けましょう。
骨折時における給付金請求の手順とは?

では実際に骨折してしまった場合、給付金を受け取るまでどのようなステップが必要になるでしょうか?
詳細は保険会社ごとに異なる場合もありますが、以下のステップで請求手続きを行うケースが多いです。
まずは保険会社に連絡
必要書類に記入し提出
口座に給付金が振り込まれる
まずは保険会社に連絡
骨折の治療を受けた場合、まずは加入している保険会社に連絡をします。電話やサイト上の専用フォームから保険会社に連絡が可能です。その際、保険証券やパンフレットを手元に用意しておくと良いでしょう。
保険会社に連絡する際は、以下の情報を正確に伝えることが大切です。
骨折の発生日時と場所
骨折の原因と状況
治療を受けた医療機関の名称と所在地
入院日数や手術の有無など、治療の概要
必要書類に記入し提出
給付金を請求する際には、以下のような書類が必要です。
給付金請求書
診断書
医療費の領収書
本人確認書類
保険会社から指定された書類に必要事項を記入し、診断書や領収書などと一緒に提出します。このとき、記入漏れや書類の不足がないように注意しましょう。また、提出期限を守ることも大切です。
給付金請求書には、保険証券番号、被保険者名、請求者名、事故発生日時と場所、事故原因と状況、治療内容と治療期間、請求金額などを記入します。記入漏れや誤りがないよう、十分に確認することが大切です。また、被保険者の署名や押印が必要な場合もあります。
診断書や請求書に関しては、保険会社がフォーマットを指定している場合がほとんど。特に診断書は病院ではなく保険会社のフォーマットに従う必要があるため、保険会社から書類が送られてきてから医師に記入してもらいましょう。
口座に給付金が振り込まれる
書類に不備がなければ、審査を経て、指定した口座に給付金が振り込まれます。振込までの期間は、保険会社によって異なりますが、通常は1~2ヶ月程度です。振込が完了したら、正しい金額が振り込まれているか確認しましょう。
給付金請求の手続きは骨折の治療で大変な中で行わなければならないため、負担に感じることもあるかもしれません。しかし、保険に加入している以上、請求手続きを行わないと保険のメリットは活かせません。
医療保険の場合、数年間は給付金を請求できます。そのため、まずは治療に専念し、完治してから請求手続きを開始するという手もあります。
まとめ
多くの医療保険では、骨折やひびは保障の対象外とされることも多いため、特約の付帯や、傷害保険、共済の活用を検討することをおすすめします。
また、骨折の治療中に新たに医療保険に加入することは難しいため、日頃から備えておくことが大切です。万が一、骨折によって生活に支障をきたした場合は、傷病手当金や障害年金、障がい者手帳など、利用できる制度を確認し、活用しましょう。
骨折やひびは、誰にでも起こりうる予期せぬ出来事です。自分に合った保険を選び、もしものときに備えることが、安心につながります。
保険について迷ったらプロに相談
保険選びに関しては、なかなか決めきれず迷ってしまう方も多いはず。
医療保険に加入すべきかはもちろん、保険会社はどうやって選べばいいか、どんな保障内容が必要なのか……。たくさんの情報を集めたうえで判断するのは、なかなか難しいですよね。
だからこそ、保険選びはプロに相談するのがおすすめです。みんかぶ保険では、保険に関する知識を豊富に持つプロに、無料で何度でも相談できます。
しつこい営業はなく、満足のいくまで利用できます。保険会社ごとの見積もりも依頼できるため、保険選びが一気に進むでしょう。
保険について迷ったら、まずは無料で相談してみましょう。