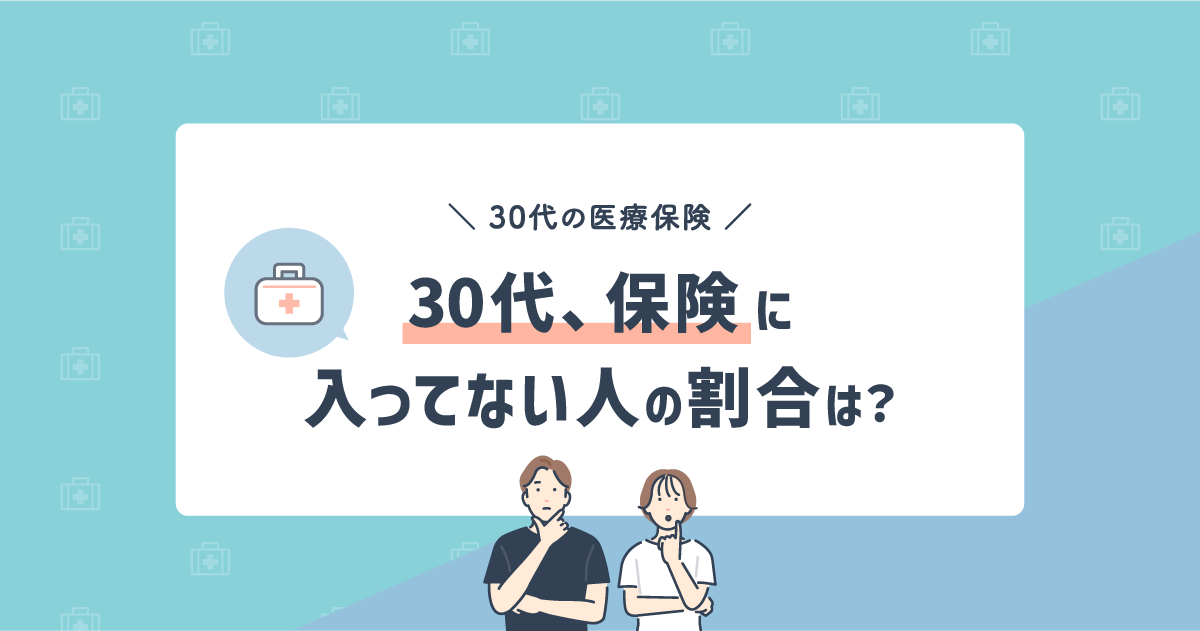妊娠、そして出産することは、多くの不安や心配がついてまわります。中には、費用面について考えている方も多いのではないでしょうか。出産は今後「多くのお金が必要になる節目」でもありますから、できるだけ自己負担を減らしたいというのが本音ですよね。
特に、出産がスムーズに進まず「帝王切開」が必要になった場合、追加で費用が必要になります。
そのような不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、事前に知識を身に着け備えておけば、帝王切開や出産の費用に対する不安は大きく減らせます。
帝王切開とはどんな出産方法?
まずは、帝王切開とはどのようなものなのかについて確認してみましょう。帝王切開の内容や目的について理解しておくことで、保険との関係や費用についてより深く理解できるようになります。
すでにご存知の方は、「帝王切開の費用は保険が適用される?」からご覧ください。
お腹を切開して胎児を直接取り出す
帝王切開とは、お腹を切開して胎児を直接取り出す分娩方法です。通常の分娩と比較して、かなり大掛かりな処置と言えます。
お腹を開く、と聞くと怖いと感じる方も多いかもしれません。ですが、医療技術の進歩により、帝王切開の安全性も向上してきているため、過度な心配は必要ありません。
うまく分娩が進まない時の手段
覚えておくべきポイントは、帝王切開は緊急時に行われることが一般的だという点です。
出産時には、胎児の心拍に異常が発生する、母体の健康に危険が生じるなど、通常の分娩が不可能な状況となってしまうこともあります。
その場合、素早く確実に赤ちゃんを取り出さなければなりません。そのために行われるのが帝王切開です。
帝王切開の費用は保険が適用される?
ここから、今回のメイントピックでもある「帝王切開の費用は保険が適用されるかどうか」についてご紹介していきます。保険適用の有無によって自己負担費用が大きく変わるため、気になる方も多いのではないでしょうか。
帝王切開は公的医療保険が適用される
結論、帝王切開の費用は公的医療保険が適用されます。そのため、帝王切開にかかった全体の費用のうち自己負担は3割となり、経済的負担が大きく抑えられます。
「産婦人科社会保険診療報酬点数早見表」(2022年4月)によれば、緊急帝王切開の費用は「22万2,000円」となっており、自己負担額はおよそ「6万6,600円」です。
先ほどお伝えした通り、帝王切開は分娩中の緊急時に対する処置として行われるのが一般的です。つまり、帝王切開は「医療行為」。そのため、公的健康保険の対象となります。
3割負担とはいえ、出産費用にプラスして「6万円弱」の費用がかかるのは痛手ですよね。では、帝王切開による費用は「民間の医療保険」でカバーできるのでしょうか。
民間の医療保険も保障が適用されることが多い
帝王切開は民間の医療保険でも基本的に保障の対象になります。実際の保障範囲や条件は、保険商品ごとに異なります。
民間の医療保険に加入しており、帝王切開が「保障の対象範囲」の場合「入院給付金」や「手術給付金」が支給されます(具体的な金額は加入している保険商品により異なります)。
公的医療保険に上乗せして費用面をカバーできるのは、嬉しいポイントですね。
通常の出産は保険が適用されない
出産にあたって気をつけていただきたいのは、「通常の出産費用は保険の適用外」であること。
帝王切開のような処置をせず、順調に出産できた場合、出産に必要な費用には公的医療保険も民間の医療保険も適用されません。
そのため、通常出産に必要な費用はすべて自己負担となってしまいます。
保険の対象となるのは「異常分娩」
保険の対象となるのは、分娩において異常が起こり何らかの処置が行われる「異常分娩」です。異常分娩=医療行為と判断されるため、公的医療保険の対象になるのです。
一方で、通常の分娩は「治療のための医療行為」ではないとみなされます。そのため、出産に必要な費用は高額になってしまいますので、注意が必要です。
帝王切開に必要な費用はいくら?

出産を控えた人の中には、より具体的な金額が気になる方も多いはず。さらに言えば、帝王切開のみならず、出産全体で必要となる費用について把握しておくのがベストでしょう。
帝王切開の自己負担費用はおよそ6万円
帝王切開を行った場合、自己負担費用はおよそ6万円となります。
分娩中の急な判断によって行われる「緊急帝王切開」の場合、必要な費用は22万2,000円となります(診療報酬点数をもとに算出)。公的医療保険が適用されるため、自己負担額は約6万円。
一方、お産が始まる前から帝王切開を計画して行う「予定帝王切開」の場合、必要費用は20万1,400円です(診療報酬点数をもとに算出)。双子や逆子など「通常分娩が困難である」と判断される場合等に行われます。
事前に予定している場合、自己負担費用は緊急帝王切開よりもやや安くなります。
帝王切開によって入院費用も高くなる可能性が
金額が変わるのは、帝王切開の処置そのものにかかる費用だけではありません。帝王切開をした場合、通常の出産と比較して入院費用も高くなる可能性があります。
帝王切開をした場合、通常の出産よりも入院日数が長期化することが多いです。そのため、入院費用や赤ちゃんの健康管理にかかる費用「新生児管理保育料」が通常の出産より高くなってしまうこともあります。
1日あたりの入院費用の平均は2万700円と報告されており、(参考:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》)6日間入院した場合には「13万円程度」がかかります。
また、入院費用に加えて、新生児管理保育料もかかります。新生児管理保育料は病院ごとに異なりますが、5,000円〜2万円と言われているため、同じく6日間必要だった場合3万円〜12万円程度かかる計算です。
出産に必要な費用はおよそ50万円
一方、全体の出産にかかる費用は約50万円と言われています。
費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 入院料 | 115,776円 |
| 分娩料 | 276,927円 |
| 新生児管理保育料 | 50,058円 |
| 検査・薬剤料 | 14,419円 |
| 処置・手当料 | 16,135円 |
| 室料差額 | 17,255円 |
| 産科医療補償制度 | 15,203円 |
| そのほか | 32,419円 |
| 妊婦合計負担額 | 538,263円 |
出産時には、上記の金額を自分で支払わなければなりません。もし帝王切開をすることになったら、さらなる費用が必要となります。
ですが、過度に不安にならなくても大丈夫。出産時にはさまざまな制度を利用し、お金を受け取ることができます。
帝王切開や出産の経済的負担を軽減させる方法

これからご紹介する「出産費用をカバーするための方法」は、大きく分けて2つです。
- 公的制度を活用する
- 医療保険に加入する
上記の方法を活用することで、お金の不安を大きく減らすことができます。
公的制度を活用する
出産時には、以下の公的制度を利用することができます。
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 48〜50万円 |
| 出産手当金 | 給与・報酬の2/3 |
| 高額療養費制度 | 自己負担額の上限を超えた分の差額 |
| 医療費控除 | 医療費に応じた所得税控除 |
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産費用による経済的負担を軽減するための給付金です。公的医療保険に加入している人が対象となるため、出産するほぼすべての人が受け取ることができます。
支給金額は、48〜50万円。出産費用の大部分をまかなうことができるため、心強いですね。
出産手当金
出産のために休業すると、その分収入が減少してしまいます。その減少分をカバーするために支給されるのが、出産手当金です。
健康保険に加入している労働者が対象で、支給額は給与の2/3。
出産の日(実際の出産が遅れた場合は出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間が対象となります。

高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月あたりの医療費が一定額を超えた場合に、超過した分の医療費を帳消しにできる制度です。対象となるのは、公的医療保険が適用される費用のみとなります。
上述した通り、帝王切開の費用は公的医療保険の対象。そのため、高額療養費制度における自己負担額として計算に加えることができ、上限額を超えた場合は差額を受け取ることができます。
医療費控除
確定申告時に、1年間の医療費を所得額から差し引くことで、税金を安くすることができる「医療費控除」。帝王切開も、医療費控除の対象となります。
医療費控除は高額療養費制度よりも幅広い種類の費用が対象となります。
医療費控除の対象となる費用
- 妊娠後の定期健診費用
- 切迫早産や妊娠悪阻など医師が認めた入院費用
- 通院や入院時に公共交通機関を使った際の交通費
- 入院時に公共交通機関が使えない場合のタクシー代
- 入院中に病院から出された食事の費用
- 出産時の入院費用
医療費控除の対象とならない費用
- 妊娠検査薬の費用
- 里帰り出産のための帰省費用
- 入院時の洗面具やパジャマなどの身の回り用品代
- 入院中に自分で用意した食事の費用
- 個室入院での差額ベッド代
帝王切開や出産費用を医療費控除として申請する場合、出産一時金などの公的制度や医療保険によって受け取った給付金を差し引く必要があります(出産手当金は除外)。
帝王切開が保障の対象になっている医療保険に加入する
公的制度だけでなく、民間の医療保険に加入することで、出産費用をさらに手厚くカバーすることができます。
医療保険に加入すれば、帝王切開によって必要になる入院費用や手術費用が保障されます。受け取れる給付金の金額は自分で選べることも多いため、不安の大きさや貯蓄状況に合わせて保障の手厚さを柔軟に変えることができます。
保障が手厚くなる分、経済的な不安は大きく抑えることができそうですね。
将来の出産に備えて 医療保険には加入すべき?
医療保険に加入すべきかどうかについては、結論を出すのが難しい問題でもあります。なぜなら、自身の健康状態や経済的な要素、将来に対するリスク管理など、さまざまな要素によって医療保険の必要性が変わるからです。
ですが、出産費用に対して少しでも不安を感じるなら、医療保険に加入しておいたほうが無難であると言えるでしょう。医療費の負担が大きくなり、経済的負担が重くなるにつれ、医療保険に加入しなかったことを後悔してしまう可能性が高くなります。
帝王切開をする人の割合は年々増えている
注目すべきなのは、帝王切開を選択する女性の割合が年々増えていること。要因としては、「出産年齢の高齢化」や「帝王切開によるリスクの低下」が挙げられます。

厚生労働省「医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」
2020年では、3〜4人に1人が帝王切開で出産していることがわかりますね。
保険が適用されるとはいえ、帝王切開による出産は通常の分娩よりも多くの費用が必要。ですが、医療保険に加入していれば、経済的な不安も大きく軽減されます。
帝王切開をする可能性が増している現状を考えれば、医療保険の必要性も高まっていると考えられるでしょう。
帝王切開による医療保険の給付金はいくらもらえる?
では、もし医療保険に加入している場合、帝王切開による給付金をいくらもらえるのでしょうか。メジャーな保障内容や医療保険によって受け取り可能な金額について、具体例をもとに解説していきます。
入院給付金
帝王切開をした場合、入院は避けられません。医療保険に加入すれば、保険契約時に設定した1日あたりの金額をもとに、入院日数に応じて「入院給付金」を受け取ることができます。
受け取った給付金は、入院に伴うさまざまな費用に充てることができます。
手術給付金
帝王切開を行った場合は、入院給付金だけでなく「手術給付金」も受け取ることができます。
帝王切開は手術に分類されるため、手術給付金の対象となります。給付金の金額は、保険商品や契約内容によって変動します。
医療保険に入っていないと費用はいくら変わる?
医療保険に加入すべきか考える上で、「具体的にいくらもらえるか」は気になるポイントですよね。
実際、医療保険に加入しておくことで、自分で負担する費用は大きく変わります。具体例をもとに考えてみましょう。
- 帝王切開による入院日数は10日間
- 1日あたりの入院給付金は1万円
- 手術給付金は10万円
と仮定すると、医療保険に入っておくことで帝王切開時に20万円を受け取れる計算になります。
出産時に医療保険に加入する際の注意点

異常分娩に備えて医療保険に加入したい場合、気をつけておくべきポイントが2つあります。
- 妊娠前に加入する
- 保障内容と保険料のバランスを考える
妊娠前に加入する
妊娠が発覚した後に医療保険に入ろうとしても、加入できない可能性があります。そのため、妊娠が発覚する前に契約するのがおすすめ。
医療保険は、手続きをしたすべての人が加入できるわけではなく、一定の基準が設けられています。妊娠中のように「給付金を受け取る可能性がすでに高い」状態で加入しようとする場合、基準を満たしていないと判断されることが多いです。
保障内容と保険料のバランスを考える
医療保険に加入する際は、保障内容と保険料のバランスを考慮することも重要です。
保障内容を手厚くするほど、保険料も高くなります。保障内容を過度に充実させてしまうと、保険料の負担が大きくなりすぎてしまいます。かといって、保険料を安くするために保障を削りすぎてしまうのも、いざというときに後悔してしまうでしょう。
ご自身の貯蓄状況やリスク観と照らし合わせつつ、最適なバランスを見つける必要があるでしょう。
保険のプロに相談しよう
自分に最適な保険商品を見つけることは、実際は骨の折れる作業となります。医療保険について勉強するだけでなく、多くの保険商品の特徴や保障内容を把握し、自身の収入も計算して……。
とても時間がかかってしまう上に、正解がないため迷ってしまいがち。
そこでおすすめなのが、保険のプロに自分の要望や予算、保障に対する考えを相談してみるという方法です。
相談と聞くと「面倒だな、イマイチな商品をおすすめされないか不安」と思うかもしれません。しかし、「自分が納得する医療保険をスムーズに見つけられる」というメリットもあります。
みんかぶ保険では、悩みや不安を保険のプロに伝えた上で、的確なアドバイスをもらったり、おすすめの保険商品を教えてもらったりすることが可能です。しつこい勧誘や営業メールもありません。
これから医療保険に加入しようと考えている方は、ぜひ活用してみてください。