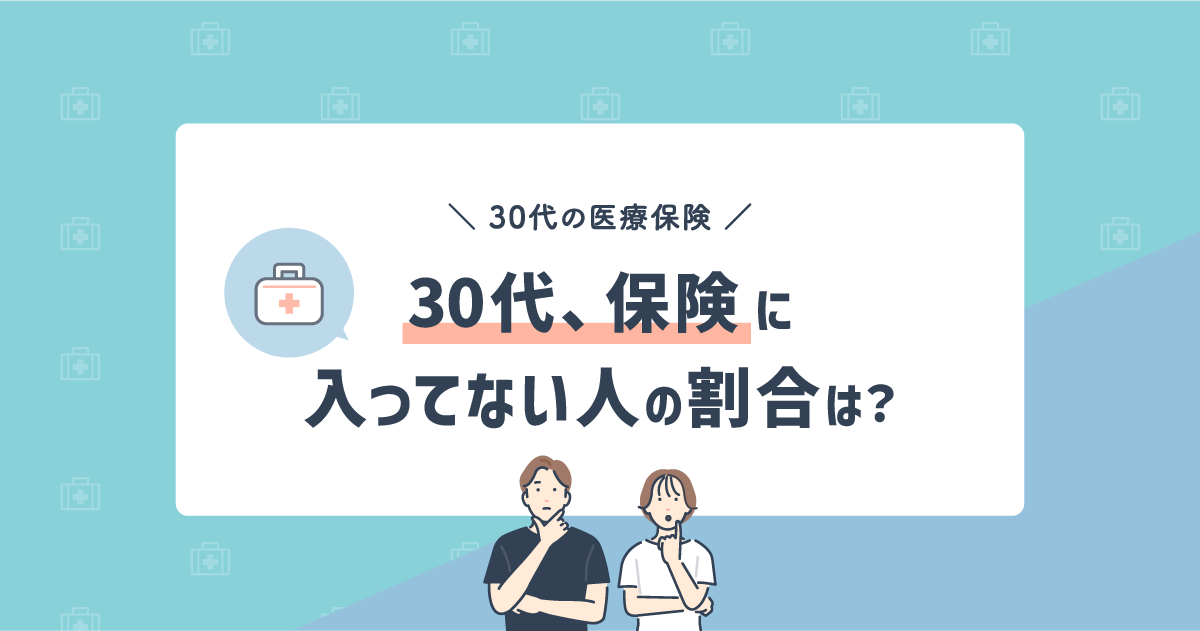社会人になったり、結婚をしたり、子供が生まれたときなど「人生の転換点」にさしかかると
という疑問を抱く人は多いと思います。
もし、医療保険がいらないのであれば保険料の分お金に余裕が生まれますが、実際のところ本当に必要なのでしょうか。
この記事では、そんな「医療保険はいらないのか必要なのか」という疑問に対する答えを具体的に紹介しています。
この記事を読めば
- 医療保険が必要な人
- 医療保険がいらない人
の判断がつくようになりますよ。
それでも「自分で判断する自信がない」という方は、みんかぶ保険の見積もり機能(無料)で、保険のプロに相談することもできます。
医療保険はいらないと言われる3つの理由

早速、医療保険がいらないと言われる「客観的な」3つの理由を確認してみましょう。
公的医療保険が充実しているから
高額療養費制度があり高額な医療費もカバーできるから
- 貯蓄や投資に回した方が、手元に残る金額が増える可能性があるから
次の章では「医療保険が必要といわれる理由」も説明しています。どちらの方が自分の考えにマッチするか、納得できるかを考えながら読み進めてみましょう。
公的医療保険が充実しているから
日本には充実した「公的医療保険制度」が用意されています。
- 被用者保険(健康保険・共済制度)
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
上記のような公的医療保険によって、医療費の自己負担額が1割〜3割で済みます。

それだけでなく、公的医療保険ではさまざまな制度が利用可能です。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 入院時食事療養費 | 入院中の食事費用を補助 |
| 入院時生活療養費 | 65歳以上の人が入院する際に所得に応じて食費や居住費を補助 |
| 高額療養費制度 | 1か月あたりの医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される |
| 傷病手当金 | 病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに給付金が支給される |
たとえば、年収500万円・40代の人ががんにかかってしまい、保険適用の医療費が月100万円かかったとしましょう。

その場合の自己負担は以下のようになります。
窓口負担→3割(約30万円)
高額療養費としての払い戻し→約21万2570円
自己負担限度額(最終的な自己負担)→8万7430円
例のようにもし高額な医療費がかかったとしても自己負担額はそこまで大きくならないよう国が保険制度を整備してくれているのです。
この「公的医療制度が充実していること」が医療保険がいらないと言われる一番の理由といえるでしょう。
とはいえ、完治が難しい病気や長期治療が必要な場合はこの限りではありません。一回の治療が3万円だとしても入院費や、薬代などが複数回かかるとなると「自己負担額」も大きくなってしまいます。
ですから、公的医療保険があるからといって医療保険はいらないというのは少々言い過ぎのように感じられます。
高額療養費制度があり高額な医療費もカバーできるから
既出の高額療養費制度をもう少し深掘りしてみましょう。高額療養費制度とは国民の医療費負担額の「上限」を定めることで一定以上の経済負担を強いないようにするための制度です。
自己負担額の上限は「年齢」と「所得区分」の二つによって決められます。
69歳以下の被保険者の場合
| 適用区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) |
|---|---|
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
| ~年収約370万円 健保:標準報酬月額※126万円以下 国保:旧ただし書き所得※2210万円以下 | 57,600円 |
| 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
70歳以上の被保険者の場合
| 適用区分 | 自己負担限度額 | |
| 個人ごと(外来) | 世帯ごと | |
| Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) | 8,000円 | 15,000円 |
| Ⅱ住民税非課税世帯 | 24,600円 | |
| 年収156万~約370万円 標準報酬月額:26万円以下 課税所得額※3:145万円未満等 | 18,000円 (年間144,000円) | 57,600円 |
| 年収約370万円~約770万円 標準報酬月額:28万円以上 課税所得額:145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
| 年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額:53万円以上 課税所得額:380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
| 年収約1,160万円~ 標準報酬月額:83万円以上 課税所得額:690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
また、過去12ヶ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合には「多数該当」という扱いになりさらに自己負担額が下げられます。
高額療養費制度があるため、がん保険や医療保険は必要ないと考えている人もいるということですね。
この「自己負担額の範疇なら余裕で支払いができる人」に関しては医療保険は不要かもしれません。
しかし、自己負担額が減ったとしてもかなり家計に響くな…と感じた人は、自分の家計と保障内容のバランスのとれた医療保険に加入したほうが良いと考えます。
貯蓄や投資に回した方が、手元に残る金額が増える可能性があるから
医療保険へお金を払うのであれば、その分投資や貯蓄に回したほうが経済的に合理的であるという考えもあります。

たしかに「NISA制度」などを活用してコツコツ資産形成をすれば長期的には大きな利益と積立額になる可能性も十分にあります。
しかし、投資の成果がでるタイミングと「病気に罹ってしまうタイミング」が必ずしも一致するとは限りません。
運悪く「株式市場が不調なとき」と被ってしまうと思わぬ経済負担を受けてしまう可能性もあります。
投資にはこうした「不確実性(リスク)」がどうしても付随してしまうのです。ですから「安心のための医療保険」と「将来資金のための資産形成」は別物として考える必要があるのです。
一番理想的なのは「家計的に負担をかけない金額の医療保険」+「無理のない範囲での資産形成」の両立です。
医療保険は必要と言われる3つの理由

次は医療保険が必要だと言われる理由を確認していきましょう。主な理由は以下の3つです。
- 大きな病気やケガに備えることで安心感が得られるから
- 差額ベッド代や先進医療など保険適用外の費用にも備えられるから
- 急な出費に対応できるお金が十分にないから
大きな病気やケガに備えることで安心感が得られるから
一番理由として大きいのは「安心感が得られるから」です。
もともと、保険は得するために入るものではありません。実際、大きな病気にかからなければ保険料を支払った分だけ「損」になってしまいます。
しかし、医療保険に入っていて一番良いケースは「病気にかからず健康に過ごすことができた場合」ではないでしょうか。
さらに、医療保険に入っていれば加入期間は「大病にかかったらどうしよう」「今の経済状況で治療費って支払えるのかな」など未来への「不安」が軽減されます。
日常生活における「不安」を保険料を支払うことで取り除くことができる。これが医療保険のメリットでもあり、必要だと言われる理由にもなります。
誰しも「いつ病気になってしまうのか」はわかりませんし、その不安が払拭できるのはありがたいですよね。
差額ベッド代や先進医療など保険適用外の費用にも備えられるから
公的医療制度が充実している日本ですが、なかには保険適用にならない治療費も存在します。中でも代表的なのが以下2つ。
- 差額ベッド代…入院の際に複数人数がいる大部屋ではなく個室にした場合にかかる費用
- 先進医療…一般治療よりも高度な医療技術を用いた治療。新しく開発された治療法や手術がメイン。
差額ベッド代は入院する病院にもよりますがおおよそ「6000円前後」かかります。10日間入院したとすれば「60,000円」は自己負担しなければなりません。
この金額に加えて「公的医療制度」で賄えない分の自己負担が重なると家計にとって大きな負担になってしまいそうです。
さらに、先進医療になれば以下のような金額が必要です。資金不足で受けたい治療が受けられないなんていう事態になったらいやですよね。
インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用 療法 成人T細胞白血病リンパ腫 | |
| 先進医療総額 | 9,326,110円 |
| 年間実施件数 | 7件 |
| 1件あたりの平均額 | 約133万円 |
重粒子線治療 肝細胞癌 | |
| 先進医療総額 | 24,500,000円 |
| 年間実施件数 | 7件 |
| 1件あたりの平均額 | 約350万円 |
重粒子線治療 非小細胞肺がん | |
| 先進医療総額 | 9,163,000円 |
| 年間実施件数 | 3件 |
| 1件あたりの平均額 | 約305万円 |
マルチプレックス遺伝子パネル検査 進行性再発固形がん | |
| 先進医療総額 | 47,200,000円 |
| 年間実施件数 | 93件 |
| 1件あたりの平均額 | 約51万円 |
こうした公的医療制度の「対象外」の部分をカバーできるのが医療保険なんですね。お金が原因で治療法が狭まってしまったら悔やんでも悔やみきれません。
急な出費に対応できるお金が十分にないから
そもそも、高額療養費制度によって自己負担の上限額が決められていても、その金額分の余裕資金が全家庭にあるわけではありません。
以下は、総務省が公表している「家計調査報告(家計収支編)」をもとに、貯蓄率を算出したデータです。

家計調査報告(家計収支編)-2023年(令和5年)平均結果-(世帯人員・世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出)
※預貯金の数値は、貯蓄の純増額を採用しています。貯蓄純増 = (預貯金 + 保険料) - (預貯金引出 + 保険金)
このデータによると、毎月の預貯金の平均値は「約12万5000円」です。さらに平均値がこの数値ですから、中央値はもっと少ない金額になることが予想されます。
となると、いくら自己負担額の上限が設けられていても家計へのダメージが大きい家庭が多いことになります。急に数万円〜10万円規模の出費が必要になったら、少なからず負担に感じる人も多いはず。
こうした「そもそも預貯金が足りないから医療保険に入っておく」という意見もあるのですね。医療保険であれば月数千円で加入できるケースが多いですから。
医療保険に入っていない人の割合は?

では実際に、どれぐらいの人が医療保険に加入しているのでしょうか?医療保険に入っている人、入っていない人の割合を確認してみましょう。
医療保険の加入割合をみることで「何歳から医療保険に加入しよう」と思い始めるのか「目安」を知ることができます。

※民間の生命保険会社や郵便局、JA(農協)などで取り扱っている生命保険の医療・疾病関係の特約や医療保険(ガン保険など、特定の病気を対象とするものを含む)(銀行・証券等の窓口で加入した商品も含む)
公益財団法人 生命保険文化センター「令和元年度生活保障に関する調査」
女性の方が男性よりも加入率が高いようです。また20代の加入率は50%前後ですが、ライフイベントが重なる30代以降は加入割合が大きく増加しています。
【令和元年度 疾病入院給付金の支払われる生命保険加入率(全生保)】

公益財団法人 生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査/疾病入院給付金の支払われる生命保険加入率」
年代関係なく全体で見ると、7割以上の人が医療保険に加入しています。医療保険に入っている人のほうが多数派であることが分かりますね。
医療保険がいらない人の特徴

ここまでご紹介した内容を踏まえて、医療保険がいらない人の特徴をわかりやすく解説していきます。
次の3つに当てはまる人は、医療保険に入る必要性が低いと言えるでしょう。
- 十分な貯蓄がある
- 勤務先の福利厚生が充実している
- 健康状態に対する不安が小さい
結論、医療保険に頼らずに多額の医療費を自力で無理なく支払えるのであれば、医療保険に入る必要性は低いでしょう。
十分な貯蓄がある
入院や手術などの医療費を自力でカバーできるほど貯蓄がある人は、医療保険に加入する必要性は低いと言えるでしょう。
もともと資産に余裕がある場合には医療保険ではなく貯蓄として余裕資金を用意したほうが良いという考え方もあります。
ただし貯蓄額だけで判断するのは少々危険です。将来のライフプランや収入の見通し、投資状況などさまざまな側面から多角的に判断しましょう。
勤務先の福利厚生が充実している
勤務先の福利厚生制度が充実している場合、民間の医療保険にわざわざ加入しなくても問題ないかもしれません。
福利厚生の内容をよく確認し、医療費に対する備えが十分かどうかチェックしてみましょう。
健康状態に対する不安が小さい
大きな病気やケガに対する不安度が低い人は、医療保険に無理に入る必要はないでしょう。
特に他の出費がかさんでおり、医療保険よりも優先したいものがある場合は、経済的な余裕が生まれたタイミングで再度検討するのがおすすめです。
ただし、病気やケガはいつ起こるかわかりません。年齢を重ねるごとに病気やケガのリスクは高まりますし、予期せぬ事故に遭う可能性もあります。病気やケガに対する不安が強くなったら、早めに医療保険への加入を検討しましょう。
医療保険が必要な人の特徴

一方で、医療保険の必要性が高い人の特徴は以下のとおりです。
- 貯蓄額に不安を感じている
- 結婚や出産を予定している
- 病気やケガに対する不安が強い人
貯蓄や収入面で不安を感じるのであれば、おまもりとして医療保険に入っておくのがおすすめです。
貯蓄額に不安を感じている
入院や手術などの医療費を支払うだけの十分な貯蓄がない人は、医療保険の必要性が高いです。医療保険に入っておけば、病気やケガによる経済的なリスクにしっかり備えられます。
貯蓄が少ない人の中には「多額の治療費を払うのも難しいけど、いま医療保険の保険料が増えるのもちょっと…」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、保険料がもったいなく感じるから「医療保険は不要」という考えは少々危険です。もし、もったいないと感じて医療保険に入っていないタイミングで「ガン」や「心疾患」などで倒れてしまったらどうでしょうか。
十分な治療費を払える状況にあれば不幸中の幸いですが、仮に支払いが難しかったとしたら当面の生活は言わずもがな行き詰ってしまいます。
そのような事態を避けるためにも、十分な貯蓄額が用意できてない人は医療保険の加入を検討してみましょう。
結婚や出産を予定している
結婚や出産などのライフイベントを控えている人は、そうでない人よりも医療保険の必要性が高いです。万が一、病気やケガをして働けなくなった場合、家族の生活を守らなければなりません。
また結婚をして家族が増えると、子育てや住宅ローンでお金がかかってしまいます。家計に余裕がない場合には、保険料が安いうちに医療保険へ加入しておくのがおすすめです。
お金がかかる時期に、高額ではないといえど「医療費の負担」がかさなると家計にとって大きなダメージになりかねませんからね。
病気やケガに対する不安が強い人
もしも自分がガンだったら、突然、脳腫瘍など大きな病気になってしまったら…と人よりも「病気」への不安を大きく感じてしまう人はいませんか?
人間誰しも病気に対して不安を感じるのは、なにもおかしいことではないので安心してください。
結論として「健康状態や病気にかかることへの不安が大きい人」や「先進医療などさまざまな治療方法を選べるように保障を手厚くしたい人」は医療保険に加入したほうが良いと考えます。
なぜなら、医療保険に入っておけばある程度「病気への不安」が軽減されストレスも減ることが期待できるからです。
強い不安を感じる方は損得勘定ではなく「安心」のために医療保険への加入を検討してみましょう。
医療保険へ加入する場合「自分にとって必要なもの」に絞ることが重要

ただし、闇雲に医療保険に入り手厚い保障をつければ良いわけではありません。それこそ「医療保険の比較検討をしないのはもったいない」です。
ですから、医療保険で必要な補償は何なのか。手厚くしたい補償は何なのかなど、しっかりと医療保険を選ぶことが重要です。
まとめ
この記事では、医療保険はいらないのか、必要なのかを考察してきました。
医療保険をはじめとした「保険」は判断を誤ると思わぬ後悔を生みかねません。しっかりと商品性などを理解し、自分にあった保険選びをしましょう。
医療保険はいる・いらないに関するよくある質問

貯金もしくは投資にお金を回すのと、医療保険料に回すのとどちらがおすすめですか?
投資と保険は異なる金融資産で一概に比較することはできませんが、経済合理性でいえば「投資」のほうが優れています。病気を患ってしまったときに必要資金が用意できるかどうかの「確実性」の観点では医療保険のほうが優れています。
貯金がいくらあれば医療保険は不要でしょうか?
どのような病気にかかるかは誰にもわからないため、一概に「〇〇円貯まっていれば大丈夫」とお伝えするのは難しいです。最終的には、個々人の不安度の強さによって必要性が決まります。
参考程度に、入院費用の平均額を確認してみましょう。「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》」において、1日あたりの入院費用は平均25,800円と報告されています。
もし手術が必要となれば、さらに追加で費用が必要です。厚生労働省が調査した令和3年度の「生涯医療費」は、約2,800万円にものぼります。貯金だけでカバーする場合、多くの貯金が必要になるでしょう。
医療保険に加入していて支払った保険料が無駄になったり、損する可能性はありますか?
金額的には無駄になる可能性はあります。しかし加入期間は医療費への心配が軽減されるというお金以外のメリットがあるので、一概にどちらが損、得と言い切ることはできません。
あなたがお金のデメリットと、精神面でのメリットどちらを重要視するかで判断してみてはいかがでしょうか。
高齢者は医療保険がいらないって本当ですか?
公的医療保険において、高齢者は若年層に比べてさらに手厚く医療費の補助が受けられます。そのため、老後に医療保険は必要ないという意見を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、高齢になるほど入院や手術が必要になるリスクは高くなります。また年金受給額に不安を感じる方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
老後であっても、医療費に対する不安はむしろ強くなる可能性が高いです。医療保険に入っておけば、病気やケガにもしっかり備えられるため安心ですね。
しかし、加入する年齢が高くなるほど、毎月の保険料も高額になります。医療保険で老後の医療費に備えたいのであれば、なるべく早く加入しておくのがおすすめです。
医療保険に入らないと後悔しますか?
先進医療を受けたい、差額ベッド代や入院費など「病気になった場合」は、自分が望む治療を受けたいと考えている場合は医療保険へ加入しておくことをおすすめします。未加入で大病を患ってしまうと、資金が足りず自分が望む治療が受けられず「後悔する可能性」があるからです。
何歳から医療保険への加入を考えるべきですか?
ライフイベントの前、または病気になるリスクが高くなったタイミングがおすすめです。
結婚して子供が生まれるタイミングや、40代になり統計的な病気のリスクが高くなったタイミングで加入を検討する方が多いです。
最低限必要な保険は、3種類あるって本当ですか?
生命保険、医療保険、がん保険の3つは「入っておいたほうが良い保険」として有名です。
しかし、本当に全て加入しておく必要があるのでしょうか。結論として病気に対する不安が大きく、治療費を全て自分で賄える自信がない人は加入しておいたほうが安心できます。
- 生命保険→被保険者が死亡してしまった場合、遺族へ保険金が支払われる
- 医療保険→入院費、治療費、先進医療費など療養費がカバーできる保険
- がん保険→医療保険とはことなり「がん」に特化した保険
病気への不安を払拭したいのであれば、毎月の余裕資金の範囲内で加入することを推奨いたします。後悔先にたたずですからね。