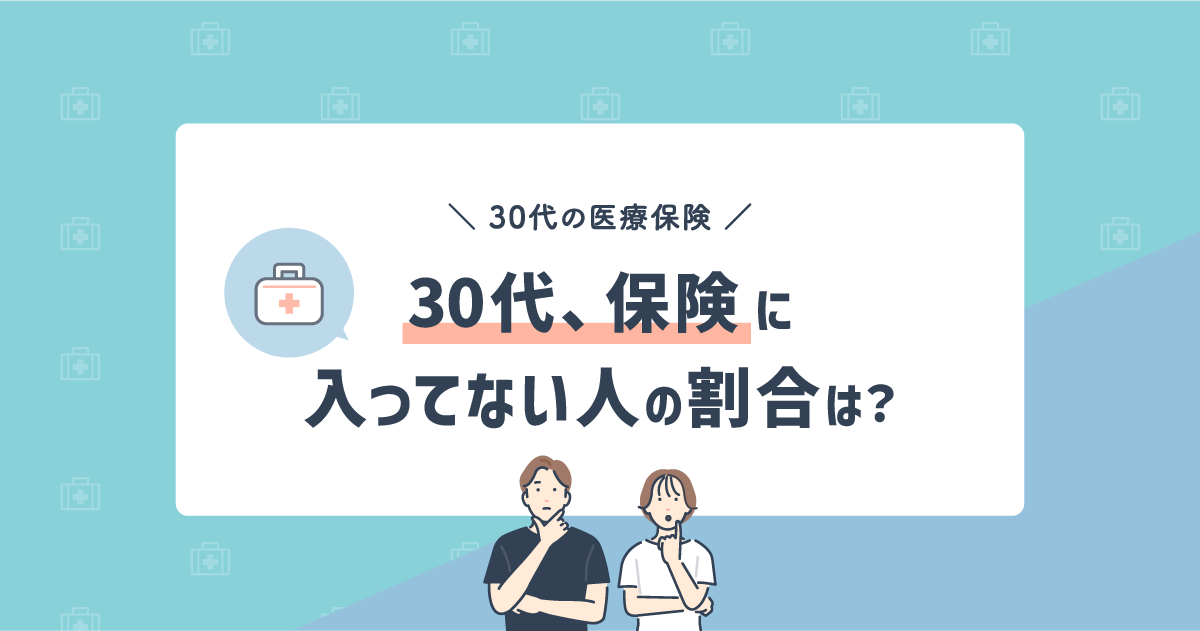医療保険に加入することは、将来の医療費を予測できない不安な状況に備えるために重要です。しかし、医療保険への加入には費用がかかるため、入らない選択をする人もいます。
また、日本には公的医療保険制度があるため、民間の医療保険に必要性を感じられないという人も多いのではないでしょうか。
では、本当に医療保険に入らないと後悔するのか?
本記事では、医療保険に入らないで後悔した人の具体例を交えながら、入った方が良い人、入らなくてもいい人の特徴を解説します。
医療保険に入らないことが原因で後悔してしまうケース
まずは、医療保険に入らなかったために後悔してしまうケースを紹介します。
①大部屋が満床で差額ベッド代がかかった
個室や少人数部屋に入院した際にかかる差額ベッド代は、健康保険の適応外です。
お金に余裕がないため大部屋を希望しても、大部屋が満床で個室入院になった際には差額ベッド代がかかることがあります。
②先進医療を受けようとしたら全額自己負担だった
新薬や最新の治療法は、保険適用外のものが多く、高額な費用がかかる場合があります。
自分が希望する治療が費用面で受けられないのは、大きな不安材料ですよね。仮に医療保険の先進医療保障を付保してあれば、自己負担額を大きく軽減できる可能性があります。
③高額療養費制度を活用しても自己負担額が大きくなってしまった
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額が公的医療保険から払い戻される制度のこと。
しかし、高額療養費制度を使ったとしても「限度額まで」は自己負担になってしまいます。
(自己負担割合は1~3割)

1ヶ月程度の比較的短い療養であれば、家計へのダメージもそこまで大きくならないかもしれませんが、これが数ヶ月から年単位になると、自己負担となった医療費も大きくなってしまいます。
結果として、貯蓄が大きく減ってしまったり、家計が圧迫されてしまう可能性があるのです。
④入院が長引いたことで収入が減ってしまった
入院が長引くと、給与や賞与の減額、ボーナスカットなどの経済的な負担が大きくなる可能性があります。
医療費による家計の圧迫と収入源が重なると生活が困窮してしまう恐れがあります。こうした事態に備えるためにも医療保険への加入検討は非常に重要になります。
医療保険に入っていない人の割合は?

医療保険に入ることは、突然のケガや病気に備える上で大切なことです。しかし、保険料の負担や保険内容の複雑さにより、医療保険に加入していない人も多いのではないでしょうか。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると令和元年度における医療保険(疾病入院給付金の支払われる生命保険)の加入率は約73.1%とされています。

つまり約3割弱の人は医療保険に入っていないということになります。
医療保険に入らない人の主な意見
従来、「加入は当たり前」とされてきた医療保険ですが、中には加入しないという選択をする人も増えています。
医療保険に入らない人の意見にはどのようなものがあるのでしょうか。。
※あくまで意見であり、これらの意見を肯定・否定するものではありません。
1. 高額療養費制度で十分だから
高額療養費制度とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に、自己負担額を上限まで軽減してくれる制度です。医療保険に入っていない人の中には、「高額療養費制度で十分なサポートを受けられる」と考えている人がいます。
2. 医療費は貯蓄で賄えるから
健康的な生活習慣を心がけ、病気や怪我のリスクを低く抑えれば「医療費は貯蓄で賄える」と考える人もいます。実際、医療保険に加入せずに、数百万円の貯蓄を準備している人もいるようです。
3. 民間保険は高額で必要ないと思うから
国民健康保険に加入していれば、入院や通院の費用の一部が負担されます。そのため、高額な民間保険に入る必要はないと考える人もいます。
4. 自己責任でリスクを管理しようと考えているから
「病気や怪我のリスクは自己責任で管理すべき」という考えを持つ人もいます。健康に自信があれば、あえて保険に入る必要はないと考えるようです。
以上が、医療保険に入らない派の主な意見です。
こうした意見がある一方で、医療保険に入らないリスクももちろん存在します。具体的にどういったリスクがあるのでしょうか。次の章で詳しく解説していきます。
医療保険に入らないと後悔する?入らないことによるリスク

医療保険に入らないことで起こり得るリスクについて説明します。
医療保険に入らないことの主なリスク
- 長期入院や手術などの高額な医療費のリスク
- 先進医療が自己負担となってしまうリスク
特にこのように考えている人は必読です。
長期入院や手術などの高額な医療費のリスクにより生活が困窮してしまうリスク
医療保険に加入していない場合、長期入院や手術などの高額な医療費が発生した場合、自己負担が大きくなるため、多額のお金が必要になります。
日本では公的医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)に加入することが義務づけられており、病気・ケガで療養を受けた場合に患者が負担する医療費は全体の医療費の1割~3割となっています。
加えて公的医療保険には、月の医療費が一定額を超えると超過した分が払い戻される高額療養費制度があるため「公的医療保険に加入していれば民間の医療保険は必要ない」と考える方もいますよね。
しかし、公的医療保険では、以下のような入院にかかる費用は自己負担になります。
公的医療保険の対象外になる主な費用
- 差額ベッド代:平均2,800〜6,354円/日
- 食事代(460円/食)
- 家族の見舞いにかかる交通費・宿泊費
- 先進医療費
- 着替えやスキンケアグッズなどの消耗品
- 家族の生活費や家賃
- 入院サポートをするため、ご家族の方が仕事を休んだ際の収入
- 保険外の診療
中央社会保険医療協議会(第466回、令和2年9月16日)「主な選定療養に係る報告状況」
このように、公的医療保険の対象外となる費用は意外に多く、高額療養費制度を利用した場合でも月の負担額が8万円〜9万円程度かかるとされています。
また、自己負担額が1割から3割といっても、それが何ヶ月も続くと自己負担額もかさんでしまいます。仮に毎月1万円の自己負担で済んでいたとしても、それが数ヶ月〜1年以上続いたとすれば10万円単位の出費に。
医療保険に加入していない場合は、自己負担のリスクが高いことを念頭に置いておきましょう。
先進医療が自己負担となってしまうリスク|医療費が足りず治療の選択肢が減ってしまうことも
厚生労働省が認めた高度な医療技術や治療法を用いる「先進医療」は公的医療保険の保証対象外になるため、自己負担になってしまうリスクがあります。
実際に先進医療の技術料としてかかる費用の一部は以下のとおりです。
MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法
平均入院期間が2.6日で、年間1,338件実施され、1件あたりの技術料は108,183円。
陽子線治療
平均入院期間が15.7日で、年間1,285件実施され、1件あたりの技術料は2,649,978円。
重粒子線治療
平均入院期間が5.2日で、年間683件実施され、1件あたりの技術料は3,186,609円。
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
平均入院期間が4.0日で、年間614件実施され、1件あたりの技術料は27,863円。
中央社会保険医療協議会「令和3年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」
一番多く実施された「MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法」は、前立腺がんかどうかの確定診断を行う技術になります。
次いで実施件数の多い「陽子線治療」「重粒子線治療」は癌治療です。
癌は「心疾患」「脳血管疾患」と並ぶ三大疾病で、日本人の死因の約3割を占めています。
三大疾病は生死にかかわる重大な病気であり、治療が長期化して医療費がかさんだり、回復しても元のように働けなくなって収入が減少してしまったりと、経済的に困窮してしまう可能性もありますよね。
医療保険に入らないことで、三大疾病という誰もがなりうる病気への備えも不十分になってしまうのは大きなリスクと言えるでしょう。
医療保険に入らないと後悔する人の特徴は?

では、医療保険に入らないことで起こり得るリスクについて理解した上で、医療保険に入らないと後悔する人はどのような人なのでしょうか。
また、医療保険はどういった人にとって必要なのでしょうか。
医療保険に入らないと後悔してしまうリスクが高い人
以下のどれかにあてはまる人は、医療保険に入らないと後悔してしまう可能性があります。
| 医療保険に入らないと後悔する人 | 具体例 |
|---|---|
| ①十分な預貯金が無く金銭面で不安がある人 | 急な入院手術に30万かかったがまとまったお金がないので払えず、家族に借りた。 |
| ②フリーランスや自営業の人 | 退院後、3カ月間は時間を短縮して仕事をしたため、収入が大幅に減って生活が厳しい。 |
| ③20代〜30代の働き世代 | 入院中、個室を希望したため、公的医療保険制度対象外の医療費がかかった。結婚に向けて貯蓄していた分が減り、仕事も長く休んだのでキャリアアップが見込めず将来が不安になった。 |
預貯金に不安がある人はもちろんですが、フリーランスや自営業の方は必読です。
①十分な預貯金が無く金銭面で不安がある人
十分な預貯金が無く金銭面で不安がある人は、医療保険に加入することをおすすめします。
例えば突然の怪我や病気で長期の入院が必要になった場合、医療費やベッド代の他にも家の家賃や携帯電話の通信費など、固定費は掛かり続けますよね。
また、直近の入院時の自己負担費用(高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額)は次のとおりであり、平均額は19.8万円かかるそうです。

※出典 : 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査
①の具体例のように、まとまったお金がないと親族や消費者金融にお金を借りて医療費を払わなくてはいけなくなってしまうリスクがあります。そうなった時に、預貯金が十分でない人は、こうした「万が一の傷病時」に困窮してしまう可能性があるため、医療保険に加入しておいたほうが後悔せず済む可能性が高くなります。
②フリーランスや自営業の人
フリーランスや自営業の人は医療保険に加入することをおすすめします。
一般的に会社員は健康保険、フリーランスや自営業の方は国民健康保険に加入しますが「健康保険」と「国民健康保険」は同じ制度では無いからです。
例えば、健康保険にはケガや病気で仕事ができず、収入が得られなかったときに保障を受けられる「傷病手当金」という制度がありますが、国民健康保険にこのような制度は基本的にありません。
そのため、ケガや病気で収入を得ることができなくなってしまうと、完全に収入がなくなってしまう恐れがあるのです。
フリーランスや自営業に限ったことではありませんが、退院後は時間を短くして働いたり、仕事内容を軽くするなどして様子をみる時間が必要な場合があります。
こうした不測の事態に備えるべく、フリーランスや自営業の方は医療保険に加入することをおすすめします。
③働き盛り世代(20代〜30代)
20代中盤から30代は培ってきた経験を活かし、キャリアアップに加えて、結婚、出産、マイホームの購入など、多くのライフイベントを控えている時期。仕事においても家庭においても責任が増えるので、働けなくなった時に備えて準備が必要です。
万が一病気や怪我で医療費がかかったとき、公的医療保険制度が適用される場合は3割負担で済みますが、公的医療保険制度対象外で高額な医療費がかかってしまうこともあります。
どちらにしても収入が減ったり、貯蓄がなくなったときは、将来の資金を取り崩さなくてはいけなくなります。これからまとまったお金が必要な時期にこのような状態になると不安ですよね。
自己負担を減らし、将来の不安を軽減したい方は医療保険の加入をおすすめします。
医療保険が必要ない・入らなくてもよい人
以下のどちらかに当てはまる人は、医療保険が必要ない可能性があります。
医療保険に入らなくても後悔しない人
- 預貯金が十分にある人
- 健康保険に加入している会社や公務員(条件付き)
医療保険が必要ない人は「莫大な資産を持っている人だけ」と言っても良いでしょう。
預貯金が十分にある人
貯金が十分であり、莫大な資産を持っている場合は医療保険は不要でしょう。
急なケガや病気でまとまったお金が必要になっても預貯金から医療費が余裕で賄えるなら医療保険に入らなくても後悔はしないですよね。
- 独身で保険に加入しなくても治療費を余裕で負担できる人
- 専業主婦・主夫で世帯主の稼ぎが十分にある人
- 収入が十分にある家庭の子供
上記に当てはまる人は、公的医療保険を活用しながら、不足分は自分または世帯主の収入や資産でまかなう方が費用がかからない可能性があります。
健康保険に加入している会社員や公務員
国民健康保険よりも手厚い制度のある「健康保険」に加入している会社員や正社員の方は、ある程度不測の事態に備えることができているため、医療保険は必要ないとも言えます。
しかし、健康保険ではカバーできない費用もあるため、そこは自分の貯金で賄える方に限るでしょう。
毎月いくらまでなら突然の出費に耐えられるのかをしっかりと考え、長期入院等にも対応できるかどうかしっかりと試算しておくことをおすすめします。
自分で今の預貯金・収入で医療費を賄えるかどうか判断が難しいという人は、保険のプロに相談するのも一つの手です。
医療保険に入ることで得られるメリットは?

医療保険に入ることで得られるメリットは多岐にわたります。健康に関する不安を取り除くことはもちろんのこと、経済的な安心感も得ることができます。医療保険に加入することで得られる具体的なメリットは以下のとおりです。
- 公的医療保険と比べてカバー範囲が広く、特定の疾病や先進医療へ備える事ができる
- 精神的不安を軽減できる
- 貯蓄が少なくても万が一の時に医療費をカバーすることができる
- 税金の控除を受けることができる(少額短期保険は除く)
公的医療保険と比べてカバー範囲が広く、特定の疾病や先進医療へ備える事ができる
医療保険は疾病やケガに対してカバーする範囲が広く、高度な医療技術である先進医療も対象となっています。
また「女性疾病入院特約」や「生活習慣病(成人病)入院特約」を付けることで、特定の疾病に対する保障も付帯することができるため、特に心配な病気がある人も安心して備える事ができるのです。
民間の医療保険に付帯できる特約には、以下のようなものがあります。
先進医療特約
公的医療保険の対象にはならない先進医療を使った治療を受けた場合に技術料が保障されます。
三大疾病一時金特約
三大疾病である「がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞(心疾患)、脳卒中(脳血管疾患)」を発症した際に一時金が支払われます。
女性疾病特約
乳がん、子宮がん、子宮筋腫など、女性特有の病気により入院した際に保障が手厚くなる特約です。通院特約病気やケガで入院をして、退院後(または入院前)にその病気やケガで通院が必要になった場合に給付金が出る特約です。
就業不能特約
病気やケガによって働けなくなってしまい、収入が減少したり途絶えたりしたときに、一定の条件のもと保険金や給付金を受け取れる特約です。
また、民間の医療保険の保険金は、治療費や薬に対する支払い以外に使用することもできます。たとえば、差額ベッド代や入院中の食事代としても使用できるのです。
このように、民間の医療保険は公的医療保険よりもカバー範囲が広く、公的制度では足りない部分を補うために役立つものになっています。
自分の年齢・性別で医療保険に特約をつけるといくらになるのか知りたい方は、実際に見積もりを取ってみましょう。
精神的不安を軽減できる
病気やケガで医療費や入院が必要になった場合、急なまとまった出費を心配することがありますよね。
しかし、いざという時のために医療保険に加入しておくことで、治療費の負担を軽減することができるため経済的にも精神的にも不安を軽減することができます。
また、日本の公的医療保険は今後もずっと今の保障内容が続くとは限りません。
日本は高齢化に伴い医療費が増え続けていることから、現在の公的医療保険の水準を維持していけるかどうか分からない状態と言えます。
将来公的医療保険の保障内容が変わり、自己負担が増えてしまう可能性も考えて民間の医療保険に加入しておくと、いざという時も安心でしょう。
貯蓄が少なくても万が一の時に医療費をカバーすることができる
自分や家族がケガや病気になった場合、急な医療費の支払いが必要になることもあります。しかし、医療保険に加入している場合、貯蓄が少なくても医療費をカバーすることができます。
例えば「社会人になったばかりで貯金が少ない」「結婚したばかりで貯蓄が少ない」といった場合でも、生活が安定するまでの一定期間を、保険料が手頃な「定期型医療保険」に加入して備えるという事もできるのです。
しかし、定期型医療保険は保険料が安価である反面、更新し続けると同じ保障内容であっても保険料が上がってしまうため、あくまでも「一時的な保障」として活用することが望ましいでしょう。
税金の控除を受けることができる
医療保険に加入することで、所得税や住民税の控除を受けることができます。
医療保険に支払う保険料は「生命保険料控除」の対象となり、これから新しく医療保険に加入する方なら、最大4万円まで控除を受けられるのです。
※少額短期保険は控除の対象外
医療保険に加入することで「経済」「精神」「税金」の3つの負担を軽減することができると言えるでしょう。
医療保険に入るデメリットは?

医療保険は予測不可能なリスクに備える上で重要な存在ですが、一方で入ることによるデメリットも存在します。
主なデメリット
- 保険金として毎月の固定費が増える
- 健康状態によっては受け取る給付金よりも支払う保険料の方が多くなってしまう
保険料として毎月の固定費が増える
当然のことにはなりますが、保険に加入するという事は毎月保険金の支払いが発生するということになります。
預貯金に余裕がない場合、もしもの時に備えて医療保険に加入したほうが良いのは確かですが、保険料の負担が重くなって普段の生活を圧迫するのは好ましくありません。
そのため、医療保険に加入する前に相見積もりをとって金額的にも内容的にも「自分に合った」医療保険を選ぶことが大切です。
健康状態によっては受け取る給付金よりも支払う保険料の方が多くなってしまう
医療保険に加入しているのに一度も使う機会がないと損をした気分になってしまいますよね。
医療保険は満期や更新、中途解約時などにお金が戻ってこない「掛け捨て型」が一般的です。
つまり、掛け捨て型で加入した場合は貯蓄性がなく、長年保険料を支払っていても解約時に解約返戻金を受け取ることはできません。
保険を使う機会がないという事は、健康的に過ごせているということなので喜ばしいことなのですが、掛け捨て型の場合は保険料は戻ってこないという点は覚えておきましょう。
まとめ

今回は、医療保険に入らないことのリスクから、医療保険に入らないで後悔する人までを解説しました。
医療保険に入ることで万が一のときにも安心することはできますが、保険料の負担が重くなって普段の生活を圧迫するのは好ましくありません。
この記事を読んで「医療保険に入らないと後悔する人」に当てはまった方は、相見積もりをとって金額的にも内容的にも「自分に合った」医療保険を選んでみてはいかがでしょうか。